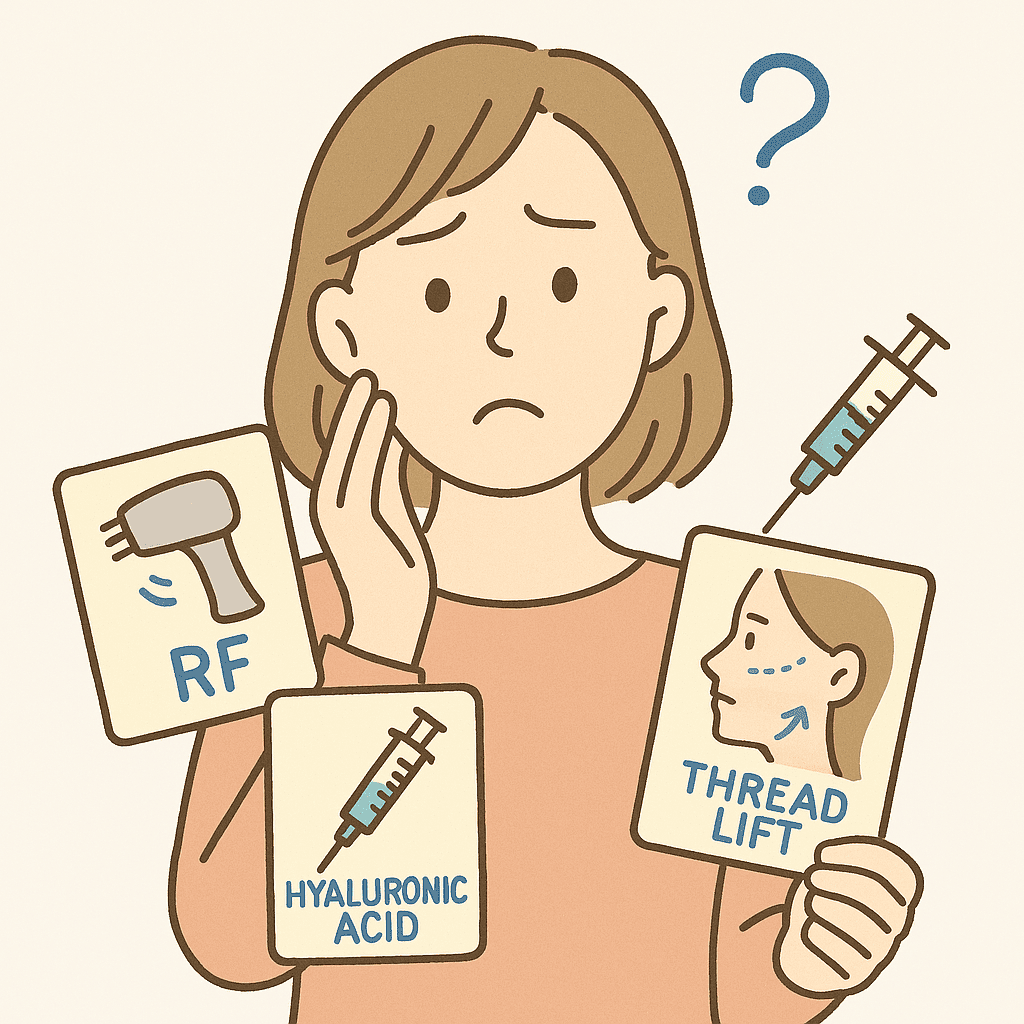
「最近、なんだか鏡を見るのが少し憂鬱…」「もう少しだけ、あの頃の自分に近づけたら…」 年齢を重ねる中で、多くの方が抱く「若々しくありたい」という願い。そして、その願いをサポートする美容医療の選択肢は、HIFU(ハイフ)やRF(高周波)、レーザーや光治療、ヒアルロン酸やボトックス注射、糸リフト、さらには美容整形と、本当にたくさんありますよね。
でも、いざ治療を考えてみると、「どれがいいの?」「本当に効果はあるの?」「痛くない?」「高そう…」など、次から次へと疑問が湧いてくるのではないでしょうか。インターネットで情報を集めても、どれが本当か分からなくなったり、かえって不安が募ったりすることも。
この記事では、美容医療の専門家として長年多くの患者様のお悩みに向き合ってきた経験から、そんなあなたの「知りたい!」に、Q&A形式でズバリお答えしていきます。難しい専門用語はできるだけ使わず、日常の「なるほど!」に繋がるような例え話を交えながら、それぞれの治療法の疑問をスッキリ解決していきましょう。
この記事を読み終える頃には、若返り治療に対する不安が軽くなり、ご自身に合った選択をするための一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。さあ、一緒にギモン解決の旅に出かけましょう!
若返り治療全般についての「これってどうなの?」Q&A
まずは、特定の治療法に限らず、若返り治療全般に関してよく寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 若返り治療って、何歳から始めるのがベストタイミングなの?
A1. 「何歳から」という決まりはありません。気になった時が始め時、そして「予防」という考え方も大切です。
「もうこんな年齢だし…」と諦めたり、「まだ若いから早いかな?」とためらったりする必要はありません。若返り治療を始めるのに、「早すぎる」「遅すぎる」ということは一概には言えないのです。
医学的には、肌の老化は20代後半から徐々に始まっていると言われています。例えば、肌のハリを保つコラーゲンは、20歳頃をピークに年齢とともに減少し始めます。ですから、肌の変化を感じ始めたタイミング、例えば「最近、ほうれい線が気になるな」「目元の小ジワがファンデーションで隠しきれないな」と感じた時が、一つの検討し始めるタイミングと言えるでしょう。
これは、お部屋の掃除に例えると分かりやすいかもしれません。汚れがひどくなってから大掃除をするのは大変ですが、こまめに掃除をしていれば、いつもキレイな状態を保ちやすいですよね。肌も同じで、老化のサインが深くなる前にケアを始めることで、より少ない負担で良い状態をキープしやすくなります。これを「予防的治療」と呼び、最近では30代前半からHIFUや光治療などを定期的に受けることで、将来のたるみやシミを予防しようと考える方も増えています。
もちろん、40代、50代、あるいはそれ以上の年齢であっても、気になる悩みに合わせた治療法はたくさんあります。大切なのは、ご自身の年齢や肌の状態、そして「どうなりたいか」という希望を医師に伝え、最適なプランを一緒に考えることです。
Q2. 効果ってどれくらい続くの? 一度やったら、もうずっと大丈夫?
A2. 治療法によって持続期間は様々。そして、残念ながら「一度で永久」という魔法はありません。老化は進み続けるので、メンテナンスも視野に。
「せっかく治療するなら、効果が長持ちしてほしい!」そう思いますよね。効果の持続期間は、治療の種類、使用する薬剤や機器、そして個人の体質や生活習慣によって大きく異なります。
例えば、ヒアルロン酸注射は約半年~2年程度、ボトックス注射は約3ヶ月~半年程度が一般的な目安です。HIFUやRF、糸リフトは半年~1年半程度、レーザーや光治療はシミの種類や肌質改善の目的によって異なりますが、効果を維持するためには定期的な施術が推奨されることが多いです。美容整形(フェイスリフトなど)は、他の治療法に比べて効果の持続期間が長く、5年~10年以上と言われることもありますが、これも老化が止まるわけではありません。
なぜ「一度で永久」ではないのか? それは、私たちの体は常に変化し、残念ながら老化も日々進行しているからです。治療によって時計の針を少し戻せたとしても、その時計が完全に止まるわけではないのです。それは、どんなに素晴らしいエンジンオイルを入れても、車が走り続ければいずれまたオイル交換が必要になるのと同じようなものです。
ですから、多くの若返り治療は、効果を維持したり、さらに良い状態を目指したりするために、定期的なメンテナンスや追加の治療が必要になることを理解しておくことが大切です。医師と相談しながら、ご自身のライフスタイルや予算に合った長期的なプランを立てていくと良いでしょう。
Q3. 痛みがとにかく心配…。治療って、やっぱり痛いんでしょうか?
A3. 治療法によって痛みの程度は異なりますが、多くの場合は麻酔や冷却でコントロール可能です。遠慮なく医師に相談しましょう。
「痛いのはイヤ!」これは、美容医療をためらう大きな理由の一つですよね。痛みの感じ方には個人差がありますが、各治療法の一般的な痛みの程度と、それを和らげるための対策についてご説明します。
- 比較的痛みが少ない治療:光治療(IPL)は温かい感じや軽く輪ゴムで弾かれる程度、一部のRF(高周波)治療は温かいマッサージを受けているような感覚と言われます。
- 多少の痛みを伴うことがある治療:
- HIFU:骨に近い部分はズーンと響くような痛みや、チリチリとした熱感を感じることがあります。
- レーザー治療:シミ取りレーザーは輪ゴムで強く弾かれるような痛み、フラクショナルレーザーなどは熱感を伴うことが多いです。
- ヒアルロン酸・ボトックス注射:針を刺すチクッとした痛みや、薬剤が入る時の鈍い圧迫感があります。
- 糸リフト:局所麻酔をするので施術中の痛みは少ないですが、麻酔の注射自体に痛みがあります。
- 痛みが強いとされるが、麻酔でしっかり対応する治療:
- 美容整形(フェイスリフトなど):全身麻酔や静脈麻酔、局所麻酔など、手術内容に応じた麻酔下で行うため、手術中に痛みを感じることはありません。術後の痛みは鎮痛剤でコントロールします。
多くのクリニックでは、痛みを最小限に抑えるために様々な工夫をしています。例えば、麻酔クリームを塗ったり、施術部位を冷却したり、笑気ガス(リラックス効果のあるガス)を吸入したり、場合によっては静脈麻酔(点滴で眠くなる麻酔)を用いたりすることもあります。
想像してみてください。歯の治療でも、昔は麻酔なしで痛い思いをしたかもしれませんが、今はしっかり麻酔をしてくれるので安心して治療を受けられますよね。美容医療も同じです。痛みが心配な方は、カウンセリングの際に遠慮なく医師に伝え、どのような痛み対策があるのか、自分に合った方法はあるのかをしっかり相談しましょう。「痛みに弱いんです」と一言伝えるだけでも、医師や看護師はより配慮してくれるはずですよ。
Q4. ダウンタイムってどれくらい? すぐに普段通りの生活に戻れるの?
A4. これも治療法によって大きく異なります。「ほぼゼロ」から「数週間~数ヶ月」まで。ご自身のライフスタイルに合わせて選びましょう。
ダウンタイムとは、治療を受けてから通常の生活に戻れるまでの回復期間のこと。赤み、腫れ、内出血、かさぶたなどが主な症状です。これも治療法を選ぶ上で重要なポイントですよね。
- ダウンタイムがほとんどない、または非常に短い治療:
- 光治療(IPL):施術直後からメイク可能な場合が多いです。
- RF(高周波):機種によりますが、赤みが数時間程度で引くものが主流です。
- ボトックス注射:まれに注射部位に小さな内出血が出ることがありますが、メイクで隠せる程度です。
- ヒアルロン酸注射:こちらもまれに内出血や軽い腫れが出ることがありますが、数日で治まることが多いです。ただし、注入部位や量によっては少し長引くことも。
- ダウンタイムが数日~1週間程度の治療:
- HIFU:軽い赤みや腫れ、筋肉痛のような鈍痛が数日続くことがあります。
- レーザー治療:シミ取りレーザーの場合、施術後に保護テープを貼ったり、かさぶたができたりすることがあり、それが取れるまでに1~2週間かかることも。レーザートーニングのようなマイルドなものはダウンタイムがほとんどありません。
- 糸リフト:腫れや内出血、口の開けにくさ、ひきつれ感などが1~2週間程度続くことがあります。髪の毛で隠せる範囲のことが多いです。
- ダウンタイムが比較的長い治療(数週間~数ヶ月単位):
- 美容整形(フェイスリフトなど):手術なので、術後の腫れや内出血は避けられません。大きな腫れは2週間~1ヶ月程度、細かいむくみや硬さが完全に落ち着くまでには3ヶ月~半年以上かかることもあります。
「週末だけ休める」「1週間くらいなら何とかなる」「まとまった休みが取れる」など、ご自身のライフスタイルや仕事の状況によって、許容できるダウンタイムは異なりますよね。これは、旅行の計画を立てるのに似ています。日帰り旅行もあれば、海外旅行のように長期の休みが必要なものもあります。ご自身のスケジュールと照らし合わせて、無理のない治療法を選ぶことが大切です。医師とのカウンセリングで、予想されるダウンタイムの具体的な期間や症状、その間の過ごし方についてもしっかり確認しましょう。
Q5. 費用はどれくらいかかるの? 保険は使えないって本当?
A5. 美容目的の治療は基本的に自由診療(保険適用外)です。費用は治療法やクリニックによって大きく異なります。
費用のことも、もちろん気になりますよね。まず大前提として、若返りを目的とした美容医療は、病気の治療ではないため、原則として健康保険は適用されず「自由診療」となります。つまり、費用は全額自己負担です。
費用は、治療の種類、使用する機器や薬剤の量、施術範囲、そしてクリニックによって大きく異なります。あくまで一般的な目安としてお考えください。
- 比較的トライしやすい価格帯(1回あたり数万円~十数万円程度):
- 光治療(IPL)、一部のレーザー治療(レーザートーニングなど)
- ボトックス注射(部位による。例えば眉間のみなら数万円程度から)
- ヒアルロン酸注射(注入量1本あたりで計算されることが多い)
- 中程度の価格帯(1回あたり十数万円~数十万円程度):
- HIFU、RF(顔全体など広範囲の場合)
- 糸リフト(使用する糸の本数や種類による)
- シミ取りレーザー(シミの数や範囲が広い場合)
- 比較的高額になる傾向(1回あたり数十万円~百万円以上):
- 美容整形(フェイスリフトなどの手術)
- 広範囲かつ複数回のレーザー治療や、高スペックな糸を多数使用する糸リフトなど
「安いから良い」「高いから効果がある」と一概には言えません。大切なのは、その費用に見合う効果や満足感が得られるかどうか、そして無理なく支払える範囲かどうかです。多くのクリニックでは、カウンセリング時に明確な見積もりを出してくれます。治療費以外に、初診料や再診料、麻酔代、薬代などが別途かかる場合もあるので、総額でいくらになるのかをしっかり確認しましょう。
これは、洋服を買うのに似ているかもしれません。ファストファッションもあれば、高級ブランドもありますよね。どちらを選ぶかは、あなたの価値観や予算、そして「何を得たいか」によります。高価な治療が必ずしもあなたにとってベストとは限りませんし、逆に安価な治療でも満足できる場合もあります。医師とよく相談し、納得のいく費用で、価値ある治療を選びたいですね。
Q6. たくさん治療法があって、どれが自分に合うのかサッパリ分かりません…。
A6. まずはご自身の「一番気になる悩み」と「どうなりたいか」を明確に。そして、専門家である医師に相談するのが一番の近道です。
HIFU、レーザー、注入、糸、手術…本当にたくさんの選択肢があって、迷ってしまいますよね。「自分には何が合っているんだろう?」と悩むのは当然です。
自分に合った治療法を見つけるためのステップは、まず「自分の悩みと向き合うこと」から始まります。
- 一番気になる悩みは何か?:たるみ?シワ?シミ?それとも全体的なハリ不足?一つだけでなく複数ある場合は、優先順位をつけてみましょう。
- どんな状態になりたいか?:「ほうれい線を浅くしたい」「フェイスラインをスッキリさせたい」「肌に透明感がほしい」など、具体的な目標をイメージしてみましょう。
- 治療にかけられる時間(ダウンタイム)や予算はどれくらいか?
- 痛みに対する許容度は?
- 「自然な変化」を望むか、「ある程度の変化」を望むか?
これらの点を自分なりに整理しておくと、医師とのカウンセリングがスムーズに進みます。 そして何より大切なのは、「専門家である医師に相談する」ことです。医師は、あなたの肌の状態を診察し、あなたの希望やライフスタイルを考慮した上で、最適な治療法や治療プランを提案してくれます。それはまるで、旅行のコンシェルジュに「こんな旅がしたいんだけど、どこがいいかな?」と相談するのに似ています。プロの視点からのアドバイスは、あなた一人で悩んでいるよりもずっと的確で、安心できるはずです。
複数のクリニックでカウンセリングを受けて、色々な医師の意見を聞いてみる(セカンドオピニオン、サードオピニオン)のも良い方法です。焦らず、じっくりと自分に合った治療法を見つけていきましょう。
Q7. 副作用やリスクについて、もっと詳しく知っておきたいです。
A7. どんな医療行為にも100%安全ということはありません。事前にしっかり理解し、納得することが大切です。
効果が期待できる一方で、副作用やリスクの可能性も気になるところですよね。美容医療は医療行為である以上、残念ながら副作用やリスクが全くゼロということはありません。事前にしっかりと理解し、納得した上で治療を受けることが非常に重要です。
一般的な副作用・リスク 治療法によって特有のものはありますが、多くの治療に共通して起こりうるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 施術中・施術直後に出やすいもの:
- 痛み、熱感、ピリピリ感
- 赤み、腫れ
- 内出血(注射や糸治療などで起こりやすい)
- 数日~数週間で治まることが多いもの:
- 上記の症状の持続
- かゆみ、乾燥
- 軽いしびれ感、違和感
- 色素沈着(レーザー治療後などに一時的にシミが濃くなることがある「炎症後色素沈着」など)
- まれではあるが、注意すべきリスク:
- 感染
- アレルギー反応(使用する薬剤などに対して)
- やけど(レーザーやHIFUなどの熱エネルギーを用いる治療の場合)
- 神経損傷(手術や、深い層に作用する治療の場合)
- 効果が期待通りでない、または効果がない
- 左右差が生じる
- ひきつれ感、凸凹感(糸リフトや注入治療で起こりうる)
- 血管塞栓(ヒアルロン酸注入で非常に稀に起こりうる重篤な合併症で、皮膚壊死や失明のリスクがあります)
治療法ごとの特有のリスク 各治療法の説明(後述の「【治療法別】もっと知りたい!ピンポイントQ&A」)でも触れますが、例えばヒアルロン酸注入では血管塞栓のリスク、糸リフトでは糸の露出や感染、美容整形では傷跡の問題や麻酔に伴うリスクなど、それぞれの治療法に特有の注意点があります。
大切なのは「インフォームドコンセント」 医師は、治療前にこれらの副作用やリスクについて、患者さんに分かりやすく説明する義務があります。これを「インフォームドコンセント(説明と同意)」と言います。あなたは、その説明を十分に理解し、納得した上で治療を受けるかどうかを決定する権利があります。
「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、カウンセリングの際には、期待できる効果だけでなく、起こりうる好ましくない結果についても、遠慮なく質問しましょう。例えば、「一番起こりやすい副作用は何ですか?」「もし〇〇という副作用が出た場合、どのような対処をしてもらえますか?」など、具体的に聞いてみると良いでしょう。リスクを理解することは、安心して治療に臨むための第一歩です。
Q8. 複数の治療を組み合わせると、もっと効果が高まるって本当?その場合の注意点は?
A8. はい、組み合わせることで相乗効果が期待できる場合があります。ただし、やみくもに増やすのはNG。医師の的確な診断と計画が不可欠です。
「たるみも気になるけど、シミも何とかしたい…」「HIFUで引き締めて、さらにヒアルロン酸で溝を埋めたらもっと良くなるかな?」など、複数のお悩みを抱えている場合や、より高い効果を求める場合、いくつかの治療法を組み合わせる「コンビネーション治療」が有効なことがあります。
組み合わせのメリット それぞれの治療法には得意な分野があります。例えば、
- HIFUやRFは肌の土台を引き締めるのが得意。
- ヒアルロン酸は失われたボリュームを補ったり、溝を埋めたりするのが得意。
- ボトックスは表情ジワを和らげるのが得意。
- レーザーや光治療はシミやくすみ、肌質改善が得意。
これらを上手く組み合わせることで、一つの治療だけでは得られないような、より総合的で高い効果が期待できます。それはまるで、オーケストラで様々な楽器がそれぞれのパートを演奏し、一つの美しいハーモニーを奏でるのに似ています。
組み合わせの例
- HIFU/RF + ヒアルロン酸・ボトックス:土台を引き締め(HIFU/RF)、ボリュームロスや深いシワを補い(ヒアルロン酸)、表情ジワを抑える(ボトックス)。たるみ、シワ、ボリューム減少に多角的にアプローチ。
- 糸リフト + ヒアルロン酸:糸でたるみを物理的に引き上げ(糸リフト)、細かい調整やボリュームアップをヒアルロン酸で行う。より自然で立体的な仕上がりに。
- レーザー/光治療 + 注入治療(ヒアルロン酸など):肌表面の色調や質感を整え(レーザー/光)、内側からハリやボリュームを与える(注入)。肌の見た目と構造の両面からアプローチ。
組み合わせる際の注意点
- 医師の診断力と経験が重要:どの治療を、どの順番で、どのタイミングで、どの程度の強さで行うかなど、肌の状態や治療の特性を熟知した医師による的確な診断と治療計画が不可欠です。
- 肌への負担:複数の治療を同時に行う場合、肌への負担が大きくなる可能性も考慮しなくてはなりません。ダウンタイムが長引いたり、予期せぬ反応が出たりすることもあり得ます。
- 費用の増加:当然ながら、治療の数が増えれば費用もそれに応じて増加します。
- 過剰な治療(オーバーフィルなど)のリスク:特に注入治療などを組み合わせる場合、やりすぎて不自然な仕上がりにならないよう、医師の美的センスと慎重な判断が求められます。
やみくもに治療を足し算すれば良いというわけではありません。大切なのは、あなたの肌にとって本当に必要な治療を見極め、最小限の負担で最大限の効果を引き出すことです。信頼できる医師とよく相談し、メリットとデメリットを理解した上で、最適なコンビネーション治療を検討しましょう。
Q9. 治療を受けた後って、どんなことに気を付ければいいの?アフターケアは?
A9. 治療によって異なりますが、基本は「保湿」「紫外線対策」「刺激を避ける」。クリニックからの指示をしっかり守りましょう。
治療が無事に終わっても、それで終わりではありません。治療効果を最大限に引き出し、トラブルを防ぐためには、術後のセルフケア(アフターケア)が非常に重要です。これは、手術が無事に終わった後のリハビリ期間のようなもので、回復を早め、より良い結果に繋げるために欠かせません。
基本的なアフターケアのポイント
- 保湿を徹底する:治療後の肌は乾燥しやすく、バリア機能が一時的に低下していることがあります。低刺激性の化粧水や保湿剤で、いつも以上に丁寧に保湿を心がけましょう。
- 紫外線対策を万全に:治療後の肌は紫外線に対して非常に敏感になっています。日焼け止めをこまめに塗り直し、帽子や日傘、サングラスなども活用して、徹底的に紫外線をブロックしましょう。これを怠ると、色素沈着のリスクが高まったり、治療効果が薄れたりすることがあります。
- 刺激を避ける:
- 洗顔やスキンケアの際は、ゴシゴシこすらず、優しく触れるようにしましょう。
- ピーリング効果のある化粧品やスクラブ洗顔などは、医師の許可が出るまでは控えましょう。
- 長時間の入浴やサウナ、激しい運動、飲酒などは、血行が良くなりすぎて腫れや赤みが強くなることがあるため、治療当日から数日間は避けるよう指示されることが多いです。
- クリニックからの指示を守る:処方された軟膏や内服薬があれば、指示通りに使用しましょう。また、施術後の過ごし方について具体的な指示(例:〇日間はメイクを控える、〇週間はマッサージをしないなど)があれば、それを必ず守ってください。
治療法ごとの注意点(例)
- レーザー治療後:かさぶたができた場合は無理に剥がさず、自然に取れるのを待ちましょう。保護テープを貼るよう指示された場合は、その期間しっかり貼っておきます。
- 注入治療後:施術当日は、注入部位を強く押したり、マッサージしたりしないようにしましょう。
- 糸リフト後:大きな口を開けたり、顔を強くこすったりする動作は、しばらくの間(数週間程度)避けるよう指示されることがあります。
もし、施術後に強い痛みや腫れ、赤み、その他気になる症状が現れた場合は、自己判断せずに速やかに治療を受けたクリニックに連絡し、指示を仰ぎましょう。適切なアフターケアを行うことで、ダウンタイムを短縮し、治療効果をより確実なものにすることができます。
Q10. アレルギー体質だったり、肌がすごく敏感だったりするんだけど、それでも受けられる治療ってあるの?
A10. はい、体質や肌質に合わせた治療法の選択や、事前のテストが可能な場合があります。まずは医師に詳しく伝えましょう。
アレルギー体質の方や敏感肌の方は、美容医療を受けるにあたって特に不安を感じますよね。「化粧品でもかぶれやすいのに、もっと強い刺激の治療なんて大丈夫かしら…」と心配になるのは当然です。
まず医師に伝えるべきこと カウンセリングの際には、必ず以下のような情報を医師に詳しく伝えましょう。
- 過去に化粧品や薬剤、食べ物などでアレルギー反応が出た経験(どんなもので、どんな症状が出たか)
- 現在治療中のアレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、気管支喘息、花粉症など)
- 普段から肌が敏感で、どのような時に刺激を感じやすいか(特定の成分、季節の変わり目など)
- 現在使用している薬やサプリメント
これらの情報は、医師があなたに合った治療法を選択したり、治療のリスクを判断したりする上で非常に重要です。
体質・肌質に合わせた治療の選択 医師は、あなたの情報を元に、比較的刺激の少ない治療法を提案したり、アレルギー反応のリスクが低い薬剤を選択したりすることを検討します。
- 比較的肌に優しいとされる治療法(例):
- 光治療(IPL)の中でも、敏感肌向けのモードや設定がある機種。
- RF(高周波)治療の一部で、肌表面への刺激が少ないもの。
- ヒアルロン酸注入でも、アレルギー反応を起こしにくいとされる製剤の選択。
- 事前のテスト:
- 例えば、ヒアルロン酸注入の場合、ごく少量を腕の内側などに注入してアレルギー反応が出ないかを確認する「皮内テスト」を行うことがあります(ただし、全てのヒアルロン酸製剤で必須ではありませんし、テストで陰性でも絶対にアレルギーが出ないとは限りません)。
- レーザーや光治療の場合も、目立たない部分でテスト照射を行い、肌の反応を見ることもあります。
注意点
- どんなに配慮しても、100%アレルギー反応や肌トラブルが起きないとは限りません。
- アトピー性皮膚炎などの症状が強く出ている時期は、治療を見送る方が良い場合もあります。
- 治療後は、特に慎重なアフターケア(保湿、紫外線対策、刺激を避ける)が必要です。
大切なのは、ご自身の体質や肌質について医師に正確に伝え、リスクとベネフィットを十分に理解した上で治療に臨むことです。不安な点は遠慮なく質問し、納得できるまで話し合いましょう。まるで、食物アレルギーのある人がレストランでシェフに詳しく食材を確認するように、あなたも医師に必要な情報をしっかり伝え、安全な治療法を選んでいきましょう。
【治療法別】もっと知りたい!ピンポイントQ&A
ここからは、各治療法について、特によくいただくご質問や、皆さんが「ここがもっと知りたい!」と感じるであろうポイントに絞って、さらに詳しくお答えしていきます。
【HIFU(ハイフ)/ RF(高周波)リフトアップ編】
Q. HIFUって本当に効果があるの?「効果がない」っていう人もいるけど…。
A. 効果の現れ方には個人差があり、たるみの原因や程度、期待値によって満足度が左右されることがあります。
HIFUは、SMAS筋膜という肌の土台を引き締めることでリフトアップ効果が期待できる治療法です [1]。多くの方が効果を実感されていますが、残念ながら「全く効果を感じなかった」という声も時折耳にします。なぜでしょうか?
- たるみの原因とHIFUの得意分野のミスマッチ:
- HIFUは主にSMAS筋膜のゆるみや、皮下脂肪が比較的多いタイプのたるみに効果を発揮しやすいです。
- しかし、たるみの原因が皮膚そのものの深刻なゆるみ(皮膚が伸びてしまっている状態)や、逆に皮下脂肪が極端に少ないことによるコケ感、骨格の萎縮によるものだった場合、HIFUだけでは期待したほどの効果が得られにくいことがあります。これは、お部屋の片付けで、散らかった服を畳む(SMAS引き締め)のは得意でも、壁紙が剥がれているのを直す(皮膚の質の改善)のは専門外、というのに似ています。
- 効果の現れ方と実感のタイミング:
- HIFUの効果は、施術直後から引き締まりを感じる方もいますが、多くの場合、熱によってダメージを受けた組織が修復され、コラーゲンが再構築される1~3ヶ月後に徐々に現れてきます。このタイムラグを知らずに「すぐに効果が出ない=効いていない」と感じてしまう方もいます。
- 期待値の高さ:
- HIFUはメスを使わない「切らないリフトアップ」ですが、外科的なフェイスリフト手術と同等の劇的な変化を期待してしまうと、物足りなさを感じるかもしれません。
- 施術の質:
- 使用する機器の種類、照射の深さやエネルギー設定、ショット数、そして施術者の技術によっても効果は左右されます。適切な層に適切なエネルギーを照射できていない場合、効果は出にくくなります。
もし効果を実感しにくい場合は、たるみの原因を再評価し、HIFUが本当に適応だったのか、他の治療法(例えば糸リフトやヒアルロン酸注入など)との組み合わせが必要なのかを医師と相談してみることが大切です。
Q. RF(高周波)とHIFUって、何が違うの?どっちを選べばいい?
A. 作用する深さと得意な効果が異なります。お悩みに合わせて使い分けたり、組み合わせたりします。
どちらも熱エネルギーを使って肌を引き締める治療ですが、作用するメカニズムとターゲットとなる深さが異なります。
- HIFU(ハイフ):
- 作用の深さ:超音波エネルギーをSMAS筋膜や皮下脂肪層など、皮膚の比較的深い層にピンポイントで集束させます。
- 主な効果:SMAS筋膜からのリフトアップ、フェイスラインの引き締め、二重あごの改善など、「土台からの持ち上げ」が得意です。
- 例えるなら:建物の基礎や柱を補強して、構造的な安定性を高める工事。
- RF(高周波):
- 作用の深さ:高周波電流によって、真皮層から皮下組織浅層にかけて、比較的広範囲に熱を発生させます。
- 主な効果:皮膚全体の引き締め、小ジワの改善、肌のハリ・ツヤ感アップ、毛穴の引き締めなど、「皮膚表面に近い層のタイトニングや質感改善」が得意です。
- 例えるなら:建物の壁や内装をリフレッシュして、見た目の美しさや肌触りを良くする工事。
どちらが良いかは、あなたのお悩みによって異なります。
- フェイスラインのたるみが気になる、SMAS筋膜からしっかり引き上げたい → HIFUが適していることが多いです。
- 皮膚表面のゆるみや小ジワ、肌のハリ不足が気になる → RFが適していることが多いです。
実際には、たるみの状態は複合的なので、HIFUとRFを組み合わせることで、より深層から浅層までトータルな引き締め効果を目指す治療法も人気があります。医師に肌の状態をしっかり診てもらい、どちらの治療法がより効果的か、あるいは組み合わせた方が良いのかを相談しましょう。
Q. HIFUを受け続けると、将来逆にたるみやすくなったり、顔がコケたりするって聞いたけど本当?
A. 適切な頻度と強さで行えば、将来たるみやすくなるという医学的根拠は乏しいです。ただし、過度な施術や適応の見誤りはコケ感に繋がる可能性も。
「HIFUをやりすぎると、かえって肌に良くないのでは?」という不安の声も聞かれますね。
まず、「HIFUを受け続けると将来たるみやすくなる」という点についてですが、医学的には、適切な間隔(例えば半年に一度~1年に一度程度)で、適切なエネルギー設定で行う限り、HIFUが将来のたるみを助長するという明確なエビデンスは現時点では乏しいと考えられます。むしろ、定期的なHIFU治療はコラーゲンの再構築を促し、たるみの進行を緩やかにする「予防効果」が期待されています。
一方で、「顔がコケる」という点については、注意が必要です。HIFUは皮下脂肪層にも作用し、脂肪細胞を減少させる効果も持つ機種や設定があります。元々顔の脂肪が少ない方や、頬がコケやすい骨格の方が、不必要に脂肪をターゲットとするような強い出力や深さでHIFUを受けると、頬が痩せてコケた印象になってしまう可能性は否定できません。これは、ダイエットで、落としたくない部分の脂肪まで落ちてしまうのに似ています。
大切なのは、
- 医師による正確なアセスメント:あなたの顔の脂肪のつき方、たるみの原因、骨格などをしっかり見極めてもらうこと。
- 適切な施術計画:照射する深さ、エネルギー、ショット数などを、あなたの状態に合わせてカスタマイズしてもらうこと。
- 過度な頻度や強さでの施術を避けること。
HIFUは正しく行えば素晴らしい効果が期待できる治療ですが、「もっと効果を!」と焦って短期間に何度も受けたり、強すぎる設定を求めたりするのは避けるべきです。信頼できる医師とよく相談し、長期的な視点で肌の健康を考えた治療計画を立てることが重要です。
【レーザー治療 / 光治療(IPLなど)編】
Q. シミ取りレーザーを受けたら、逆にシミが濃くなっちゃった!なんてことがあるって本当?
A. はい、それは「炎症後色素沈着(PIH)」と呼ばれる一時的な反応の可能性があります。適切なケアと時間で改善することが多いです。
「シミを取るはずが、余計に濃くなった!」なんて聞くと、とても不安になりますよね。これは、レーザー治療後に比較的よく見られる「炎症後色素沈着(えんしょうごしきそちんちゃく、PIH: Post-Inflammatory Hyperpigmentation)」という現象である可能性が高いです。
炎症後色素沈着とは? レーザー照射によって、シミの原因であるメラニン色素は破壊されますが、同時に皮膚には軽いやけどのような炎症が起こります。この炎症の刺激によって、メラノサイト(メラニンを作る細胞)が活性化し、一時的にメラニンを過剰に生成してしまうことがあるのです。その結果、レーザーを照射した部位が、治療前よりもかえって茶色っぽく濃く見えてしまうことがあります。これは、虫刺されやニキビの跡が、治った後にしばらく茶色く色が残るのと同じようなメカニズムです。
いつ頃起こりやすい?どれくらい続く? 炎症後色素沈着は、レーザー照射後、約2週間~1ヶ月くらい経った頃から目立ち始めることが多いです。そして、その濃さや期間には個人差がありますが、通常は3ヶ月~半年、長い方でも1年くらいかけて徐々に薄くなっていきます。
炎症後色素沈着を悪化させないためには?
- 紫外線対策の徹底:炎症後色素沈着の最大の悪化要因は紫外線です。レーザー治療後は、日焼け止めをしっかり塗り、帽子や日傘などで徹底的に紫外線を避けることが非常に重要です。
- 刺激を避ける:照射部位をこすったり、強いマッサージをしたりするのは避けましょう。
- 保湿をしっかり行う:肌のバリア機能を高め、ターンオーバーを正常に保つことも大切です。
- 医師の指示に従う:クリニックによっては、炎症後色素沈着を予防・改善するために、美白効果のある外用薬(ハイドロキノンやトレチノインなど)や内服薬(ビタミンC、トラネキサム酸など)が処方されることがあります。医師の指示に従って正しく使用しましょう。
多くの場合、炎症後色素沈着は一時的なもので、時間とともに改善していきます。しかし、ごくまれに長引いたり、完全に消えなかったりするケースも報告されています[2]。不安な場合は自己判断せず、必ず治療を受けた医師に相談してください。適切なアフターケアと経過観察が、キレイな肌を取り戻すための鍵となります。
Q. 光治療(IPL)って、エステでも受けられるけど、クリニックと何が違うの?何度も受けないと効果がないって本当?
A. クリニックの光治療は医療機器であり、出力や効果が異なります。また、1回でも効果を感じる方もいますが、複数回でより満足度が高まることが多いです。
光治療(IPL)は、シミ、そばかす、くすみ、赤ら顔、小ジワなど、様々なお肌の悩みにマイルドにアプローチできる人気の治療法ですよね。エステサロンでも似たような「光フェイシャル」といったメニューを見かけることがありますが、医療機関(クリニック)で行う光治療とは、いくつかの大きな違いがあります。
- 使用する機器の違い:
- クリニック:医療用に開発された「医療機器」を使用します。医師または医師の指示のもと看護師が施術を行い、肌の状態や悩みに合わせて出力を細かく調整できます。一般的にエステ用の機器よりも高い出力が出せるため、より効果が期待できると言われています。
- エステサロン:美容目的の「美容機器」を使用します。医療機器ほどの高い出力は出せず、効果もマイルドになる傾向があります。
- 施術者の違い:
- クリニック:医師が肌の状態を診断し、治療方針を決定します。施術は医師または看護師が行います。万が一、肌トラブルが起きた場合でも、すぐに医学的な対処が可能です。
- エステサロン:エステティシャンが施術を行います。医学的な診断や処置はできません。
- 期待できる効果と安全性: 一般的に、クリニックの光治療の方が、より明確な効果と高い安全性が期待できると言えます。これは、強力なエンジンを積んだレーシングカー(医療機器)を、訓練されたプロのドライバー(医師・看護師)が運転するのと、一般的な乗用車(美容機器)を一般のドライバー(エステティシャン)が運転するのを比べるようなものかもしれません。
「何度も受けないと効果がない?」という点について 光治療(IPL)は、レーザー治療のように1回で劇的な変化をもたらすというよりは、複数回の治療を重ねることで徐々に肌質を改善していく治療法です。多くの場合、1回の治療でも「肌のトーンが明るくなった」「化粧ノリが良くなった」といった効果を実感される方もいらっしゃいますが、シミや赤ら顔などの具体的な悩みを改善するためには、通常3~5回以上の治療を、3~4週間に1回程度のペースで継続することが推奨されています。
これは、庭の芝生の手入れに似ています。一度雑草を抜いても、また生えてくることがありますし、美しい芝生を維持するためには定期的な手入れが必要ですよね。光治療も、肌のターンオーバーに合わせて繰り返し行うことで、徐々にメラニンを排出し、コラーゲンの生成を促し、肌全体のコンディションを底上げしていくイメージです。 1回の治療でどこまでの効果を期待するか、最終的にどんな状態を目指すかによって、必要な回数は変わってきます。医師とよく相談し、自分に合った治療計画を立てましょう。
Q. 肝斑(かんぱん)があるんだけど、レーザー治療は悪化させるって聞いたけど、本当?
A. はい、一部のレーザーは肝斑を悪化させる可能性があります。しかし、肝斑に適したレーザー治療や他の治療法もあります。自己判断は禁物です。
肝斑は、主に30代~40代の女性に見られる左右対称性のシミで、頬骨のあたりや額、口周りなどに現れることが多いです。原因は完全には解明されていませんが、女性ホルモンのバランスの乱れや、紫外線、摩擦などの刺激が関与していると考えられています。
そして、ご質問の通り、肝斑は非常にデリケートで、不適切な刺激(強いレーザー照射や摩擦など)によって悪化しやすいという特徴があります。一般的なシミ(老人性色素斑など)に使われるQスイッチレーザーなどを不用意に照射すると、かえって色が濃くなったり、範囲が広がったりすることがあるのです。これは、眠っているライオンを不用意に刺激して怒らせてしまうようなものです。
では、肝斑にはどんな治療法があるの? 肝斑治療の基本は、まず「刺激を与えないこと」と「メラニンの生成を抑えること」です。
- 内服薬:トラネキサム酸やビタミンCなどが処方されることが多いです。これらはメラニンの生成を抑えたり、炎症を鎮めたりする効果が期待できます。
- 外用薬:ハイドロキノンやトレチノインといった美白効果のある塗り薬が用いられることがあります。
- レーザートーニング:肝斑治療のために開発された、非常に弱い出力のレーザーを顔全体に均一に照射する方法です。メラノサイトを刺激しないように、少しずつメラニンを分解・排出させていく治療法で、多くのクリニックで行われています。
- 光治療(IPL):機種や設定によっては肝斑に有効な場合もありますが、慎重な判断が必要です。
- スキンケアの見直し:摩擦を避ける(ゴシゴシ洗顔しない)、紫外線対策を徹底する、保湿をしっかり行う、といった基本的なスキンケアも非常に重要です。
大切なのは、まず「それが本当に肝斑なのか」を医師に正確に診断してもらうことです。シミには様々な種類があり、自己判断でケアをすると悪化させてしまうこともあります。特に肝斑が疑われる場合は、経験豊富な皮膚科専門医や美容皮膚科医に相談し、適切な治療法を選択するようにしましょう。
【ヒアルロン酸 / ボトックス注射編】

Q. ヒアルロン酸を打ち続けると、だんだん顔がパンパンになったり、不自然になったりしない?
A. 適量を適切な部位に注入すれば、自然な仕上がりが期待できます。しかし、過度な注入や不適切な手技は不自然さの原因になり得ます。
「ヒアルロン酸でシワが消えるのは嬉しいけど、だんだん顔が不自然に膨らんでしまうのでは…」という不安は、よく聞かれますね。いわゆる「ヒアル顔」「パンパン顔」といった状態を心配されるのだと思います。
なぜ「パンパン顔」に見えてしまうことがあるのか?
- 過剰な注入(オーバーフィル): 「もっとシワをなくしたい」「もっとボリュームを出したい」という思いから、必要以上の量のヒアルロン酸を注入してしまうと、顔全体が膨らんだような不自然な印象になることがあります。これは、風船に空気を入れすぎて、パンパンに張り裂けそうになっている状態に似ています。
- 不適切な部位への注入: ヒアルロン酸は、ただ溝を埋めれば良いというものではありません。顔全体のバランスや、加齢による骨格の変化、脂肪の移動などを考慮せずに、やみくもに注入すると、不自然な膨らみや凸凹感が生じることがあります。
- 製剤の選択ミス: ヒアルロン酸には様々な硬さや粘稠度の種類があります。注入する部位や目的に合わない製剤を選ぶと、仕上がりが不自然になることがあります。例えば、皮膚の浅い層に硬いヒアルロン酸を注入すると、しこりのように感じたり、凸凹したりすることがあります。
- 注入技術の問題: 医師の技術や経験も、仕上がりの自然さを大きく左右します。
自然な仕上がりを保つためには?
- 「足るを知る」精神:一度に多くの量を注入するのではなく、少しずつ状態を見ながら調整していく方が、自然な仕上がりになりやすいです。医師からも「今回はこれくらいにして、また数ヶ月後に状態を見ましょう」といった提案があるかもしれません。
- 信頼できる医師を選ぶ:解剖学的な知識が豊富で、顔全体のバランスを考えた「オーダーメイド」の注入をしてくれる医師を選びましょう。美的センスも重要です。多くの医師は、患者様の顔立ちを活かした自然な美しさを目指しています[4]。
- 定期的な診察と相談:ヒアルロン酸の効果は永久ではないため、定期的に医師の診察を受け、その時々の状態に合わせて適切なメンテナンス計画を立てることが大切です。
ヒアルロン酸は、正しく用いれば非常に効果的で満足度の高い治療法です。大切なのは、「量より質」、そして「全体の調和」です。不自然になることへの不安は、カウンセリングで医師にしっかり伝え、どのような仕上がりを目指すのかを共有しましょう。
Q. ボトックス注射で、表情がなくなったり、目が開けにくくなったりするって本当? ちょっと怖い…。
A. 注入量や部位、手技が適切であれば、自然な表情を保ちつつシワを改善できます。経験豊富な医師を選ぶことが重要です。
「ボトックスを打ったら、笑顔がひきつるんじゃないか…」「眉が動かなくなって、能面みたいになったらどうしよう…」そんな不安から、ボトックス治療をためらう方もいらっしゃるかもしれませんね。
なぜ表情が不自然になることがあるのか? ボトックスは、筋肉の動きを一時的に弱めることで表情ジワを改善する薬です[3]。
- 注入量が多すぎる:必要以上に多くの量を注入すると、ターゲットとした筋肉の動きが弱くなりすぎたり、時には完全に麻痺してしまったりして、表情が硬く不自然に見えることがあります。
- 注入部位が不適切:狙った筋肉以外の周囲の筋肉にまで薬液が広がってしまうと、意図しない部分の動きが弱まり、例えば目が開けにくくなったり(眼瞼下垂)、眉が不自然に吊り上がったり(スポック眉)することがあります。
- 医師の技術や経験不足:表情筋は非常に複雑で、一人ひとりつき方や動きの癖が異なります。これらの個人差を考慮せず、画一的な方法で注入すると、不自然な結果を招きやすくなります。
自然な表情を保つためのポイント
- 「効かせすぎない」ことの重要性:経験豊富な医師は、シワを完全に消し去ることを目指すのではなく、表情の自然さを保ちながら、シワを「目立たなくする」「和らげる」ことを目標に、注入量や部位を微調整します。これは、料理の塩加減に似ています。入れすぎるとしょっぱくて食べられませんが、適量なら素材の味を引き立てて美味しくなりますよね。
- 筋肉の動きをよく観察してもらう:カウンセリングや施術前に、医師にあなたの表情の癖(笑った時の目尻のシワの寄り方、眉を寄せた時の眉間のシワの深さなど)をしっかり見てもらい、どの筋肉にどの程度効かせるのがベストかを判断してもらうことが大切です。
- 少量から始める:特に初めてボトックスを受ける場合や、効果に不安がある場合は、医師と相談して通常よりも少なめの量から試してみるのも一つの方法です。効果が足りなければ後から追加することも可能です。
ボトックスは、医師の技術と経験によって結果が大きく左右される治療法の一つです。症例経験が豊富で、顔の解剖を熟知し、あなたの希望を丁寧に聞き取ってくれる医師を選びましょう。正しく行えば、ボトックスはあなたの表情をより若々しく、魅力的に見せてくれるはずです。
Q. ヒアルロン酸やボトックスの効果が切れたら、治療前よりシワが深くなったり、老けたりするってこと、あるんですか?
A. いいえ、基本的に効果が切れたからといって、治療前よりも悪化するということはありません。むしろ、定期的な治療は老化の進行を遅らせる効果も期待できます。
「効果が切れたら、リバウンドみたいにもっとひどくなるんじゃないか…」という心配は、時々耳にしますが、これは誤解であることが多いです。
ヒアルロン酸の場合 ヒアルロン酸は、注入された後、徐々に体内に吸収されていきます。効果が薄れてくると、シワや溝が治療前の状態に近づいていきますが、治療前よりも悪化するということは通常ありません。 むしろ、ヒアルロン酸が注入されている間、皮膚はその分だけ伸びにくくなっているため、シワが深くなるのをある程度防いでいるとも考えられます。また、ヒアルロン酸自体が周囲の組織のコラーゲン産生をわずかに刺激するという報告もあります。
ボトックスの場合 ボトックスの効果が切れると、抑えられていた筋肉の動きが元に戻り、再び表情ジワが寄りやすくなります。しかし、これも治療前よりもシワが深くなるということはありません。 むしろ、ボトックスが効いている間は、シワの原因となる表情筋の動きが抑えられているため、その期間は新たなシワが刻まれにくくなっています。つまり、定期的にボトックス治療を続けることは、将来のシワの進行を遅らせる「予防的効果」があると言えます。これは、シワという名の「折り目」が、一時的にでもつかないように保護しているようなものです。
なぜ「悪化した」と感じることがあるのか? 治療によって若々しい状態に慣れてしまうと、効果が切れて元の状態に戻った時に、そのギャップから「前より老けた」と感じてしまう心理的な側面はあるかもしれません。しかし、客観的に見て治療前より悪化しているわけではないことが多いです。
大切なのは、効果の持続期間を理解し、定期的なメンテナンスを計画することです。医師と相談しながら、ご自身の状態や希望に合わせて、適切なタイミングで次の治療を検討すると良いでしょう。
【糸リフト(スレッドリフト)編】
Q. 糸リフトで使う糸って、体にずっと残るの? 安全性は大丈夫?
A. 糸の種類によります。最近は体内でゆっくりと吸収される「溶ける糸」が主流で、安全性も高いものが使われています。
「顔の中に糸を入れるなんて、ちょっと怖い…」「その糸はずっと体の中に残るの?」というご不安は、糸リフトを検討される方にとって大きな関心事ですよね。
糸の種類:「溶ける糸」と「溶けない糸」 糸リフトで使われる糸には、大きく分けて2つのタイプがあります。
- 吸収性(溶ける)糸: 現在、多くのクリニックで主流となっているのがこのタイプです。PDO(ポリジオキサノン)、PCL(ポリカプロラクトン)、PLLA(ポリ乳酸)といった、もともと外科手術の縫合糸などにも長年使われてきた安全性の高い医療用素材でできています。これらの糸は、体内に挿入された後、数ヶ月から1~2年かけてゆっくりと水と二酸化炭素に分解され、最終的には吸収されてなくなります。糸が吸収される過程で、周囲の組織ではコラーゲンの生成が促進されるため、糸が溶けた後もある程度の引き締め効果やハリ感の持続が期待できます [5]。
- 例えるなら:土に還る生分解性プラスチックのようなイメージです。役目を終えた後は自然に分解されますが、その間に土壌を豊かにする(コラーゲン生成を促す)置き土産を残してくれるような感じです。
- 非吸収性(溶けない)糸: 過去には、ポリプロピレンなどの体内に残り続ける素材の糸も使われていましたが、長期的な異物反応のリスクや、将来的に他の治療を受ける際の妨げになる可能性などから、最近では顔の美容目的で積極的に使われることは少なくなってきています。ただし、特定の目的や部位によっては、医師の判断で用いられることもあります。
安全性について 吸収性の糸は、長年の医療現場での使用実績があり、アレルギー反応なども起こしにくいとされています。もちろん、どんな医療材料にも100%安全ということはありませんが、現在美容医療で一般的に使用されている吸収性の糸は、厳しい基準をクリアした安全性の高いものが選ばれています。
ただし、まれに以下のようなことが起こる可能性はあります。
- 感染:挿入時の清潔操作が不十分だった場合など。
- アレルギー反応・異物反応:非常にまれですが、糸の素材に対して体が過敏に反応することがあります。
- 糸の露出・突出:皮膚の浅い層に挿入された場合や、表情の動きなどによって、糸の先端が皮膚から出てきたり、透けて見えたりすることがあります。
これらのリスクを最小限に抑えるためには、清潔な環境で、経験豊富な医師に、適切な種類の糸を、適切な深さに挿入してもらうことが重要です. カウンセリングの際には、使用する糸の種類や素材、安全性についてもしっかりと説明を受け、納得した上で治療に臨むようにしましょう。
Q. 糸リフトの後、顔がひきつったり、凸凹(でこぼこ)したりするって聞くけど、本当?
A. 施術直後には一時的にひきつれ感や軽い凸凹が出ることがありますが、通常は時間とともに馴染んで改善します。長引く場合は医師に相談を。
「糸で引っ張るんだから、顔がひきつったり、不自然な凸凹ができたりしないかな…」これも糸リフトでよくある心配事の一つですね。
なぜ、ひきつれ感や凸凹が起こることがあるの?
- 施術直後の正常な反応として: 糸リフトは、コグ(トゲ)のついた糸で皮下組織を物理的に引き上げる治療です。そのため、施術直後は組織が新しい位置に馴染むまで、多少のひきつれ感(特に口を開けたり、大きく笑ったりした時)や、糸の挿入部分やコグが引っかかっている部分が一時的に少し盛り上がったり、逆に少しへこんだりして見えることがあります。これは、新しい家具を部屋に入れた時に、最初は少し配置に違和感があるけれど、だんだん見慣れて馴染んでくるのに似ています。
- 腫れや内出血の影響: 施術に伴う腫れや内出血によって、一時的に皮膚表面が不均一に見えることもあります。
- 糸の挿入技術や種類の問題(まれに):
- 糸を挿入する深さが浅すぎたり、引き上げる力が強すぎたり、均一でなかったりすると、ひきつれ感や凸凹が長引いたり、目立ったりする可能性があります。
- 使用する糸の種類やコグの形状が、その方の皮膚の厚みやたるみの状態に合っていない場合も、不自然な仕上がりになることがあります。
通常はどれくらいで改善するの? 施術直後に見られる軽いひきつれ感や凸凹は、多くの場合、数日~2週間程度で徐々に組織が馴染み、腫れが引くことで自然に改善していきます。マッサージなどはせず、安静に過ごすことが大切です。
長引く場合や気になる場合は? もし、2週間以上経っても強いひきつれ感や明らかな凸凹が改善しない場合、または痛みや赤みが増してくるような場合は、自己判断せずに速やかに治療を受けたクリニックに連絡し、医師の診察を受けましょう。 場合によっては、挿入した糸の調整や、マッサージの指示、場合によっては糸の除去などが必要になることもあります(非常にまれですが)。
多くの経験豊富な医師は、できるだけひきつれや凸凹が起こらないように、そして起こったとしても一時的で済むように、糸の種類、挿入する深さ、引き上げる方向や力加減などを慎重にデザインして施術を行っています。ダウンタイム中の経過について不安な点は、事前に医師にしっかり確認しておきましょう。
Q. 糸リフトを受けると、将来、他の美容治療(例えばHIFUとかレーザーとか)が受けにくくなることってあるの?
A. 多くの場合は問題ありませんが、糸の種類や挿入されている深さ、受ける治療の種類によっては注意が必要なことも。必ず事前に医師に申告しましょう。
「一度糸を入れたら、その部分にはもう他の治療はできないのかな…」と心配される方もいらっしゃいますね。
基本的には他の治療も可能 現在主流となっている「溶ける糸」を使用した場合、糸が吸収されていく過程や、吸収された後であれば、HIFUやレーザー、光治療、注入治療など、他の多くの美容治療を受けることは基本的に可能です。糸がコラーゲン生成を促し、肌の土台が強化されることで、むしろ他の治療との相乗効果が期待できる場合もあります。
注意が必要なケース
- 糸リフト直後~糸が安定するまで: 糸リフトを受けてから数週間~1ヶ月程度は、挿入した糸が組織にしっかりと定着し、炎症が落ち着くまでの期間です。この時期に、糸リフトと同じ部位に強い刺激を与えるような他の治療(特に熱を加えるHIFUや一部のレーザーなど)を行うことは、糸の定着を妨げたり、炎症を増強させたりする可能性があるため、避けるのが一般的です。
- 非吸収性(溶けない)糸が挿入されている場合: もし過去に溶けない糸によるリフトアップ治療を受けている場合は、その糸が残っていることで、HIFUやRFなどの熱を加える治療で予期せぬ反応(糸の変性や周囲組織への影響など)が起こる可能性や、手術の際に妨げになる可能性が考えられます。
- 受ける治療の種類と糸の深さ: 例えば、非常に浅い層に作用するレーザー治療であれば、深い層に挿入された糸には影響しにくいと考えられますが、HIFUのようにSMAS筋膜に近い深い層に熱を加える治療の場合、糸が挿入されている深さによっては注意が必要です。
最も大切なこと:必ず医師に申告する 過去に糸リフト(に限らず、ヒアルロン酸注入や他の美容医療、美容整形など)を受けたことがある場合は、これから新しい治療を受ける前に、必ず担当の医師にその旨を正確に伝えましょう。いつ、どこに、どんな種類の糸(分かれば)を入れたのか、どんな薬剤を注入したのか、といった情報は、医師が安全かつ効果的に次の治療を行うために非常に重要です。
それは、新しい薬を処方してもらう前に、現在服用中の薬やお薬手帳を医師に見せるのと同じです。情報の共有が、安全で最適な治療への第一歩となります。
【美容整形(フェイスリフトなど)編】
Q. フェイスリフトの傷跡って、やっぱり目立つの?どれくらいで分からなくなる?
A. 傷跡が全くゼロになるわけではありませんが、経験豊富な医師はできるだけ目立たない位置に、丁寧に縫合します。時間とともにかなり分かりにくくなります。
フェイスリフトは、たるみを根本的に改善できる非常に効果的な手術ですが、「切る」という行為が伴うため、傷跡に関する心配は当然ですよね。
傷跡はどこにできるの? フェイスリフトの切開線は、一般的に耳の前(耳珠と呼ばれる軟骨のラインに沿って)、耳たぶの後ろを回り、髪の生え際へと続くようにデザインされることが多いです。たるみの程度や手術の方法(ミニリフト、フルフェイスリフトなど)によって、切開の長さや範囲は異なります。 経験豊富な医師は、これらの切開線を、できるだけシワのラインや髪の毛で隠れるような、目立ちにくい場所に設定するように工夫します。
傷跡の経過
- 手術直後~数週間:切開線は赤みを帯び、少し盛り上がっていることもあります。縫合した糸がまだ付いている状態です。
- 1ヶ月~3ヶ月頃:赤みは徐々に薄茶色っぽく変化し、傷は少し硬く感じられることがあります。この時期が一番傷跡が目立つと感じる方もいます。
- 3ヶ月~6ヶ月以降:傷の赤みはさらに薄れ、硬さも和らいで柔らかくなっていきます。徐々に白い線状の跡へと変化し、かなり目立ちにくくなっていきます。
- 1年~数年:最終的には、ほとんど分からないくらいに馴染むことが多いです。ただし、完全に消えてなくなるわけではなく、よく見れば細い線として残ることはあります。
傷跡をできるだけキレイに治すために
- 医師の技術:形成外科的な知識と縫合技術に長けた医師を選ぶことが最も重要です。皮膚の緊張を最小限に抑え、丁寧に縫合することで、傷跡はよりキレイに治りやすくなります。
- 術後のケア:
- 紫外線対策:傷跡に紫外線が当たると色素沈着を起こし、目立ちやすくなるため、徹底した紫外線対策が必要です。
- 保湿:傷跡が乾燥しないように保湿することも大切です。
- 禁煙:喫煙は血行を悪化させ、傷の治りを遅らせるため、術前術後は禁煙が強く推奨されます。
- クリニックからの指示を守る:処方された軟膏やテープなどがあれば、指示通りに使用しましょう。
傷跡の治り方には個人差(体質、年齢、肌の色など)もあります。カウンセリングの際には、傷跡がどこにできて、どのような経過をたどるのか、そしてご自身の体質で目立ちやすい可能性はあるのかなど、しっかりと説明を受け、症例写真なども見せてもらうと良いでしょう。
Q. 手術後の腫れや内出血は、どれくらい続くものなの?完全に元に戻るまでどれくらい?
A. 大きな腫れや内出血は2週間~1ヶ月程度でかなり引きますが、細かいむくみや硬さが完全に落ち着くには3ヶ月~半年以上かかることもあります。
フェイスリフトなどの外科手術は、効果が高い分、ダウンタイムも他の治療法に比べて長くなる傾向があります。
一般的な腫れ・内出血の経過
- 手術直後~3日目頃:腫れと内出血が最も強く出る時期です。顔全体がパンパンに腫れたり、目元や首の方まで内出血が広がったりすることがあります。痛みもこの時期がピークですが、鎮痛剤でコントロールします。冷却も行います。
- 1週間~2週間頃:大きな腫れは徐々に引き始め、内出血も黄色っぽく変化しながら薄くなっていきます。この頃に抜糸が行われることが多いです。まだ腫れぼったさは残りますが、メイクでカバーすれば外出できる方もいます。
- 1ヶ月頃:腫れや内出血はかなり目立たなくなり、多くの場合は日常生活に支障がない程度に回復します。しかし、まだ顔に触れると少し硬さを感じたり、細かいむくみが残っていたりします。
- 3ヶ月~6ヶ月以降:残っていたむくみや硬さもほとんどなくなり、皮膚の感覚も徐々に正常に戻ってきます。傷跡も成熟し、仕上がりがほぼ完成する時期と言えます。
完全に「元に戻る」というよりは「新しい状態に落ち着く」 「完全に元に戻る」という表現よりは、「手術による変化が落ち着き、完成形になる」と捉える方が適切かもしれません。手術によって組織の位置が変わり、新しいバランスが生まれるわけですから。
ダウンタイムを少しでも快適に過ごすために
- 安静にする:術後数日間は、できるだけ頭を高くして安静に過ごしましょう。
- 冷却する:医師の指示に従って、適切に冷却することで腫れを抑えることができます。
- 圧迫:クリニックによっては、フェイスバンドなどで適度に圧迫するよう指示されることがあります。
- 食事:塩分の多い食事はむくみを助長するので控えめに。栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
- 禁煙・禁酒:血行に影響し、治りを遅らせる可能性があるため、医師の指示に従いましょう。
ダウンタイムの長さや程度には個人差があります。また、手術の範囲や方法によっても異なります。焦らず、医師の指示に従って適切なケアを行い、心身ともに無理なく過ごすことが大切です。まるで、大きな怪我をした後のリハビリのように、時間をかけてゆっくりと回復していくイメージを持つと良いでしょう。
Q. 「切る治療」って、一度やったらもう元には戻せないのが不安…。修正はできるの?
A. はい、外科手術は基本的に元に戻すことを前提としていません。だからこそ慎重な判断が必要です。ただし、万が一の場合の修正手術の可能性はゼロではありませんが、初回手術より難易度が上がることが多いです。
フェイスリフトなどの外科手術は、他の多くの保存的な治療法(ヒアルロン酸やボトックスなど)とは異なり、組織を切除したり、位置を大きく変えたりするため、基本的に「元に戻す」という考え方はありません。一度切除した皮膚やSMAS筋膜を元通りに復元することは不可能です。だからこそ、手術を受ける前には、本当に自分に必要なのか、どんな結果を望むのかを、時間をかけてじっくりと考え、医師と徹底的に話し合うことが何よりも重要になります。
もし結果に満足できなかった場合、修正は可能なのか? 万が一、手術の結果が期待通りでなかったり、何らかの問題が生じたりした場合、修正手術を検討することはあり得ます。しかし、いくつかの注意点があります。
- 修正手術の難易度: 一般的に、初回の手術よりも修正手術の方が難易度は高くなります。なぜなら、初回の手術によって組織には瘢痕(はんこん:きずあと)ができており、正常な解剖学的構造が変化しているため、手術操作がより複雑になるからです。また、血行も悪くなっている可能性があり、治りも遅くなる傾向があります。
- 修正できる範囲の限界: 修正手術でどこまで改善できるかは、初回の状態や問題点によって大きく異なります。完全に理想通りの状態に戻せるとは限りません。
- 修正手術のタイミング: 通常、修正手術を行う場合でも、初回の術後の炎症や腫れが完全に落ち着き、組織が安定するまで(最低でも半年~1年程度)待つ必要があります。
- 医師選びの重要性: 修正手術はより高度な技術と経験が求められるため、修正手術を得意とする、あるいは経験豊富な医師を選ぶことが非常に重要です。
「元に戻せない」からこそ、事前の準備が全て 「元に戻せないかもしれない」という不安は、外科手術を考える上で最も大きなハードルの一つでしょう。だからこそ、
- 焦って結論を出さないこと。
- 複数の医師の意見を聞くこと(セカンドオピニオン)。
- 医師との間で、仕上がりのイメージを徹底的に共有すること(シミュレーションなどがあれば活用する)。
- メリットだけでなく、デメリットやリスク、起こりうる好ましくない結果についても、全て納得いくまで説明を受けること。
- 「この医師なら任せられる」と心から信頼できる医師を見つけること。
これらが、後悔しないための最も大切なステップです。それはまるで、人生の大きな決断をする時に、様々な情報を集め、多くの人の意見を聞き、そして最後は自分自身で覚悟を決めるのに似ています。
最後に:あなたの「知りたい!」が「なりたい自分」への架け橋となるように
若返り治療に関する様々な疑問にお答えしてきましたが、いかがでしたでしょうか? 「ああ、そういうことだったのか!」「ちょっと不安が軽くなったかも」そんな風に感じていただけたなら、とても嬉しく思います。
美容医療の世界は、情報も選択肢も本当にたくさんあって、まるで広大な海を航海するようなものかもしれません。どの船に乗り、どのルートを進むのか。それは、あなた自身が船長となって決めることです。そして、この記事が、その航海のための少しでも役立つ海図や羅針盤のような存在になれたとしたら、これ以上の喜びはありません。
大切なのは、巷の情報に振り回されたり、誰かの意見を鵜呑みにしたりするのではなく、あなた自身が「なぜ?」「どうして?」という知的好奇心を持ち続け、正しい情報を集め、そして「自分はどうしたいのか」という心の声に耳を澄ませることです。
知識は、あなたを不安から守り、賢明な選択をするための力強い武器になります。そして、その選択の先には、きっとあなたが思い描く「なりたい自分」との出会いが待っているはずです。
美容医療は、決して魔法ではありません。しかし、あなたがより前向きに、より自信を持って、笑顔で毎日を過ごすための一つの素晴らしい「きっかけ」や「応援団」にはなってくれるはずです。
この記事を通じて得た知識が、あなたの「知りたい!」という気持ちを満たし、そしてそれが「なりたい自分」へと続く輝く架け橋となることを、心から願っています。あなたのこれからの毎日が、より一層彩り豊かで、喜びに満ちたものになりますように。
自然な若返りにはヒアルロン酸注入、それも総合的に注入する「TFT治療」が重要です。「TFT治療」について詳しく知りたい方はこちらからどうぞ。
参考文献
[1] Shome, D., Vadera, S., Kapoor, R., & Kadershah, N. (2019). Principles and Rationale of Non-Surgical Skin Tightening. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 12(1), 1–7.
[2] Kaufman, J., Green, J. B., & Weiner, S. F. (2022). Laser Treatment of Scars and Striae. In Lasers and Energy Devices for the Skin (pp. 197-210). Springer, Cham.
[3] Carruthers, J., & Carruthers, A. (2003). Botulinum toxin A in the treatment of glabellar frown lines and other facial wrinkles. Clinics in Dermatology, 21(6), 481-488.
[4] De Maio, M., & Rzany, B. (2007). Injectable Fillers in Aesthetic Medicine. Springer Science & Business Media.
[5] Rezaee Khiaban, A., Alihemmati, A., Ahmad, A. N., Yousefi, M., & Rahbarghazi, R. (2021). Thread-lift as a promising anti-aging modality: A systematic review on procedural and cellular an_d molecular aspects. Journal of Cosmetic Dermatology, 20(11), 3436–3448.

