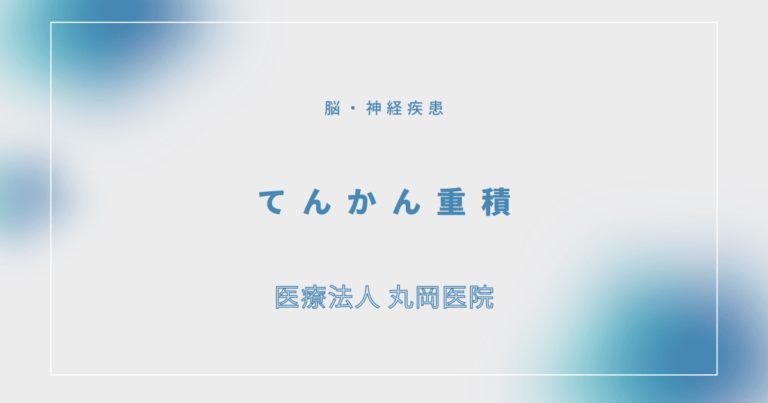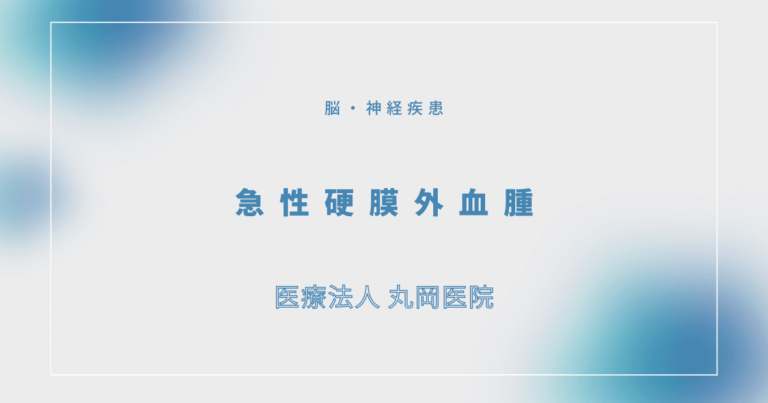スリット脳室症候群(slit ventricle syndrome)とは、脳脊髄液のシャント手術後に起こりうる合併症の一つで、脳室が狭小化して頭蓋内圧が上昇し、さまざまな神経症状を起こす疾患です。
この症候群は、脳脊髄液の過度な排出によって脳室が細くなることで、頭痛や嘔吐、めまいなどの症状が現れます。
シャント手術を受けた患者さんの中でも、小児期に手術を受けた方に多く見られ、成長に伴って症状が顕在化することがあるため、長期的な経過観察が重要です。
発症初期は軽度の頭痛から始まることが多く、進行すると視覚障害や意識レベルの変化など、より深刻な神経症状を伴います。
スリット脳室症候群の主な症状
スリット脳室症候群の主たる症状は、頭痛や嘔吐、めまいや平衡機能障害、さらには視覚障害など、多岐にわたる神経学的症候が見られます。
頭蓋内圧亢進に伴う症状
頭蓋内圧亢進に起因する症状群は、朝方に悪化する拍動性の頭痛が多くの患者さんに共通して認められます。
頭痛は、体位変換や身体活動によって増強することが多く、安静時であっても持続的に存在します。
嘔気や嘔吐といった消化器症状も頭蓋内圧亢進に伴って現れ、早朝空腹時に症状が顕著です。
| 症状 | 特徴的な出現パターン |
| 頭痛 | 朝方増悪、体動で増強 |
| 嘔気・嘔吐 | 早朝空腹時に顕著 |
| めまい | 起立時や体位変換時 |
| 視覚異常 | 一過性の視野障害 |
神経学的症候の多様性
神経学的症候としては、平衡感覚の障害やめまい感生じ、症状は起立時や急激に体位を変換する時に多くみられます。
視覚に関する症状は、一過性の視野障害や複視、光過敏などです。
聴覚系の症状として、耳鳴りや難聴といった症状が起こることもあり、症状は頭蓋内圧の変動に伴って変化します。
症状の日内変動と増悪因子
症状の強さは、一日の中でも変動することが多く、早朝から午前中にかけて症状が強くなります。
また、体位の変換や咳、くしゃみなどの動作によって頭蓋内圧が一時的に上昇することで、症状が増悪します。
| 時間帯 | 症状の特徴 |
| 早朝 | 頭痛・嘔吐が強い |
| 日中 | 活動に伴い変動 |
| 夕方 | 比較的安定傾向 |
| 夜間 | 臥床により軽減 |
神経学的所見の評価
神経学的診察において確認される他覚的所見として、以下の項目が重要です。
- 瞳孔反応の変化や眼球運動障害が認められることがあり、両側性の外転神経麻痺が観察される
- 頭蓋内圧亢進に伴う乳頭浮腫が眼底検査で確認され、視神経乳頭の境界不鮮明化や血管怒張などの所見が特徴的
- 小脳症状として、体幹失調や歩行障害が現れ、閉眼時の立位保持が困難になる
- 前庭機能検査では、自発性眼振や頭位性眼振が観察される
本症候群における神経学的所見は、症状の進行度や重症度を反映することから、定期的な神経学的評価が必要となります。
スリット脳室症候群の原因
スリット脳室症候群は、主にシャント手術後の脳室が過度に狭くなることと、頭蓋内圧変動によって起こります。
病態の基本的メカニズム
脳脊髄液の過剰な排出によって脳室系全体が著しく狭くなることで、脳組織への圧迫や血流障害が生じ、変化が複雑に絡み合って神経機能に影響を及ぼします。
長期的な脳脊髄液の変化は、脳実質や血管系にも影響を与え、頭蓋内圧の変動や脳血流の調節にも重大な変化をもたらす可能性があります。
発症リスク要因の分類
| リスク要因 | 影響度合い |
| 幼少期のシャント手術歴 | 非常に高い |
| 急激な脳脊髄液排出 | 高い |
| 頭蓋内圧変動の履歴 | 中程度 |
| 解剖学的要因 | 中程度 |
リスク要因は複合的に作用することで発症リスクを高め、特に幼少期のシャント手術歴を持つ患者さんでは、成長に伴う頭蓋内の環境変化が加わることで、より複雑な病態を形成します。
解剖学的な要因分析
脳室系の構造変化と脳組織の適応機能について、以下の要因が病態の進行に関与しています。
- 脳室壁の弾性低下による圧力調節機能の低下
- 脳実質の可塑性変化による代償機能の限界
- 髄液循環動態の慢性的な変調
- クモ膜下腔の構造的変化
- 脳血管系の自動調節機能への影響
二次的な影響と関連要因
| 影響を受ける機能 | 関連する解剖学的構造 |
| 髄液産生能 | 脈絡叢 |
| 髄液吸収能 | クモ膜顆粒 |
| 血流調節機能 | 脳血管系 |
| 代謝機能 | グリア細胞 |
二次的な影響は、長期的な経過の中で徐々に顕在化し、脳を維持する機能全体に影響を及ぼします。
脳血管系の自動調節機能への影響は、脳組織の酸素供給や代謝物質の除去にも関与するため、神経機能の維持において大切な要素です。
また、グリア細胞(中枢神経系を構成する神経細胞以外の細胞)の変化は、神経細胞の支持機能や代謝調節にも影響を与え、より広範な神経学的な変化をもたらす要因となります。
さらに、クモ膜顆粒(脳脊髄液を静脈血に吸収する場所)における変化は、頭蓋内圧の日内変動や姿勢の変化に対する適応能力を低下させます。
診察(検査)と診断
スリット脳室症候群の診断では、神経学的診察を基本としながら、脳脊髄液圧測定や神経画像検査などの検査手法を組み合わせて行います。
基本的な神経学的診察手順
神経学的診察では、まず意識状態や認知機能の評価から開始し、脳神経機能、運動機能、感覚機能などの神経系の状態を確認します。
特に眼底検査では、視神経乳頭の状態を詳細に観察することで、頭蓋内圧亢進の有無や程度を判断することが大切です。
| 診察項目 | 診察内容と留意点 |
| 眼底検査 | 視神経乳頭浮腫の有無、網膜静脈怒張の程度 |
| 瞳孔反応 | 対光反射、輻輳反射の確認 |
| 眼球運動 | 複視の有無、眼振の観察 |
| 平衡機能 | 起立・歩行時の偏倚、動揺の程度 |
画像診断による脳室評価
頭部MRIやCTスキャンによる画像検査で、脳室の形態や大きさを観察することが不可欠です。
MRI検査では、T1強調画像、T2強調画像、FLAIR画像を用いることで、より詳細な脳室の特徴を把握できます。
脳脊髄液検査による圧測定
脳脊髄液検査は以下の手順で実施します。
- 腰椎穿刺による髄液採取を行い、初圧と終圧を測定して髄液圧の変動を確認
- 髄液の性状分析を行い、細胞数、蛋白質濃度、糖濃度などの生化学的検査を実施
- 必要に応じて持続的な髄液圧モニタリングを行い、日内変動や体位変換時の圧変化を記録
- 髄液産生量や吸収能の評価のため、特殊な負荷試験を追加することも
特殊検査による機能評価
頭蓋内圧のモニタリングでは、24時間以上にわたって頭蓋内圧の変動を記録し、日内変動のパターンや体位変換による変化を分析します。
| 検査種類 | 検査の目的と意義 |
| 脳血流検査 | 脳循環動態の評価、血流障害の把握 |
| 脳波検査 | 脳活動の電気生理学的評価 |
| 誘発電位 | 視覚・聴覚伝導路の機能評価 |
| 神経超音波 | 脳室系の形態学的観察 |
核医学検査では、脳脊髄液の循環動態を視覚化することで、髄液の産生から吸収までの過程を観察します。
また、脳血流シンチグラフィーを用いることで、脳実質の血流状態や代謝活性についても評価できます。
さらに、磁気共鳴スペクトロスコピー(MRS)などの先進的な検査手法を用いることで、脳組織の代謝状態をより詳細に把握することも可能です。
スリット脳室症候群の治療法と処方薬、治療期間
スリット脳室症候群の治療は、シャントシステムの調整や再建術、薬物療法など、複数の治療を組み合わせながら行います。
治療方針の決定と基本的アプローチ
シャントシステムの圧設定値の調整から開始し、患者さんの状態に合わせて段階的に治療強度を上げていくことで、脳室の形態と機能の改善を目指します。
入院治療期間は、通常2週間から1ヶ月です。
シャントシステムの調整と手術的治療
| 手術的アプローチ | 治療期間の目安 |
| シャント圧調整術 | 2-4週間 |
| シャント再建術 | 4-8週間 |
| 内視鏡的治療 | 3-6週間 |
| 脳室拡大術 | 6-12週間 |
術後のシャントシステムの調整では、頭蓋内圧の変動を緩やかにコントロールしながら、脳室の形態回復を促します。
薬物療法
脳浮腫の制御や頭蓋内圧の安定化を目的として、以下の薬剤を使用します。
- グリセオール(浸透圧利尿薬)による頭蓋内圧降下療法
- マンニトール(浸透圧利尿薬)を用いた脳浮腫の制御
- フロセミド(ループ利尿薬)による髄液産生の調整
- アセタゾラミド(炭酸脱水酵素阻害薬)による髄液産生抑制
- デキサメタゾン(副腎皮質ステロイド)による抗浮腫効果
治療スケジュールと投薬計画
| 治療段階 | 主な使用薬剤 |
| 急性期 | グリセオール、デキサメタゾン |
| 安定期 | アセタゾラミド、フロセミド |
| 維持期 | 必要に応じた間欠的投与 |
| 寛解期 | 漸減・中止の検討 |
薬物療法は、患者さんの状態や治療経過に応じて投与量や組み合わせを調整しながら、必要な期間継続することが大切です。
急性期の薬物療法では、頭蓋内圧の急激な変動を避け、安定期に入ってからは、脳脊髄液の循環動態の正常化を目指します。
維持期における薬物療法では、症状の安定性を確認しながら、投与間隔や投与量の見直しを行い、寛解期に向かう過程では、薬物の減量を検討します。
スリット脳室症候群の治療における副作用やリスク
スリット脳室症候群の治療においては、シャント手術や内視鏡的処置などの外科的介入に関連して、感染症や機器関連合併症、また髄液動態の変化に伴う神経学的合併症などの副作用やリスクがあります。
シャント関連の合併症
シャントシステムに関連する合併症として、カテーテルの閉塞や位置異常、また接続部の離断などが代表的な機械的トラブルとして挙げられます。
黄色ブドウ球菌などの細菌による感染が発生した際には、髄膜炎や脳室炎などの重篤な感染性合併症に進展する可能性があるので注意が必要です。
| 合併症の種類 | 内容と特徴 |
| 機械的トラブル | カテーテル閉塞、位置異常、接続部離断 |
| 感染性合併症 | 髄膜炎、脳室炎、シャント感染 |
| 出血性合併症 | 硬膜下血腫、脳室内出血 |
| 過剰排液 | 硬膜下水腫、脳室虚脱 |
髄液動態の変化に伴う合併症
髄液の過剰な排液は硬膜下水腫や脳室虚脱を引き起こす要因となり、頭蓋内圧の急激な低下によって脳実質の偏位や血管の引っ張られることで、神経症状の悪化を招きます。
反対に、髄液排液が不十分な状況では、頭蓋内圧が上昇することにより視神経乳頭浮腫や視力障害などの神経学的合併症が現することがあり、早期発見と対応が不可欠です。
注意が必要な合併症
- 視神経症状として、視力低下や視野欠損が進行性に現れることがあり、永続的な視機能障害につながる危険性
- 脳幹圧迫症状として、意識レベルの変動や呼吸異常が生じた際には、生命予後に関わる
- 小脳症状として、平衡機能障害や協調運動障害が出現することがあり、転倒リスクの増加につながる
- 脳神経症状として、顔面神経麻痺や聴力障害などが見られることがある
感染性合併症のリスク管理
術後早期の感染予防は極めて重要で、無菌操作の徹底や予防的抗生剤の使用など、複数の感染対策を組み合わせて実施します。
| 感染対策 | 実施内容 |
| 手術時対策 | 厳密な無菌操作、予防的抗生剤投与 |
| 術後管理 | 創部の清潔保持、定期的な消毒 |
| モニタリング | 感染徴候の観察、血液検査 |
| 早期対応 | 感染兆候時の迅速な治療開始 |
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
手術関連費用の内訳
| 治療内容 | 3割負担の概算費用 | 備考 |
| シャント手術 | 30-45万円 | 基本的な手術費用 |
| 内視鏡手術 | 40-60万円 | 機器使用料を含む |
| 術前検査一式 | 5-8万円 | MRI・CT等を含む |
| 入院費(14日) | 15-20万円 | 食事代別途 |
画像診断・検査費用
MRI検査1回あたりの自己負担額は2万円から3万円で、CT検査は1回あたり1万円から1万5000円程度です。
脳血流シンチグラフィー検査は、放射性同位元素の使用料を含めて4万円から5万円になります。
術後フォローアップ費用
術後の定期検査に必要な費用として、以下の項目が挙げられます。
- 外来診察料と処方箋料 1回あたり3000円から5000円程度
- 定期的な画像検査(MRIまたはCT) 2万円から3万円程度
- 脳脊髄液検査 1万5000円から2万円程度
- 神経生理学的検査 1万円から1万5000円程度
医療材料費用
シャントシステムの種類によって価格が異なります。
| 医療材料 | 費用(3割負担) | 特徴 |
| 標準シャント | 15-20万円 | 一般的に使用 |
| 可変圧シャント | 20-25万円 | 圧調整可能 |
| 抗菌カテーテル | 18-22万円 | 感染予防タイプ |
| 特殊バルブ付き | 22-28万円 | 高機能タイプ |
リハビリテーション関連費用
理学療法や作業療法などのリハビリテーション費用は、1回あたり3000円から5000円程度の自己負担です。
以上
Rekate HL. Shunt-related headaches: the slit ventricle syndromes. Child’s Nervous System. 2008 Apr;24:423-30.
Epstein F, Lapras C, Wisoff JH. ‘Slit-ventricle syndrome’: etiology and treatment. Pediatric Neurosurgery. 1988 Mar 5;14(1):5-10.
Panagopoulos D, Karydakis P, Themistocleous M. Slit ventricle syndrome: historical considerations, diagnosis, pathophysiology, and treatment review. Brain Circulation. 2021 Jul 1;7(3):167-77.
Serlo W, Saukkonen AL, Heikkinen E, Von Wendt L. The incidence and management of the slit ventricle syndrome. Acta neurochirurgica. 1989 Sep;99:113-6.
Di Rocco C. Is the slit ventricle syndrome always a slit ventricle syndrome?. Child’s Nervous System. 1994 Jan;10:49-58.
Rekate HL. The slit ventricle syndrome: advances based on technology and understanding. Pediatric neurosurgery. 2004 Dec 1;40(6):259-63.
Walker ML, Fried A, Petronio J. Diagnosis and treatment of the slit ventricle syndrome. Neurosurgery clinics of North America. 1993 Oct 1;4(4):707-14.
Baskin JJ, Manwaring KH, Rekate HL. Ventricular shunt removal: the ultimate treatment of the slit ventricle syndrome. Journal of neurosurgery. 1998 Mar 1;88(3):478-84.
Serlo W, Heikkinen E, Saukkonen AL, v Wendt L. Classification and management of the slit ventricle syndrome. Child’s nervous system. 1985 Oct;1:194-9.
Benzel EC, Reeves JD, Kesterson L, Hadden TA. Slit ventricle syndrome in children: clinical presentation and treatment. Acta neurochirurgica. 1992 Mar;117:7-14.