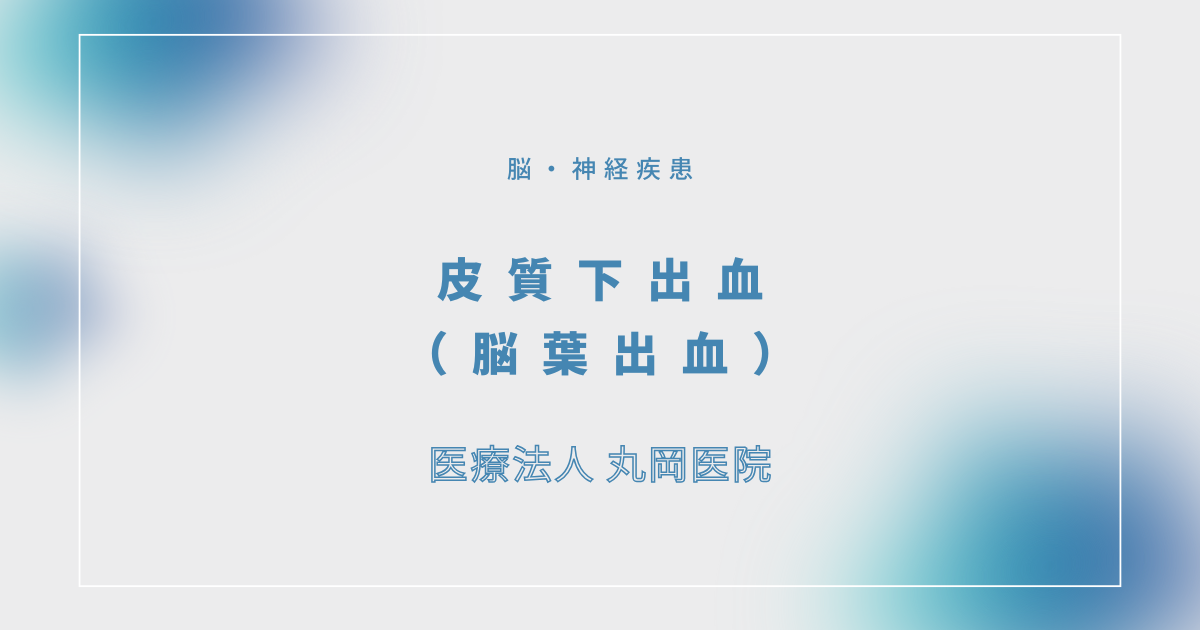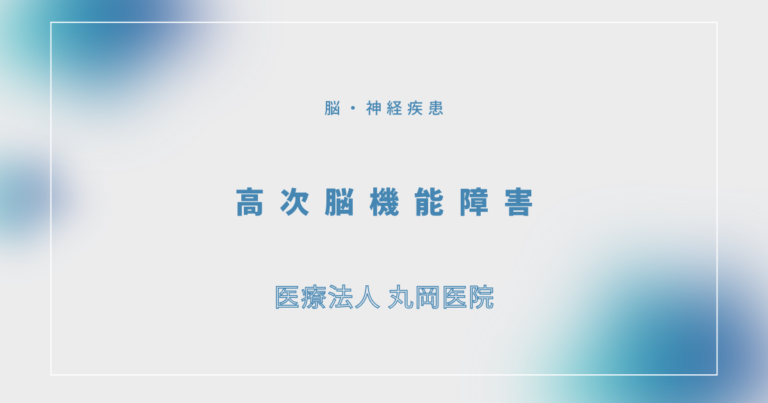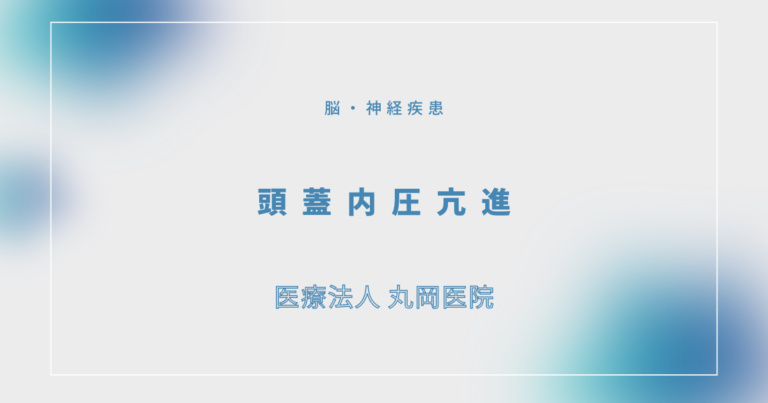皮質下出血(脳葉出血)(subcortical hemorrhage)とは、脳の深い部分にある白質と呼ばれる領域で発生する出血性の脳血管疾患のことです。
この病気は、長年の高血圧による血管へのダメージが原因となることが多く、発症すると突然の激しい頭痛や意識の障害、手足の麻痺といった深刻な症状が現れます。
脳卒中の中でも日本人に比較的多く見られる病型で、特に高血圧の既往がある方や高齢者の方々に発症しやすいです。
皮質下出血(脳葉出血)の主な症状
皮質下出血の症状は、頭痛、嘔吐、意識障害といった頭蓋内圧亢進症状に加えて、麻痺や言語障害などの神経症状が突然に出現し、時間の経過とともに徐々に進行していきます。
初期症状と進行性の変化
皮質下出血では、脳の実質内に出血が起こることで周囲の脳組織が圧迫され、それに伴って様々な神経症状が現れてきます。
出血発症直後から数時間の間に、激しい頭痛や嘔吐などの症状が現れ、出血量が増加するにつれて意識レベルの低下や神経症状が進行していくことが多いです。
| 時間経過 | 主な症状の変化 |
| 発症直後 | 頭痛・嘔吐 |
| 数時間以内 | 意識障害の出現 |
| 24時間以内 | 神経症状の進行 |
| 48時間以内 | 症状の安定化 |
出血部位による特徴的な症状
前頭葉での出血では、性格変化や意欲低下などの高次脳機能障害が目立つ一方で、運動や言語に関する症状は軽度にとどまることが特徴です。
側頭葉の出血では、記憶障害や聴覚に関する症状があり、発作的な意識障害を伴うこともあります。
頭頂葉の出血で起こる症状
- 反対側の手足の感覚障害
- 空間認知の障害
- 左右の区別が困難
- 視野の一部が見えにくい
- 物の位置や距離の把握が苦手
麻痺症状の特徴と進行
麻痺の程度や範囲は出血の大きさと関係しており、特に内包後脚という部位に近い出血では、反対側の手足に重度の麻痺が現れることが少なくありません。
| 麻痺の種類 | 症状の特徴 |
| 完全麻痺 | 全く動かない |
| 不全麻痺 | やや動く |
| 軽度麻痺 | ほぼ動く |
| 筋力低下 | 力が入りにくい |
意識障害の評価と経過
意識障害は出血量や脳浮腫の程度によって変化し、出血が大きい時には、急速に意識レベルが低下していきます。
意識障害の評価には、JCS(Japan Coma Scale)やGCS(Glasgow Coma Scale)という指標を用いており、数値の変化を継続的に観察することで、病状の進行を判断することが重要です。
また、意識レベルの変化は、瞳孔の大きさや対光反射、呼吸状態などの他の神経学的所見とも関連しています。
さらに、脳浮腫の進行に伴って、頭痛や嘔吐などの症状が強くなったり、新たな神経症状が出現したりすることもあり、発症後48時間程度は注意深い観察が大切です。
脳浮腫のピークは発症後3~4日目で、この時期には意識レベルの変動や神経症状の増悪が起こる事例も少なくありません。
皮質下出血(脳葉出血)の原因
皮質下出血の原因は高血圧性脳出血が最も多く、その他にも脳アミロイドアンギオパチー、血管奇形、抗凝固薬の影響、脳腫瘍からの出血など、様々な要因が関与しています。
高血圧による血管病変
長期間にわたる高血圧により、脳の細い動脈には小さな瘤(マイクロアネリズム)や血管壁の変性(フィブリノイド壊死)などの変化が起こり、脆弱化した血管が破綻することで出血に至ります。
特に、深部穿通枝と呼ばれる細い動脈は高血圧の影響を受けやすく、血管壁の老化や硬化が進行することで、突然の破綻をきたすことがあるのです。
| 血管変化の種類 | 病態の特徴 |
| 微小動脈瘤 | 血管壁の一部膨張 |
| 血管壁変性 | 壁の構造破壊 |
| 動脈硬化 | 血管弾力低下 |
| 血管内皮障害 | 血管機能異常 |
アミロイドアンギオパチーによる血管脆弱性
高齢者に多く見られる脳アミロイドアンギオパチーでは、以下のような変化が脳血管に生じることで出血の原因となります。
- アミロイドβタンパクの血管壁への沈着
- 血管壁の層構造の破壊
- 血管周囲の炎症反応
- 微小出血の多発
- 血管壁の二次性変性
その他の血管性病変
脳動静脈奇形や海綿状血管腫などの先天的な血管の異常も、皮質下出血の原因となることがあり、血管奇形は若年者の出血性病変として特に注意が必要です。
| 血管奇形の種類 | 特徴的な所見 |
| 脳動静脈奇形 | 異常血管の集簇 |
| 海綿状血管腫 | 拡張した血管腔 |
| 静脈性血管腫 | 放射状の静脈集合 |
| 毛細血管拡張症 | 微細血管の拡張 |
薬剤性要因と全身疾患
抗凝固薬や抗血小板薬を服用している患者さんでは、薬剤の作用により出血のリスクが高まることがあり、特に高齢者や高血圧を合併している場合には注意深く経過観察をします。
また、血液の凝固異常を伴う全身疾患や、血小板減少症などの血液疾患も、皮質下出血の原因として考慮すべき疾患です。
白血病や再生不良性貧血などの血液疾患では、血小板数の著しい減少により出血傾向が強まり、皮質下出血のリスクが上昇します。
さらに、肝硬変や慢性腎臓病などの内臓疾患も、凝固機能の異常や血管壁の脆弱性を起こすことで、出血の原因となります。
診察(検査)と診断
皮質下出血(脳葉出血)の診断においては、神経学的診察と最先端の画像診断技術を組み合わせ、出血の位置や大きさ、進行状況などを正確に把握します。
初期診察の基本
救急外来での初期診察では、発症時の状況や経過時間、既往歴など、患者さんやご家族から詳細な情報収集を行い、情報を基に初期評価の方向性を決定していきます。
神経学的診察では、意識レベルの定量的評価をはじめとして、瞳孔の大きさや対光反射、手足の運動機能、感覚機能など、脳神経系の機能を総合的に評価することが大切です。
画像検査による診断
画像検査は急性期の診断病態の時に、正確な把握を可能にします。
- 頭部CT検査により、出血の位置や血腫量を即座に評価し、緊急性の判断材料とする
- MRI検査で脳実質の微細な変化を捉え、二次的な損傷の程度を確認
- MRA検査を用いて脳血管の構造異常や狭窄の有無を詳しく調べる
- CT perfusion により脳血流の状態を定量的に評価し、虚血の範囲を特定
血液検査による評価
急性期の診断において、血液検査は出血の原因究明や病態の把握に重要です。
| 血液検査項目 | 確認内容 |
| 凝固系 | PT-INR、APTT |
| 血算 | 血小板数、貧血の有無 |
| 生化学 | 電解質、腎機能 |
| 血糖値 | 高血糖の有無 |
血液検査の結果は現在の状態を把握するだけでなく、今後起こりうる合併症の予測や、必要な予防措置の判断にも活用できます。
追加検査による精査
頸動脈超音波検査では、頸部血管の動脈硬化の程度や血流速度を詳細に評価することで、脳血管障害のリスク因子を定量化し、今後の再発予防に向けた指標になります。
また、心臓超音波検査により、心機能や弁膜症の有無、心腔内血栓の存在などを確認することで、心原性脳塞栓の可能性について検討します。
脳波検査では、意識障害の原因となっている脳機能障害の範囲や程度を評価でき、意識レベルの変動を伴う症例では、経過観察において有用です。
皮質下出血(脳葉出血)の治療法と処方薬、治療期間
皮質下出血の治療は、出血の大きさや部位によって保存的治療と手術療法を選択し、それぞれに応じた薬物療法を組み合わせながら行います。
保存的治療の基本方針
保存的治療では、まず出血の拡大を防ぎながら、脳浮腫の軽減と頭蓋内圧の管理を行うことが重要です。
薬物療法は、第一段階として血圧を厳格にコントロールする降圧薬の投与から始まり、続いて脳浮腫を抑制するための浸透圧利尿薬や、頭蓋内圧を下げるためのステロイド薬を組み合わせて使用します。
| 使用薬剤 | 投与目的 |
| カルシウム拮抗薬 | 血圧低下 |
| グリセオール | 浮腫軽減 |
| マンニトール | 頭蓋内圧低下 |
| デキサメタゾン | 抗浮腫作用 |
手術療法と適応
手術療法には以下のような方法があります。
- 開頭血腫除去術 従来からの標準的な手術方法
- 定位的血腫除去術 より低侵襲な手術方法
- 内視鏡下血腫除去術 出血部位を直接確認しながら行う方法
- 血腫ドレナージ術 穿頭による血腫排出法
- 減圧開頭術 高度な脳浮腫への対応策
開頭血腫除去術は、大きな出血に対して直接アプローチできる利点がある一方で、手術の負担が大きくなり、定位的血腫除去術や内視鏡下血腫除去術は、より小さな傷で手術ができ、患者さんの負担を減らせます。
また、血腫ドレナージ術は、比較的小さな穴から血腫を排出し緊急時の処置として有効で、減圧開頭術は、脳の腫れが強い場合に、頭蓋内圧を下げるために行う手術です。
薬物療法の組み立て方
急性期には、まず全身管理に必要な薬剤を使用しながら、段階的に治療薬を追加します。
| 投与時期 | 主な使用薬剤 |
| 超急性期 | 降圧薬・止血剤 |
| 急性期 | 浸透圧利尿薬 |
| 回復期前期 | 抗浮腫薬 |
| 回復期後期 | 脳代謝改善薬 |
治療期間と回復過程
急性期治療は1〜2週間程度を要し、この間は集中治療室での全身管理が必要です。
一般病棟での回復期治療には2〜3週間を要し、この期間には徐々に薬物療法を調整しながら、早期離床に向けた準備を進めていきます。
早期のリハビリテーション介入も重要で、さらに、退院後も外来での投薬治療は継続し、高血圧のコントロールや再発予防のための薬物療法は長期にわたって継続することが大切です。
摂食・嚥下機能の回復状況に応じて、経管栄養から経口摂取への移行を図り、この過程で必要な栄養剤や補助食品なども使用していきます。
皮質下出血(脳葉出血)の治療における副作用やリスク
皮質下出血(脳葉出血)に対する治療においては、手術療法と内科的治療の両方において、出血部位や周辺の脳組織への影響、また全身状態の変化など、様々な副作用やリスクがあります。
手術に関連する一般的なリスク
開頭手術に伴う基本的なリスクとしては、手術部位の感染や出血、周囲組織の損傷などがあります。
また、術後の脳浮腫対策も重要な課題です。
| 術中合併症 | 発生頻度 |
| 術中出血 | 2-5% |
| 感染症 | 1-3% |
| 脳浮腫 | 3-7% |
| 血腫再発 | 2-4% |
麻酔に関連した合併症として、呼吸器系や循環器系への影響に留意することが重要で、術中の血圧管理については、低すぎても高すぎても問題となることから、慎重な調整が必要です。
血腫除去に伴うリスク
手術における血腫除去の過程で起こりえる合併症
- 周辺の正常脳組織への機械的損傷による神経機能の低下
- 術後の再出血による症状の急激な悪化
- 脳浮腫の増悪に伴う頭蓋内圧上昇
- 脳室穿破による水頭症の発症リスク
合併症は、出血の部位や血腫量、また患者さんの全身状態によって発生リスクが大きく異なります。
薬物療法関連のリスク
内科的治療において用いられる各種薬剤には、それぞれに副作用があります。
| 薬剤の種類 | 副作用 |
| 降圧薬 | 過度の血圧低下、めまい |
| 浸透圧利尿薬 | 電解質異常、腎機能障害 |
| 抗てんかん薬 | 眠気、ふらつき |
| 鎮痛薬 | 消化器症状、腎機能低下 |
急性期においては、複数の薬剤を併用することが多いため、薬剤間の相互作用にも十分な注意を払いながら、定期的な血液検査などによるモニタリングが大切です。
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
基本的な入院治療費
手術を伴わない保存的治療では、2~4週間の入院期間が必要です。
| 治療内容 | 概算費用(3割負担) |
| ICU管理 | 15~20万円/週 |
| 一般病棟 | 8~12万円/週 |
| 薬物療法 | 3~5万円/週 |
| 画像検査 | 5~8万円/回 |
手術関連費用
手術に関連する費用には以下のような項目が含まれます。
- 術前検査一式 12~15万円
- 手術室使用料 15~20万円
- 麻酔料 8~12万円
- 術者技術料 20~25万円
- 手術材料費 10~15万円
薬物療法と検査費用
| 治療項目 | 費用(3割負担) |
| MRI検査 | 3~5万円 |
| CT検査 | 2~3万円 |
| 血液検査 | 5千~1万円 |
| 降圧薬 | 3~5千円/週 |
リハビリテーション関連費用
急性期リハビリテーションは1単位あたり2,000~3,000円程度の費用が発生し、回復期での治療は、1日あたり2~3万円です。
言語聴覚療法や作業療法などの専門的なリハビリテーションも、それぞれ1単位あたり2,000~3,000円程度の追加費用となります。
以上
Hino A, Fujimoto M, Yamaki T, Iwamoto Y, Katsumori T. Value of repeat angiography in patients with spontaneous subcortical hemorrhage. Stroke. 1998 Dec;29(12):2517-21.
Kase CS. Subcortical hemorrhages. Subcortical stroke. 2002 Apr 11;2:347-77.
Peach RK, Tonkovich JD. Phonemic characteristics of apraxia of speech resulting from subcortical hemorrhage. Journal of Communication Disorders. 2004 Jan 1;37(1):77-90.
Kurata A, Miyasaka Y, Kitahara T, Kan S, Takagi H. Subcortical cerebral hemorrhage with reference to vascular malformations and hypertension as causes of hemorrhage. Neurosurgery. 1993 Apr 1;32(4):505-11.
Cuvinciuc V, Viguier A, Calviere L, Raposo N, Larrue V, Cognard C, Bonneville F. Isolated acute nontraumatic cortical subarachnoid hemorrhage. American journal of neuroradiology. 2010 Sep 1;31(8):1355-62.
Keiper MD, Ng SE, Atlas SW, Grossman RI. Subcortical hemorrhage: marker for radiographically occult cerebral vein thrombosis on CT. Journal of computer assisted tomography. 1995 Jul 1;19(4):527-31.
Takeda S, Yamazaki K, Miyakawa T, Onda K, Hinokuma K, Ikuta F, Arai H. Subcortical hematoma caused by cerebral amyloid angiopathy: does the first evidence of hemorrhage occur in the subarachnoid space?. Neuropathology. 2003 Dec;23(4):254-61.
Yamada SM, Tomita Y, Iwamoto N, Takeda R, Nakane M, Aso T, Takahashi M. Subcortical hemorrhage caused by cerebral amyloid angiopathy compared with hypertensive hemorrhage. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2024 Jan 1;236:108076.
Sugiyama H, Tsutsumi S, Watanabe A, Nonaka S, Okura H, Ishii H. Simultaneous presentation of subcortical hemorrhage, subdural hemorrhage, and cerebral infarct in a hemiplegic patient. Radiology Case Reports. 2022 May 1;17(5):1376-9.
Liao YC, Hu YC, Chung CP, Wang YF, Guo YC, Tsai YS, Lee YC. Intracerebral hemorrhage in cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy. Stroke. 2021.