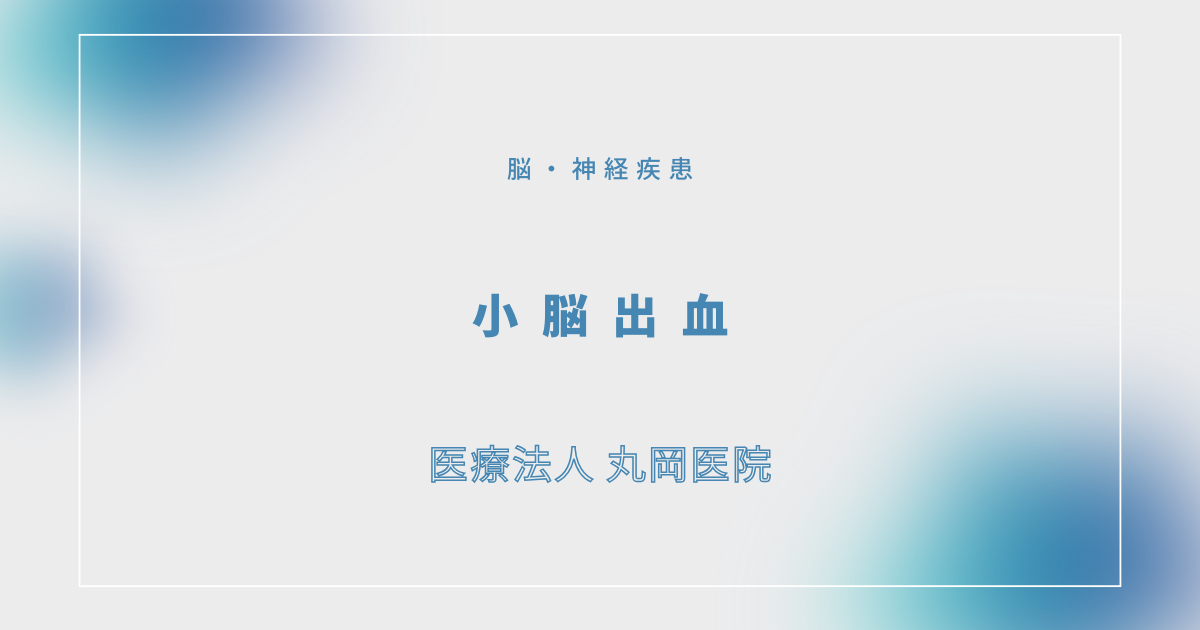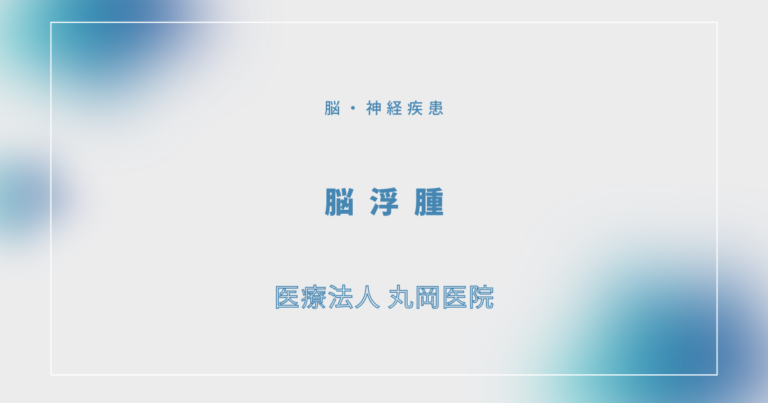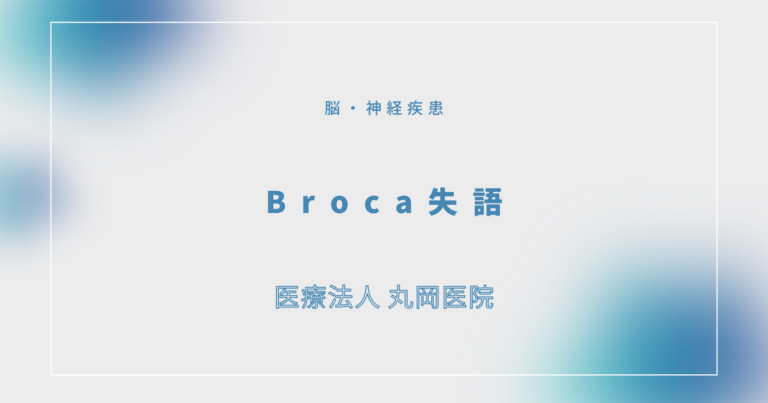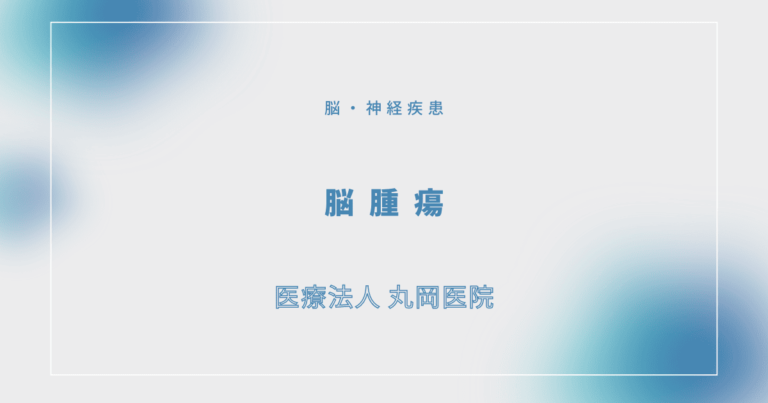小脳出血(cerebellar hemorrhage)とは、脳の後ろ下部にある小脳と呼ばれる部分で発生する出血性の脳卒中です。
小脳は体のバランスや運動の調整を担う重要な部位であり、ここで出血が起こると激しいめまいや嘔吐、歩行時のふらつきなどの特徴的な神経症状が現れます。
この疾患は高血圧や血管の異常が主な原因で、高齢者や高血圧の方は発症リスクが高いので、注意が必要です。
小脳出血の主な症状
小脳出血の症状は、突然の激しい頭痛やめまい、嘔吐などの一般的な脳卒中症状に加えて、小脳特有の機能障害による歩行時のふらつきや運動の協調障害、さらには脳幹への圧迫による意識障害などが生じます。
初期症状と随伴症状
発症時の症状として最も特徴的なものは、後頭部を中心とした激しい頭痛で、頭痛は拍動性で持続的な性質を持つことが多く、同時に激しい回転性のめまいと、制御の難しい嘔吐を伴います。
| 初期症状 | 特徴的な性質 |
| 頭痛 | 後頭部中心の拍動性疼痛 |
| めまい | 回転性のめまい感 |
| 嘔吐 | 持続的な嘔気を伴う |
| 眼振 | 水平性・垂直性の異常眼球運動 |
症状は、小脳という部位の特殊性から、通常の脳卒中とは異なる独特の症状パターンを示し、特に眼球の不随意運動である眼振は、小脳出血を示唆する重要な神経学的所です。
小脳性運動障害
小脳の機能障害に起因する特徴的な症状として、以下のような運動障害が観察されます。
- 四肢の協調運動障害
- 歩行時のふらつき
- 手足の測定異常
- 言語の障害(構音障害)
- 姿勢保持の困難さ
症状は、小脳が本来持っている運動の微調整機能が障害されることで生じ、歩行時の不安定性や手足の動きのぎこちなさとして現れます。
意識障害と脳幹症状
| 症状分類 | 症状 |
| 意識障害 | 傾眠〜昏睡 |
| 呼吸障害 | 不規則な呼吸 |
| 自律神経症状 | 血圧変動、発汗異常 |
脳幹への圧迫が進行すると、意識レベルの低下や呼吸の異常、自律神経症状など、生命維持に関わる重篤な症状が生じることがあり、このような症状の出現は緊急性が高い状態です。
神経学的所見
運動失調は小脳出血に最も特徴的な神経学的所見であり、四肢や体幹の協調運動障害として見られ、特に歩行時の不安定性や手足の動きの不正確さとして観察され、診断において大切な要素となります。
進行性の症状
出血の進行に伴って神経症状が徐々に悪化することが特徴的であり、意識レベルの低下や脳幹症状の出現は、病態の進行を示す重要なサインです。
小脳出血の原因
小脳出血の主たる原因は、長年の高血圧による血管障害であり、それに加えて脳動脈瘤や血管奇形、血液の凝固異常など、複数の要因が互いに影響し合って発症に至ります。
高血圧による血管障害
長期にわたる高血圧の持続により、小脳の細い血管の壁が次第に弱くなっていき、分岐部分において微小な動脈瘤が形成されることで、突発的な出血が起こりやすい状態となります。
| 血圧値 | 出血リスク |
| 正常血圧 | 基準値 |
| 軽度高血圧 | 2倍以上 |
| 重度高血圧 | 4倍以上 |
慢性的な高血圧状態が続くと、血管の内側を覆う内皮細胞に障害が起こり、血管壁全体の変性が徐々に進行していくことが、出血発症の重要な要因です。
血管の構造異常
先天的あるいは後天的な血管の形態異常として、以下のような病変が小脳出血の原因となることが知られています。
- 脳動脈瘤(血管壁の一部が瘤状に膨らむ)
- 脳動静脈奇形(動脈と静脈が異常に吻合)
- 海綿状血管腫(血管が海綿状に集簇)
- もやもや病(脳底部の血管網異常)
血管異常は、画像診断の進歩により早期発見が可能となってきており、定期的な経過観察により出血リスクの評価を行うことが可能です。
血液凝固異常
| 凝固異常の種類 | リスク要因 |
| 抗凝固薬服用 | 出血時間延長 |
| 血小板減少 | 止血機能低下 |
| 肝機能障害 | 凝固因子低下 |
血液の凝固機能に影響を与える様々な要因が小脳出血の発症リスクを高め、特に高齢者における抗凝固薬の使用については、出血リスクと血栓予防のバランスを慎重に判断する必要があります。
加齢による影響
加齢に伴って血管壁の弾力性が失われ、微小血管の変性やアミロイド血管症などが進行していくことで、血管壁の脆弱性が増大し、出血の可能性が高まります。
その他の要因
頭部への強い衝撃による血管損傷や、脳腫瘍による血管への浸潤なども、小脳出血を起こす要因で、背景因子を持つ患者さんについては、特に注意深い観察が欠かせません。
診察(検査)と診断
小脳出血の診断では、神経学的な診察による症状の確認と、CTやMRIといった画像検査による出血の場所や広がりの把握を組み合わせながら行います。
初期診察と神経学的所見
小脳出血を疑う患者さんに対する初期診察では、まず意識状態の確認から始めて、その後に小脳の機能を詳しく調べる神経学的診察へと進みます。
緊急性の判断に関わる重要な所見として、意識状態の変化や呼吸状態の変化などがあります。
| 診察項目 | 確認のポイント |
| 意識レベル | JCS、GCSによる定量評価 |
| 瞳孔所見 | 左右差、対光反射 |
| バイタル | 血圧、脈拍、呼吸状態 |
| 小脳機能 | 協調運動、平衡機能 |
画像診断による出血の評価
頭部CTは小脳出血の診断において最初に選択する画像検査で、出血の有無や範囲をすぐに判断できることが特徴です。
MRI検査では、出血の周りの様子や、出血による脳幹への圧迫の状態などをより詳しく確認でき、診断の精度を高めることにつながります。
画像検査の項目
- 単純CTによる出血の検出
- 造影CTによる出血源の特定
- MRI T2強調画像による微小出血の確認
- MRA(磁気共鳴血管造影)による血管評価
血液検査と凝固機能検査
血液検査では患者さんの体の状態を総合的に把握するとともに、出血を引き起こしやすい状態が隠れていないかを慎重に確認していくことが大切です。
特に、血液の固まりやすさを調べる凝固機能検査は、今後の出血リスクを予測する上で欠かせない情報になります。
| 検査項目 | 診断的意義 |
| 血算 | 貧血、血小板数 |
| 凝固系 | PT、APTT、D-dimer |
| 生化学 | 肝機能、腎機能 |
脳血管造影検査
脳血管造影検査は、出血の原因となる血管の異常があるかどうかを詳しく調べる検査で、動脈瘤や血管奇形といった血管の病変を見つけ出すことができます。
検査では、造影剤を血管の中に流しながらレントゲンを撮影することで、普通の画像検査では分からない細かな血管の異常まで発見することが可能です。
小脳出血の治療法と処方薬、治療期間
小脳出血の治療には、手術による血腫除去や、薬物による頭蓋内圧のコントロール、全身管理など複数のアプローチを組み合わせます。
手術療法
小脳出血の手術治療では、血腫の大きさや位置、患者さんの全身状態などを総合的に判断しながら、最も効果的な手術方法を選択していきます。
出血量が多かったり、脳幹部への圧迫が強い場合には、頭蓋骨を一時的に外して直接血腫を取り除く開頭手術を行います。
出血が比較的小さい場合や、患者さんの全身状態によっては、CT等で確認しながら細い管を用いて血腫を吸引する方法を選択することも。
| 手術方法 | 目的と特徴 |
| 開頭血腫除去術 | 直視下での確実な血腫除去 |
| 定位的血腫吸引術 | 低侵襲での血腫減量 |
| 脳室ドレナージ | 水頭症の軽減 |
急性期の薬物療法
発症直後から約1-2週間の急性期では、脳の圧力を下げる薬や血圧を安定させる薬を中心に、複数の薬剤を組み合わせながら治療を進めます。
特に発症後72時間は再出血の危険性が高い時期となるため、血圧のコントロールを厳密に行いながら、降圧薬の投与量を細かく調整していくことが重要です。
脳圧を下げる薬剤の使用では、血液中の電解質バランスに注意を払いながら、次のような薬剤を状態に応じて使用していきます。
- グリセオール(浸透圧利尿薬による脳圧降下)
- マンニトール(脳浮腫の軽減)
- ニカルジピン(持続静注による降圧)
- フロセミド(利尿による循環動態の改善)
抗浮腫療法
脳の浮腫に対する治療では、ステロイド薬や利尿薬を組み合わせて使用することで、より効果的に脳の腫れを抑えられます。
ステロイド薬の投与方法は急性期には点滴で行い、その後徐々に内服薬へと切り替えていき、この過程で患者さんの状態を見ながら少しずつ量を減らすことが大切です。
利尿薬は腎臓の働きや電解質のバランスを確認しながら投与量を調整していき、カリウムなどの電解質を補充することもあります。
| 薬剤 | 投与方法 |
| デキサメタゾン | 静脈内投与 |
| ベタメタゾン | 経口投与 |
| フロセミド | 静脈内投与 |
回復期の薬物療法
急性期を過ぎて全身状態が安定してきた段階では、再出血を防ぐための降圧薬や、脳の機能回復を促進する薬剤の内服治療へと移行します。
この時期の投薬では、服用する薬の種類や量を整理しながら、日常生活に合わせた内服スケジュールを組み立てていくことが大切です。
薬物療法の期間は患者さんの回復状態によって個別に判断していきますが、3-6ヶ月程度の継続的な服用が必要となります。
小脳出血の治療における副作用やリスク
小脳出血の治療においては、手術による周辺の脳組織への影響や、様々な薬物療法が全身に及ぼす影響、そして合併症が起こるリスクなどがあります。
手術に関連する合併症
手術中や手術後に起こる出血、感染症、脳浮腫といった合併症は、患者さんの回復に大きく影響を与える要因で、特に高齢の方や持病をお持ちの方では、より慎重な対応が大切です。
手術中の出血は、時として予期せぬ血管からも起こることがあり、出血量が増えると脳への圧迫が強くなって深刻な事態を招くこともあります。
| 合併症 | リスク要因 |
| 術中出血 | 血管の脆弱性、血圧変動 |
| 感染症 | 手術創の汚染、免疫力低下 |
| 脳浮腫 | 周辺組織の損傷、炎症反応 |
| 髄液漏 | 硬膜の縫合不全、組織の脆弱性 |
血圧管理に関連するリスク
血圧を下げる治療では、脳への血流が不足しないよう調整が欠かせませんが、急激な血圧低下は脳の血流不足を起こすことがあるため、慎重な管理が重要です。
治療時の注意点
- 急激な血圧低下による脳血流の低下(意識レベルの悪化や麻痺症状の出現)
- 臓器虚血の発生(腎機能障害や心筋障害のリスク)
- 血圧変動による再出血(特に高血圧の既往がある場合)
- 降圧薬の副作用(めまいやふらつき、電解質異常)
薬物療法による副作用
脳のむくみを抑える薬や炎症を抑える薬といった治療薬は、体全体に様々な影響を及ぼす可能性があり、腎臓や肝臓などの臓器機能が低下している患者さんでは注意が必要です。
ステロイド薬の使用では、感染症のリスクが高まることに加えて、血糖値の上昇や消化管出血などの合併症の可能性もあります。
また、利尿薬の使用による電解質バランスの乱れは、心臓の不整脈や意識障害などを起こすことがあるため、血液検査による頻繁なモニタリングと電解質の補正を行います。
| 使用薬剤 | 副作用と注意点 |
| 浸透圧利尿薬 | 電解質異常(特にナトリウム値の変動)、腎機能障害のリスク増加 |
| ステロイド | 免疫力低下による感染症、血糖上昇、消化管出血のリスク |
| 抗痙攣薬 | 眠気やめまい、肝機能への影響、他剤との相互作用 |
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
急性期入院時の基本的な治療費
入院期間は通常、2週間から1ヶ月です。
| 治療内容 | 3割負担の概算費用 |
| 一般病棟入院(1日) | 6,000円~8,000円 |
| ICU入院(1日) | 20,000円~30,000円 |
| 脳神経外科手術 | 30万円~50万円 |
| 脳血管造影 | 3万円~5万円 |
薬物療法にかかる費用
薬物治療に関する主な費用
- グリセオール(1日)2,000円~3,000円
- ニカルジピン(1日)1,500円~2,000円
- エダラボン(1日)3,000円~4,000円
- 抗てんかん薬(1日)500円~1,000円
検査費用
| 検査項目 | 3割負担の費用 |
| MRI検査 | 15,000円~20,000円 |
| CT検査 | 8,000円~12,000円 |
| 血液検査 | 3,000円~5,000円 |
| 脳波検査 | 4,000円~6,000円 |
回復期の入院費用
回復期リハビリテーション病棟での治療は、1日あたり5,000円から8,000円程度の費用が発生します。
以上
Heros RC. Cerebellar hemorrhage and infarction. Stroke. 1982 Jan;13(1):106-9.
Datar S, Rabinstein AA. Cerebellar hemorrhage. Neurologic clinics. 2014 Nov 1;32(4):993-1007.
Ott KH, Kase CS, Ojemann RG, Mohr JP. Cerebellar hemorrhage: diagnosis and treatment: a review of 56 cases. Archives of neurology. 1974 Sep 1;31(3):160-7.
Brockmann MA, Groden C. Remote cerebellar hemorrhage: a review. The cerebellum. 2006 Mar;5:64-8.
Fisher CM, Picard EH, Polak A, Dalal P, Ojemann RG. Acute hypertensive cerebellar hemorrhage: diagnosis and surgical treatment. The Journal of nervous and mental disease. 1965 Jan 1;140(1):38-57.
Little JR, Tubman DE, Ethier R. Cerebellar hemorrhage in adults: diagnosis by computerized tomography. Journal of neurosurgery. 1978 Apr 1;48(4):575-9.
Salvati M, Cervoni L, Raco A, Delfini R. Spontaneous cerebellar hemorrhage: clinical remarks on 50 cases. Surgical neurology. 2001 Mar 1;55(3):156-61.
Kobayashi S, Sato A, Kageyama Y, Nakamura H, Watanabe Y, Yamaura A. Treatment of hypertensive cerebellar hemorrhage–surgical or conservative management?. Neurosurgery. 1994 Feb 1;34(2):246-51.
Friedman JA, Ecker RD, Piepgras DG, Duke DA. Cerebellar hemorrhage after spinal surgery: report of two cases and literature review. Neurosurgery. 2002 Jun 1;50(6):1361-4.
Han J, Lee HK, Cho TG, Moon JG, Kim CH. Management and outcome of spontaneous cerebellar hemorrhage. Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery. 2015 Sep 1;17(3):185-93.