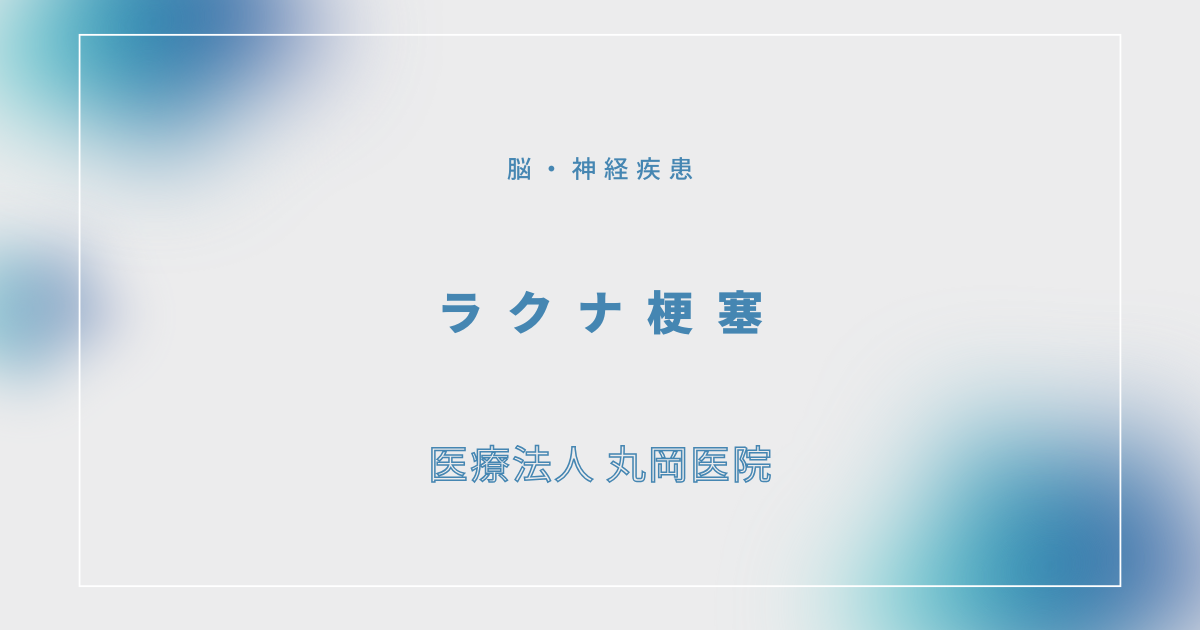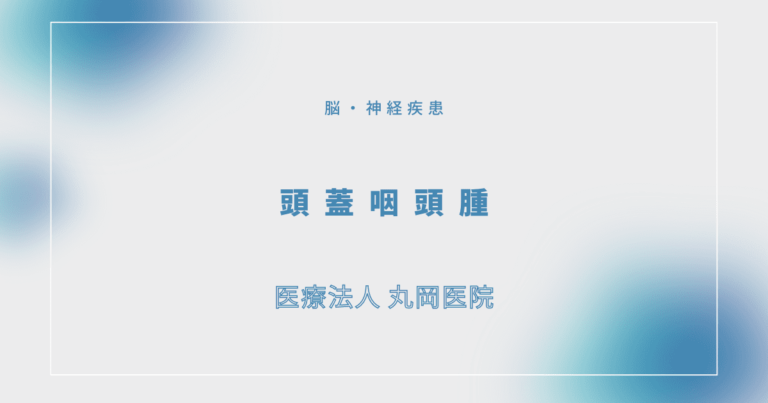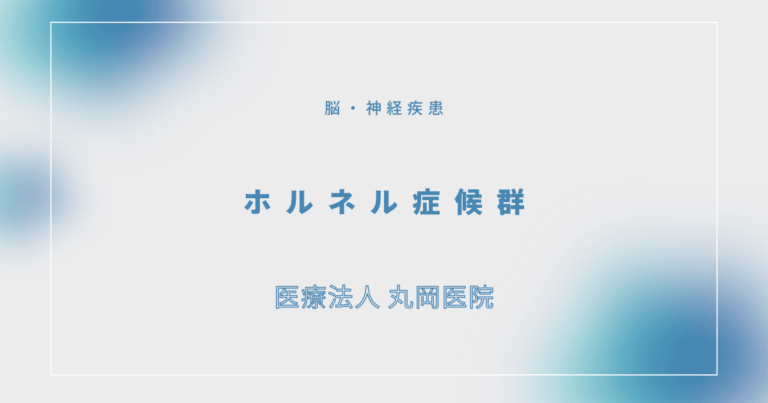ラクナ梗塞(lacunar infarction)とは、脳深部の穿通枝動脈における閉塞性病変により発症する脳梗塞です。
この疾患の原因となるのは、高血圧症や糖尿病などの基礎疾患による慢性的な血管障害で、血管壁の変性が徐々に進行していきます。
脳深部の穿通枝領域における微小循環障害により、脳組織が虚血状態に陥り、特徴的な小梗塞巣を形成することで神経症状が現れます。
ラクナ梗塞の主な症状
ラクナ梗塞では、片側の手足の筋力低下や感覚障害、構音障害、顔面の麻痺といった神経症状が突然現れることが多いです。
神経症状の多様性と特徴
ラクナ梗塞における神経症状は、脳の深部にある細い血管が閉塞することで生じ、症状は閉塞した血管の支配領域によって大きく異なります。
運動障害と感覚障害は、それぞれ単独で出現することもあれば両方が同時に現れることもあり、患者さんが示す症状の組み合わせは様々です。
| 症状の分類 | 代表的な症状 |
|---|---|
| 運動障害型 | 片側の手足の筋力低下や麻痺が中心となり、歩行時のふらつきや物を落としやすくなるなどの症状が現れる |
| 感覚障害型 | 手足のしびれや違和感、温度感覚の低下などが特徴的で、日常生活動作に影響を及ぼすことがある |
構音障害と嚥下機能への影響
構音障害は、脳幹部のラクナ梗塞でしばしば認められる症状で、発話時の明瞭度が低下することで周囲とのコミュニケーションに影響を及ぼします。
嚥下機能については、食事中にむせやすくなったり、飲み込みにくさを感じたりすることがあり、液体を飲む際に症状が目立つことが多いです。
症状は、脳幹部の神経核や神経線維の障害によって引き起こされます。
| 障害部位 | 特徴的な症状 |
|---|---|
| 内包領域 | 片側の手足の麻痺や感覚障害が中心で、顔面神経麻痺を伴うことがある |
| 脳幹部 | 構音障害、嚥下障害、めまい感などが特徴的な症状として出現 |
運動機能障害の具体的な様相
運動機能の障害の症状
- 片側の手足に力が入りにくく、細かい動作が困難になる
- 歩行時にふらつきや不安定さを感じる
- 顔の片側が歪んだり、表情が作りにくくなる
- 手の握力が低下し、物をつかむ力が弱くなる
- 足を引きずるような歩き方になる
運動機能の障害は、脳の運動を司る神経経路の障害によって引き起こされ、日常生活における基本的な動作に大きな影響を及ぼします。
手指の細かい動作の障害は、箸や鉛筆を使う際の困難さとして現れ、書字動作や食事動作に支障をきたします。
感覚障害の詳細な症状
感覚障害の症状は、しびれや痛み、温度感覚の低下など多岐にわたり、患者さんの体験する不快感や違和感は症状の出現部位によって様々です。
温度感覚や痛覚の障害は、やけどや凍傷などの危険性を高める要因となり得るため、入浴時や寒冷環境での細心の注意が必要となります。
深部感覚の障害により、手足の位置がわかりにくくなることで、歩行時のふらつきや物を持つ際の力加減が難しくなることがあります。
ラクナ梗塞の原因
ラクナ梗塞は、脳深部の穿通枝動脈における血管の変化と、それに伴う血流障害によって起きます。
発症の仕組み
血管内膜の細胞が損傷を受けることから始まり、その後血管壁の肥厚や硬化が進行することで、脳深部の穿通枝動脈における血流障害が生じます。
注目すべきなのは、持続する高血圧による血管への負担が内膜細胞を傷つけ、その後血管壁の変化が進行していくということです。
血管の変化は、脳深部の穿通枝と呼ばれる細い動脈において顕著に認められ、血流障害を起こし、脳組織への酸素や栄養の供給が不足する状態を招きます。
発症の要因
| 原因となる因子 | 影響する要素 |
|---|---|
| 基礎疾患 | 高血圧症、糖尿病、脂質異常症 |
| 生活習慣 | 喫煙、過度の飲酒、運動不足 |
| 既往歴 | 心房細動、動脈硬化症、脳卒中の既往 |
これらの要因は、血管内膜細胞の機能を低下させ、血管壁の構造変化を促進することで、ラクナ梗塞の発症リスクを大きく高めます。
血管変化の進行
血管の変化の進行過程
- 血管内膜細胞の機能障害
- 血管平滑筋の増殖
- 血管壁の線維化
- 血管内腔の狭小化
- 血管壁の脆弱化
変化は段階的に進行し、最終的に血管の閉塞や微小出血を引き起こす原因となります。
体質と環境因子の関連
| 体質的要因 | 環境因子との関連 |
|---|---|
| 家族歴 | 生活習慣による影響 |
| 遺伝的素因 | ストレス応答の違い |
| 人種差 | 食生活・文化的背景 |
個人の持つ遺伝的な特徴と、日常生活における環境要因が組み合わさることで、ラクナ梗塞の発症リスクが決定されることが、近年の研究で明らかになってきました。
特にアジア人においては、穿通枝動脈の解剖学的特徴と遺伝的背景から、欧米人と比較してラクナ梗塞の発症頻度が高いです。
診察(検査)と診断
ラクナ梗塞の診断は、神経学的診察から始まり、MRIやCTなどの画像検査、血液検査など複数の検査を組み合わせながら、段階的に診断を進めていきます。
初期診察の実際
神経学的診察では、脳の各部位の機能を詳しく調べることから始まり、運動機能、感覚機能、脳神経機能について入念な診察を行うことで、障害されている脳の部位をある程度推測することが可能です。
問診において、症状の出現時期や進行の様子、これまでの病歴や生活習慣について詳しく聴取し、神経学的診察の結果と合わせて、脳血管障害の有無や範囲を判断していきます。
| 診察項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 運動機能検査 | 筋力、協調運動、歩行状態 |
| 感覚機能検査 | 触覚、温度覚、痛覚、位置覚 |
| 脳神経検査 | 顔面神経、動眼神経、舌下神経機能 |
画像診断の進め方
MRI検査は、脳の微細な構造変化を捉えられ、DWI(拡散強調画像)とFLAIR(fluid-attenuated inversion recovery)を組み合わせることで、急性期のラクナ梗塞を高い精度で検出できます。
CT検査は、出血性病変の除外診断に優れており、発症直後の急性期において重要な検査となりますが、小さなラクナ梗塞の検出には限界があることに注意が必要です。
脳血管の状態を詳しく調べるための検査
- MRA(磁気共鳴血管撮影)による血管の形態観察
- 頸動脈エコーによる動脈硬化の評価
- 経頭蓋ドップラーによる脳血流速度の測定
- 経食道心エコーによる心源性塞栓の検索
- SPECTによる脳血流の評価
検査は、病態の理解や今後の方針決定において大きな意味を持ちます。
血液検査による全身状態の把握
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 凝固系検査 | PT-INR、APTT、Dダイマー |
| 脂質検査 | LDL、HDL、中性脂肪 |
| 糖代謝検査 | 血糖値、HbA1c |
| 炎症反応 | CRP、白血球数 |
血液検査では、脳梗塞の危険因子となる様々な項目を確認し、また全身状態を総合的に評価することで、今後の再発リスクの評価にも有用です。
長期的な経過観察の方法
定期的な画像検査を実施することで、梗塞巣の大きさや範囲の変化を観察し、また新たな病変の出現がないかどうかを確認します。
また、血圧測定や血液検査などの基本的な検査を継続的に行うことで、危険因子のコントロール状態を把握し、必要に応じて生活習慣の改善を提案することが大切です。
ラクナ梗塞の治療法と処方薬、治療期間
ラクナ梗塞の治療では、急性期における血栓溶解療法や抗血栓療法、慢性期における抗血小板薬の継続投与、さらに血圧管理のための降圧薬や脂質異常症に対するスタチン系薬剤の使用など、段階的な薬物療法を実施します。
急性期の治療戦略
急性期治療では、発症から4.5時間以内であれば血栓溶解療法(rt-PA静注療法)の実施を検討し、血栓を溶かすことで脳血流の早期改善が可能です。
アルガトロバンによる抗凝固療法は、血栓の進展を防ぎ、急性期の神経症状の増悪を抑制する効果が期待できます。
| 急性期治療薬 | 投与方法と期間 |
|---|---|
| rt-PA製剤 | 発症4.5時間以内に経静脈的に投与し、投与時間は1時間で完了 |
| アルガトロバン | 急性期に2週間程度、持続点滴で投与を継続 |
慢性期の抗血小板療法
慢性期の治療では、抗血小板薬を単剤あるいは併用で処方することが一般的です。
- アスピリン 1日1回100mgを継続的に服用し、再発予防効果を発揮
- クロピドグレル 1日1回75mgを服用し、血小板凝集抑制作用を示す
- シロスタゾール 1日2回100mgずつ服用し、血管拡張作用も併せ持つ
- プラスグレル 1日1回3.75mgを服用し、強力な血小板凝集抑制効果を発揮
- チクロピジン 1日2回100mgずつ服用し、血小板機能を抑制
抗血小板薬の選択では、患者さんの年齢や腎機能、既往歴などを考慮しながら、最も効果的な薬剤を判断し、服用開始後は定期的な血液検査を実施し、薬剤の効果や安全性を確認します。
血圧管理のための降圧療法
血圧管理のために、カルシウム拮抗薬やARB、ACE阻害薬などを使用し、目標血圧の達成を目指して投与量を調整していきます。
降圧薬の投与は、患者さんの血圧値や年齢に応じて個別に選択し、複数の薬剤を組み合わせることで、より効果的な血圧コントロールを目指します。
| 降圧薬の種類 | 投与量と特徴 |
|---|---|
| カルシウム拮抗薬 | 1日1回の服用で効果が持続し、脳血管拡張作用も期待できる |
| ARB/ACE阻害薬 | 1日1回の服用で臓器保護作用も併せ持つことから、広く使用 |
脂質異常症に対する治療
スタチン系薬剤は、LDLコレステロール値を低下させる効果があり、動脈硬化の進展予防になります。
投与開始後は、定期的な血液検査で脂質の状態を確認しながら、投与量の調整を行うことが大切です。
スタチン系薬剤は、夕食後または就寝前に服用することで、コレステロール合成を抑制し、非スタチン系薬剤として、エゼチミブやフィブラート系薬剤などの使用も検討します。
リハビリテーション治療
理学療法士による運動療法は、麻痺の改善や筋力維持に不可欠で、早期から積極的に実施することで、より高い回復効果が期待できます。
作業療法では、日常生活動作の改善を目指して、段階的に難易度を上げながら訓練を進めていくことが重要です。
また、言語聴覚士による構音障害や嚥下障害への介入も大切で、継続的な訓練により機能の改善を図れます。
リハビリテーションの期間は、急性期病院での2〜3週間の入院治療後、回復期リハビリテーション病院での3ヶ月程度の集中的な訓練へと移行することが多いです。
ラクナ梗塞の治療における副作用やリスク
ラクナ梗塞の治療では、抗血栓薬や血圧降下薬などの投薬治療に伴う出血性合併症や臓器障害などの副作用があります。
抗血栓薬による副作用
抗血栓薬の使用においては、出血性の副作用に対する慎重な経過観察が不可欠で、消化管出血や頭蓋内出血には細心の注意が必要です。
消化管出血のリスクを軽減するため、胃粘膜保護薬の併用を検討することがありますが、薬剤の相互作用による予期せぬ副作用の出現にも気を付けます。
抗血栓薬の副作用は、投与開始直後から数週間以内に現れることが多く、高齢者や腎機能障害のある患者さんでは、より慎重な投与量の調整とモニタリングを行います。
出血性の副作用は、軽度の皮下出血から重篤な消化管出血まで様々な程度で生じる可能性があり、抜歯などの観血的処置を行う際には、事前に医療機関への相談を行うことが大切です。
| 抗血栓薬の種類 | 主な副作用とその特徴 |
|---|---|
| アスピリン | 消化管出血、皮下出血、まれに気管支喘息発作を誘発することがあり、特に喘息の既往がある患者さんでは注意深い観察を要する |
| クロピドグレル | 出血傾向、肝機能障害、白血球減少、発疹などが現れることがあり、定期的な血液検査によるモニタリングが推奨される |
血圧降下薬に関連する副作用
血圧降下薬による急激な血圧低下は、脳血流の低下を引き起こす危険性があり、高齢者では起立性低血圧に伴うめまいや転倒のリスクが高まることから、投与開始時は少量から開始し、段階的に増量します。
腎機能障害がある患者さんでは、薬剤の体内蓄積による副作用の増強に注意を払い、定期的な腎機能検査によるモニタリングを実施することで、早期に異常を発見することが重要です。
利尿薬の使用では、電解質バランスの崩れによる不整脈や脱水などの合併症に注意が必要で、夏季には水分摂取量の調整や電解質補正を考慮することがあります。
- 過度の血圧低下による脱力感やめまい、失神などの症状が出現した際は、すぐに医療機関を受診
- カリウム値の異常に伴う不整脈の発現には、定期的な血液検査でモニタリングを行う
- 口渇や電解質異常の予防には、適切な水分摂取と食事管理が必要
- 咳嗽や気道刺激症状が持続する場合は、薬剤の変更を検討
- 末梢性浮腫や体重増加が認められる際は、利尿薬の用量調整を行うことがある
スタチン系薬剤の副作用
スタチン系薬剤による筋肉痛や筋力低下は、服薬継続の障害となることがあり、高齢者や運動負荷の高い患者さんでは注意深い観察が求められ、症状出現時には速やかな対応が必要です。
肝機能障害には注意深いモニタリングを行い、定期的な肝機能検査を実施することで早期発見につなげ、異常が認められた際には投与量の調整や一時的な休薬を検討します。
スタチン系薬剤の長期服用では、糖尿病の新規発症や既存の糖尿病の悪化に注意を払い、定期的な血糖値のモニタリングも重要な観察項目です。
| スタチンの副作用 | 症状と対応 |
|---|---|
| 筋障害 | 筋肉痛、脱力感、歩行困難が出現した際は、すぐに医師に相談し、CPK値の測定や投与量の見直しを行う |
| 肝機能障害 | 食欲不振、倦怠感、黄疸などの症状に注意し、定期的な肝機能検査で経過を観察し、異常時には投与を中断 |
リハビリテーションに伴うリスク
リハビリテーション実施時の過度な運動負荷は、血圧上昇や心負荷の増大を招く危険性があり、心血管系の合併症予防のため、運動強度の調整と頻繁なバイタルサインの確認が必要です。
麻痺のある患者さんでは、バランス障害による転倒のリスクが高まるため、訓練時の安全確保が重要で、必要に応じて補助具の使用や介助者の配置を考慮します。
関節拘縮や筋力低下の予防のため、早期からの運動療法は大切ですが、過度な負荷は逆効果となることがあり、段階的な負荷量の調整と患者さんの体力レベルに応じた個別のプログラム作成が大切です。
運動療法中の血圧変動や不整脈の出現には注意を払い、バイタルサインのモニタリングを実施し、異常が認められた際には直ちに運動を中止します。
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
入院時の基本的な治療費
| 治療内容 | 患者負担額(3割負担の場合) |
|---|---|
| 入院基本料(1日あたり) | 6,000円〜9,000円 |
| MRI検査 | 15,000円〜25,000円 |
| CT検査 | 8,000円〜12,000円 |
| 血液検査 | 3,000円〜5,000円 |
薬物療法にかかる費用
急性期の薬物療法では、以下の薬剤費用が発生します。
- 血栓溶解薬(アルテプラーゼ) 1回投与 約45,000円
- 脳保護薬(エダラボン) 14日間 約42,000円
- 抗血小板薬(クロピドグレル) 28日分 約4,500円
- 降圧薬(ARB系) 28日分 約3,500円
リハビリテーション費用
| リハビリ内容 | 1回あたりの費用(3割負担) |
|---|---|
| 理学療法 | 2,500円〜3,500円 |
| 作業療法 | 2,500円〜3,500円 |
| 言語聴覚療法 | 2,500円〜3,500円 |
長期治療における費用
継続的な外来治療では、月額で約15,000円から30,000円程度の医療費が必要となり、定期的な画像検査や血液検査の費用が含まれます。
以上
Horowitz DR, Tuhrim S, Weinberger JM, Rudolph SH. Mechanisms in lacunar infarction. Stroke. 1992 Mar;23(3):325-7.
Norrving B. Long-term prognosis after lacunar infarction. The Lancet Neurology. 2003 Apr 1;2(4):238-45.
Caplan LR. Lacunar infarction and small vessel disease: pathology and pathophysiology. Journal of stroke. 2015 Jan;17(1):2.
You R, McNeil JJ, O’malley HM, Davis SM, Donnan GA. Risk factors for lacunar infarction syndromes. Neurology. 1995 Aug;45(8):1483-7.
Lastilla M. Lacunar infarct. Clinical and Experimental Hypertension. 2006 Jan 1;28(3-4):205-15.
Jackson C, Sudlow C. Comparing risks of death and recurrent vascular events between lacunar and non-lacunar infarction. Brain. 2005 Nov 1;128(11):2507-17.
Samuelsson M, Söderfeldt B, Olsson GB. Functional outcome in patients with lacunar infarction. Stroke. 1996 May;27(5):842-6.
Arboix A, Font A, Garro C, Garcia-Eroles L, Comes E, Massons J. Recurrent lacunar infarction following a previous lacunar stroke: a clinical study of 122 patients. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2007 Dec 1;78(12):1392-4.
Bamford J, Sandercock P, Jones L, Warlow C. The natural history of lacunar infarction: the Oxfordshire Community Stroke Project. Stroke. 1987 May;18(3):545-51.
Loeb C, Gandolfo C, Croce R, Conti M. Dementia associated with lacunar infarction. Stroke. 1992 Sep;23(9):1225-9.