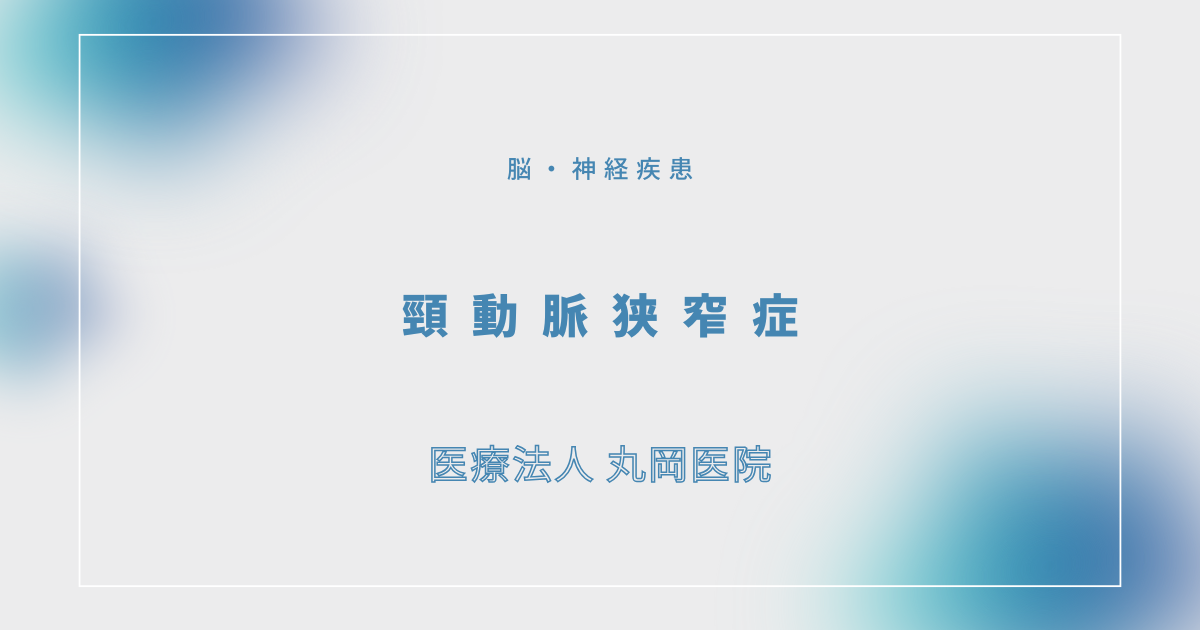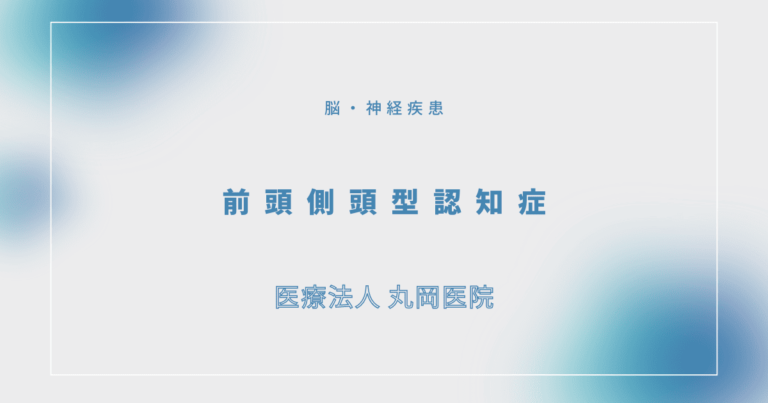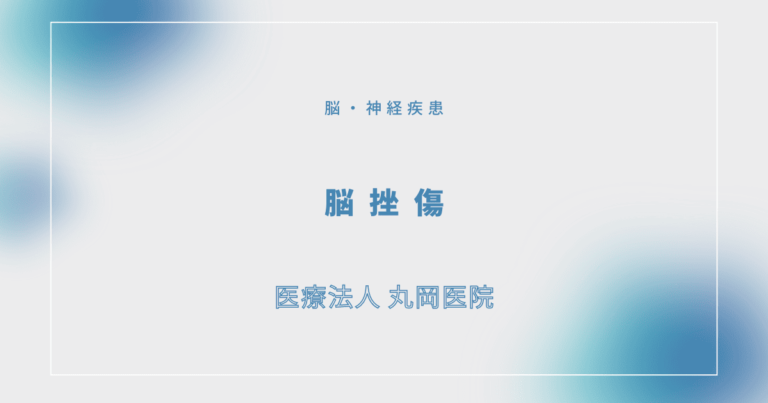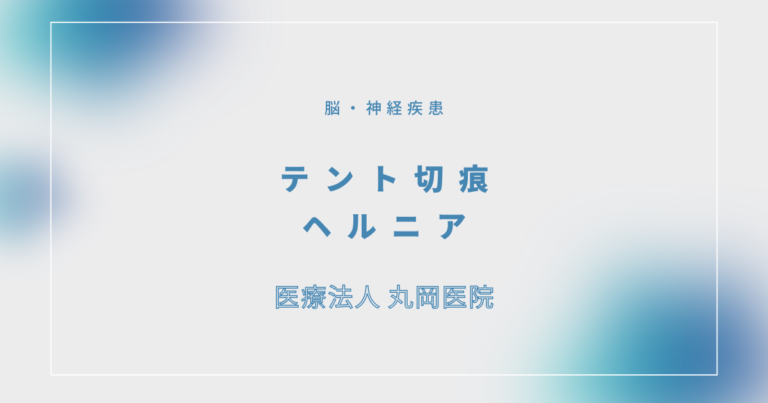頸動脈狭窄症(carotid artery stenosis)とは、首の両側を走る太い血管である頸動脈の内側が、コレステロールなどの脂質が蓄積することによって徐々に狭くなり、脳への血流が妨げられる疾患です。
この病気は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を背景として、長い年月をかけて少しずつ進行していき、加齢とともに発症リスクが高まります。
狭くなった血管では血液の流れが悪くなるだけでなく、その部分に血栓ができやすくなり、血栓が血流に乗って脳の血管に詰まると、重大な脳梗塞を引き起こす危険があります。
頸動脈狭窄症の主な症状
頸動脈狭窄症は、一過性の視力障害や半身の脱力感から、重度の場合には脳梗塞による永続的な麻痺まで、多様な神経症状を引き起こします。
一過性脳虚血発作の症状
一時的な脳血流の低下によって、様々な神経症状が出現し、症状は突然発症し、数分から数時間程度で自然に改善することが特徴的です。
特に注目すべき点として、症状の一過性という性質は、将来的な脳梗塞発症の警告サインとなり得ます。
| 症状の種類 | 特徴的な表現 |
| 視覚症状 | カーテンが下りる感覚 |
| 言語症状 | 呂律が回らない状態 |
| 運動症状 | 手足の急な脱力 |
| 感覚症状 | 片側のしびれ感 |
一過性の症状は、脳の血流が一時的に不足することで起こり、血流が回復すると症状も消失します。
ただし、症状が短時間で改善したとしても、頸動脈狭窄の進行を示唆する重大なサインとして捉えることが必要です。
眼症状と視覚異常
視覚異常は、網膜への血流低下が原因で発生し、特に一過性黒内障は頸動脈狭窄症に特徴的な症状です。
患者さんの多くは、「突然片目が見えなくなる」という不安な体験をされ、症状は数分程度で自然に改善することが多いものの、放置すべきではありません。
- 一過性黒内障
- 視野欠損
- 複視
- 光のちらつき
- かすみ目
運動機能障害
片側の手足に突然の脱力感や麻痺が生じることがあり、手足の脱力は瞬間的に発症することが多く、患者さんに不安にさせる代表的な症状です。
| 障害部位 | 具体的症状 |
| 上肢 | 物が持てない |
| 下肢 | 歩行困難 |
| 顔面 | 表情筋の麻痺 |
| 舌 | 構音障害 |
運動障害は、数分から数時間で改善する一過性のものから、持続するものまで様々で、症状の持続時間や改善の程度は、血管の狭窄度合いや側副血行路の発達状態によって異なります。
感覚障害と神経症状
手足のしびれや感覚鈍麻が多く見られ、症状は片側性に生じることが特徴的です。
感覚障害は、上肢から始まり下肢に及び、時には顔面や口周囲にも及ぶことがあります。
顔面や口周囲のしびれ感も特徴的な症状であり、症状は患者さんの食事動作や会話にも影響を与え、また、感覚障害は運動障害と同様に、一過性のものから持続性のものまで様々な経過をたどります。
言語障害
言葉が出にくくなったり、他人の言葉が理解しづらくなったりすることがあり、突然の言語障害は、周囲の人々が最初に気付く症状となることも多く、社会生活への影響も大きいです。
言語障害は、流暢な会話が困難になる運動性失語や、言葉の理解が困難になる感覚性失語など、様々な形態で現れ、また、構音障害として、発音が不明瞭になることも少なくありません。
頸動脈狭窄症の原因
頸動脈狭窄症は、加齢による自然な血管の変化に加えて、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病、そして喫煙や運動不足などの生活習慣が長年にわたって血管に影響を与え続けることで進行します。
生活習慣病による血管への影響
生活習慣病は血管の内壁に様々なダメージを与え続け、持続的な高血圧状態では血管内皮細胞が物理的なストレスにより損傷を受け、そこに脂質やコレステロールが入り込んで蓄積していくことで、動脈硬化の進行を加速させます。
血管壁への継続的な圧力は炎症反応を起こし、損傷を受けた部分に白血球が集まることで、プラークと呼ばれる隆起が形成され、徐々に血管内腔が狭くなっていくのです。
糖尿病による持続的な高血糖状態は、血管内皮細胞の機能を著しく低下させ、活性酸素の産生を促進することで血管壁の修復能力を弱めるとともに、異常な血管新生を引き起こし、動脈硬化の進行を促進します。
| 生活習慣病 | 血管への影響 |
| 高血圧 | 血管内皮の損傷 |
| 糖尿病 | 血管の炎症 |
| 脂質異常症 | プラーク形成 |
| 肥満 | 血管の機能低下 |
生活習慣要因
日常生活における様々な生活習慣が、頸動脈の健康状態に深刻な影響を及ぼすことが明らかになっています。
特に喫煙習慣は血管内皮細胞を直接的に傷つけるだけでなく、慢性的な炎症を引き起こすとともに、血液凝固能を亢進させることで動脈硬化を促進します。
- 喫煙による血管内皮の損傷
- 運動不足による血流の停滞
- 過度な飲酒による血圧上昇
- ストレスによる自律神経の乱れ
- 不規則な食生活
- 睡眠不足による代謝異常
複数の生活習慣要因が重なり合うことで、血管への悪影響は相乗的に増大し、特に運動不足は血流の停滞を起こし、血管内皮細胞の機能低下や肥満、糖尿病のリスク上昇にもつながり、動脈硬化の進行を加速させます。
加齢による血管の変化
加齢に伴う血管の変化は生理的な現象として避けられないものですが、進行速度は生活習慣や遺伝的要因によって大きく異なり、不適切な生活習慣が重なると、血管の老化が早まります。
40代から始まる血管の弾力性の低下は、血管壁を構成する弾性繊維の減少や膠原繊維の増加によって起こり、これに炎症や酸化ストレスが加わることで、内膜の肥厚や石灰化が徐々に進行していきます。
| 年齢 | 血管の変化 |
| 40代 | 弾力性の低下 |
| 50代 | 内膜の肥厚 |
| 60代 | 石灰化の進行 |
| 70代以上 | 血管壁の硬化 |
50代以降になると血管内膜の肥厚が顕著となり、60代に入ると血管壁の石灰化が急速に進行することで、血管の柔軟性が著しく失われ、様々な血管障害のリスクが飛躍的に高まっていきます。
遺伝的要因と体質
遺伝的な要因は動脈硬化の進行速度に決定的な影響を与えます。
動脈硬化性疾患の家族歴がある方では、若年期から血管壁の脆弱性や脂質代謝異常が顕在化しやすい傾向にあることが分かっています。
両親や兄弟に早期発症の動脈硬化性疾患の既往がある場合、血管内皮細胞の修復能力が低下していたり、コレステロールの代謝に関わる遺伝子の変異を受け継いでいたりする可能性が高いです。
診察(検査)と診断
頸動脈狭窄症の診断には、詳細な問診から画像検査まで、複数の検査を組み合わせることで、血管狭窄の程度や範囲を正確に把握することが不可欠となります。
初期診察と神経学的検査
頸動脈の聴診による血管雑音の確認は頸動脈狭窄を示唆する重要な検査法で、特に収縮期雑音の聴取は狭窄の存在を強く示唆する所見です。
| 診察項目 | 診察内容 |
| 頸部聴診 | 血管雑音の有無 |
| 脈拍触診 | 左右差の確認 |
| 血圧測定 | 両側同時測定 |
| 神経診察 | 脳神経機能確認 |
神経学的診察では、顔面の動きや舌の動き、眼球運動など、脳神経系の機能を詳細に観察することで神経学的な異常の有無を判断し、また両側の血圧を同時に測定することで左右差の存在も確認します。
画像検査による血管評価
- 頸動脈超音波検査
- MRアンギオグラフィー
- CTアンギオグラフィー
- 脳血管造影検査
- 経頭蓋ドップラー検査
画像検査により血管の形態や血流の状態を詳細に観察でき、頸動脈超音波検査は非侵襲的で繰り返し実施できる利点で、血管壁の性状や血流速度などの経時的な変化を継続的に追跡することが可能です。
MRアンギオグラフィーやCTアンギオグラフィーによる検査では、血管の立体的な構造を把握するとともに、周辺組織との関係性も含めた総合的な画像診断を行えます。
血液検査と生化学マーカー
血液検査においては、脂質異常症や糖尿病、炎症反応など、動脈硬化に関連する様々な因子を確認するとともに、血管病変の進行に関与する要因について詳しく調べていきます。
| 検査項目 | 確認内容 |
| 脂質検査 | コレステロール値 |
| 凝固系 | 血液粘性 |
| 炎症反応 | CRP値 |
| 血糖値 | 糖尿病の有無 |
検査結果は動脈硬化の程度や進行速度を推測する上で大切な指標となり、また凝固系の検査では血栓形成のリスクについても評価を行っていきます。
神経機能検査
瞳孔反応や視野、眼球運動などの脳神経系の機能を細かく確認することで、脳血流低下による神経機能への影響を調べるとともに、視野検査や眼底検査による網膜血流の状態も重要な指標です。
運動機能や感覚機能の左右差、協調運動や反射機能なども含めた神経学的診察を通じて、微細な神経学的異常の存在について慎重に確認を進めます。
心機能検査
心電図検査や心エコー検査を併せて実施することで、不整脈の有無や心機能の状態を観察しながら、心原性脳塞栓症のリスク因子となる心疾患の有無を確認します。
心房細動などの不整脈の発見は脳梗塞予防の観点からも可能性のある所見として捉え、また他の心疾患との関連性についても検討を加えながら、心機能評価を実施することが大切です。
頸動脈狭窄症の治療法と処方薬、治療期間
頸動脈狭窄症の治療は、動脈硬化の進行度と狭窄の程度に応じて、抗血小板薬や降圧薬などの薬物療法を基本とし、狭窄が高度な場合には頸動脈内膜剥離術やステント留置術などの外科的治療を組み合わせます。
内科的治療の基本方針
薬物療法による内科的治療は、血栓の形成を防ぎながら、さらなる動脈硬化の進行を抑制することを目指し、複数の作用機序の異なる薬剤を組み合わせて治療効果を高めます。
抗血小板薬は血小板の凝集を抑制することで血栓の形成を防ぎ、アスピリンやクロピドグレルなどの薬剤を、患者さんの状態や他の持病との兼ね合いを考慮しながら使用します。
| 薬剤分類 | 主な治療目的 |
| 抗血小板薬 | 血栓予防 |
| 降圧薬 | 血圧コントロール |
| スタチン | コレステロール低下 |
| 抗糖尿病薬 | 血糖値管理 |
血圧のコントロールは動脈硬化の進行抑制に重要で、カルシウム拮抗薬やARB、ACE阻害薬などの降圧薬を、単剤あるいは複数組み合わせて用い、24時間にわたる安定した降圧効果が目標です。
外科的治療の選択と実際
狭窄が70%を超えるような症例では、内科的治療に加えて外科的治療の実施を検討し、手術方法は患者さんの年齢や全身状態、動脈硬化の範囲などを総合的に判断して選択します。
- 頸動脈内膜剥離術(CEA)
- カテーテル治療(CAS)
- ハイブリッド手術
- バイパス手術
- 経皮的血管形成術
手術方法のうち、頸動脈内膜剥離術は、頸動脈を直接切開して動脈硬化によって厚くなった内膜を剥離除去する方法で、長期的な治療効果が期待できる標準的な術式です。
| 手術方法 | 治療期間 |
| CEA | 入院2週間 術後観察3か月 |
| CAS | 入院1週間 術後観察3か月 |
| ハイブリッド手術 | 入院3週間 術後観察6か月 |
| バイパス手術 | 入院4週間 術後観察6か月 |
治療期間と段階的アプローチ
治療開始から安定期に入るまでの期間は、3か月から半年程度を要し、この間、定期的な画像検査や血液検査を行いながら、薬物療法の効果や手術後の経過を評価します。
初期の4週間は特に厳密な血圧管理と抗血栓療法が必要で、その後の8週間は段階的に投薬内容を調整しながら、安定した治療効果を目指します。
手術を実施した場合は、術後の回復期間として2週間から1か月程度の入院療養、その後の3か月間は定期的な外来通院によっての経過観察が必要です。
処方薬の投与スケジュール
抗血小板薬は、発症早期から継続的な服用が必要で、アスピリンやクロピドグレルを中心に、単剤あるいは複数の薬剤を組み合わせて使用します。
降圧薬は、24時間にわたって安定した血圧コントロールを実現するため、作用時間の異なる薬剤を組み合わせ、朝晩の定時の服用を基本として、必要に応じて昼間の追加服用も検討することが重要です。
スタチンなどの脂質異常症治療薬は、コレステロール値を適切な範囲にコントロールすることで、さらなる動脈硬化の進行を抑制し、長期的な治療効果の維持を目指します。
抗糖尿病薬は、血糖値の変動を抑制することで血管への負担を軽減し、動脈硬化の進行を抑制する効果が期待できるため、糖尿病を合併している患者さんには継続的な使用が必要です。
頸動脈狭窄症の治療における副作用やリスク
頸動脈狭窄症の治療においては、投薬療法から血管内手術まで、それぞれの医療介入に伴う特有の副作用やリスクがあし、出血性および虚血性の合併症に注意を払う必要があります。
薬物療法における副作用
抗凝固薬や抗血小板の使用に伴う出血傾向の増加や、血圧降下剤による急激な血圧低下など、投薬治療には様々な副作用が伴います。
| 薬剤分類 | 発生しうる副作用 |
| 抗凝固薬 | 消化管出血、皮下出血 |
| 抗血小板薬 | 鼻出血、歯肉出血 |
| 降圧薬 | めまい、起立性低血圧 |
| 脳保護薬 | 肝機能障害、腎機能障害 |
投薬に関連する副作用の程度は、患者さんの年齢や体重、他の基礎疾患の有無により、特に高齢者では慎重な薬剤選択が大切です。
血管内治療に伴うリスク
- カテーテル操作による血管損傷
- 造影剤による腎機能障害
- 放射線被曝の影響
- 術中の血栓形成
- 穿刺部位の感染
合併症は手術手技の複雑さや血管の状態によって発生リスクが変動し、血管の蛇行が強い症例や石灰化が著しい病変では、より慎重な手技操作が重要です。
術中・術後の合併症
血管内手術や頸動脈内膜剥離術などの外科的治療における術中・術後の合併症には、様々な種類と段階があります。
| 時期 | 発生しうる合併症 |
| 術中 | 血圧変動、不整脈 |
| 術直後 | 過灌流症候群、出血 |
| 術後早期 | 創部感染、血腫形成 |
| 遠隔期 | 再狭窄、血栓形成 |
外科的処置に伴う合併症は、手術時間の延長や術中の血行動態の変化によって発生リスクが上昇し全身状態が不安定な患者さんでは注意が必要です。
全身麻酔に関連するリスク
全身麻酔下での治療においては、気道確保の困難さや術中の血圧管理など、麻酔に関連する様々なリスクがあり、高齢者や心肺機能に問題がある患者さんでは、より慎重な麻酔管理が不可欠となります。
麻酔導入時や覚醒時の血圧変動は、脳血流に重大な影響を及ぼす可能性があるため、細やかな循環動態の管理と薬剤投与が必要です。
周術期の循環動態変化
手術操作に伴う血行動態の変化は、脳血流に直接的な影響を与える可能性があり、特に頸動脈の遮断時や再開通時には、厳重な血圧管理と脳保護を行います。
血圧の急激な変動は、脳灌流圧にも大きな影響を与えることから、術中の血圧管理には細心の注意を払う必要があります。
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
入院時の基本的な費用
一般病棟での入院費用は、病室のタイプによって1日あたりの費用が異なり、4人部屋で5,000円から個室では20,000円程度となります。
集中治療室(ICU)での管理が必要な際は、1日あたり20,000円から30,000円です。
| 入院施設 | 1日あたりの費用(3割負担) |
| 一般病床 | 5,000-8,000円 |
| 2人部屋 | 8,000-12,000円 |
| 個室 | 12,000-20,000円 |
| ICU | 20,000-30,000円 |
手術に関連する費用
手術費用は術式によって異なり、カテーテル治療では80万円から120万円、開頭手術では100万円から180万円程度の費用が必要です。
- カテーテル治療(CAS)80-120万円
- 頸動脈内膜剥離術(CEA)100-150万円
- ハイブリッド手術 150-200万円
- バイパス手術 120-180万円
- 血管形成術 70-100万円
投薬治療に関わる費用
継続的な投薬治療には、抗血小板薬や降圧薬などの薬剤費用として、月額5,000円から15,000円程度の費用が発生します。
| 薬剤の種類 | 月額費用(3割負担) |
| 抗血小板薬 | 3,000-8,000円 |
| 降圧薬 | 2,000-5,000円 |
| スタチン | 3,000-7,000円 |
| 糖尿病薬 | 4,000-10,000円 |
画像診断に関わる費用
頭部MRIやMRAなどの画像検査は、1回あたり10,000円から20,000円で、造影剤を使用する場合はさらに5,000円から10,000円かかります。
脳血管造影検査は、検査自体の費用が15,000円から25,000円で、使用する造影剤の種類や量によってさらに10,000円から20,000円程度の追加費用が発生します。
リハビリテーション関連費用
入院中のリハビリテーション料金は1日あたり3,000円から8,000円程度で、通常2週間から1か月程度の期間が必要です。
退院後の外来リハビリテーションでは、1回あたり2,000円から5,000円程度の費用が発生します。
以上
Saxena A, Ng EY, Lim ST. Imaging modalities to diagnose carotid artery stenosis: progress and prospect. Biomedical engineering online. 2019 Dec;18:1-23.
Flaherty ML, Kissela B, Khoury JC, Alwell K, Moomaw CJ, Woo D, Khatri P, Ferioli S, Adeoye O, Broderick JP, Kleindorfer D. Carotid artery stenosis as a cause of stroke. Neuroepidemiology. 2012 Oct 11;40(1):36-41.
Inzitari D, Eliasziw M, Gates P, Sharpe BL, Chan RK, Meldrum HE, Barnett HJ. The causes and risk of stroke in patients with asymptomatic internal-carotid-artery stenosis. New England Journal of Medicine. 2000 Jun 8;342(23):1693-701.
Bernhard VM, Johnson WD, Peterson JJ. Carotid artery stenosis: association with surgery for coronary artery disease. Archives of Surgery. 1972 Dec 1;105(6):837-40.
Brott TG, Hobson RW, Howard G, Roubin GS, Clark WM, Brooks W, Mackey A, Hill MD, Leimgruber PP, Sheffet AJ, Howard VJ. Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. New England Journal of Medicine. 2010 Jul 1;363(1):11-23.
Lanzino G, Rabinstein AA, Brown Jr RD. Treatment of carotid artery stenosis: medical therapy, surgery, or stenting?. InMayo Clinic Proceedings 2009 Apr 1 (Vol. 84, No. 4, pp. 362-368). Elsevier.
Bladin CF, Alexandrov AV, Murphy J, Maggisano R, Norris JW. Carotid stenosis index: a new method of measuring internal carotid artery stenosis. Stroke. 1995 Feb;26(2):230-4.
Arasu R, Arasu A, Muller J. Carotid artery stenosis: An approach to its diagnosis and management. Australian journal of general practice. 2021 Nov 1;50(11):821-5.
Craig DR, Meguro K, Watridge C, Robertson JT, Barnett HJ, Fox AJ. Intracranial internal carotid artery stenosis. Stroke. 1982 Nov;13(6):825-8.
Barnett HJ, Gunton RW, Eliasziw M, Fleming L, Sharpe B, Gates P, Meldrum H. Causes and severity of ischemic stroke in patients with internal carotid artery stenosis. Jama. 2000 Mar 15;283(11):1429-36.