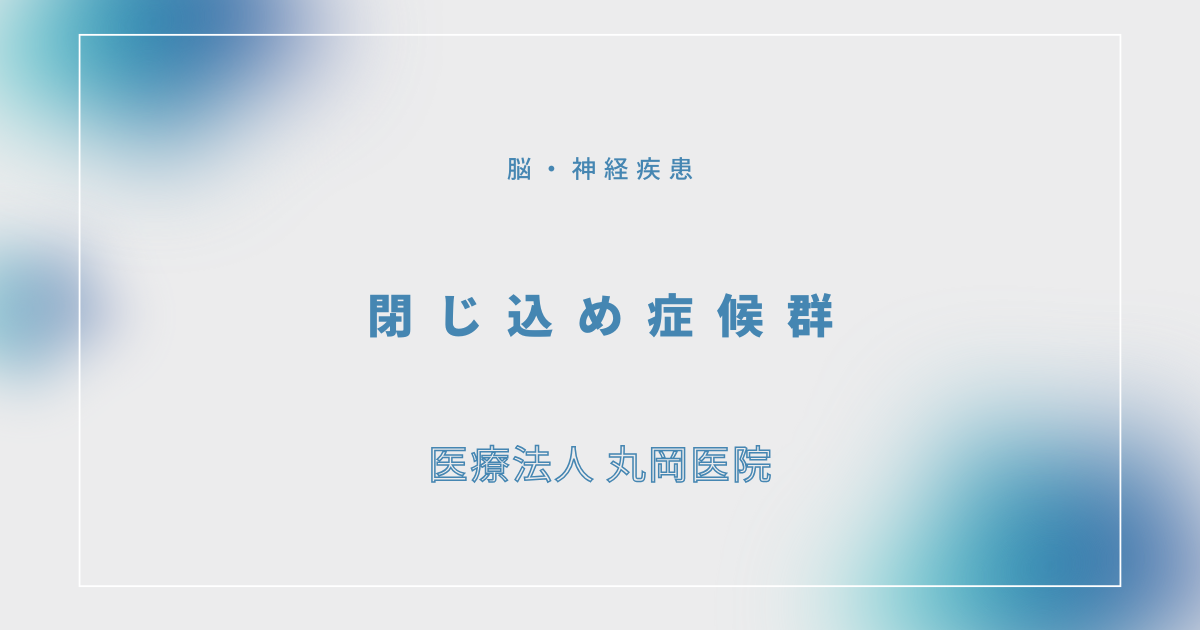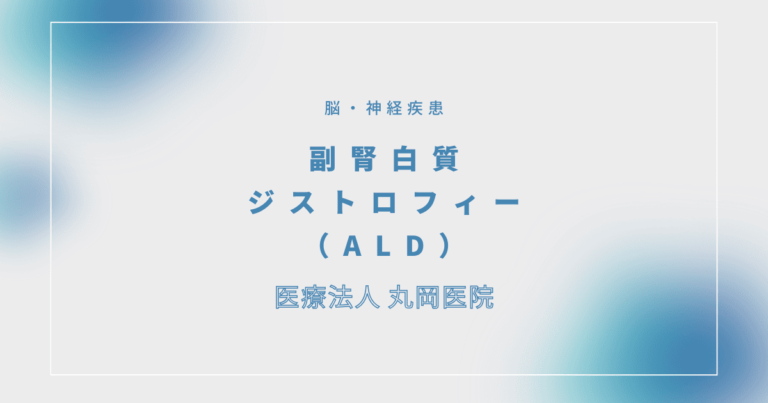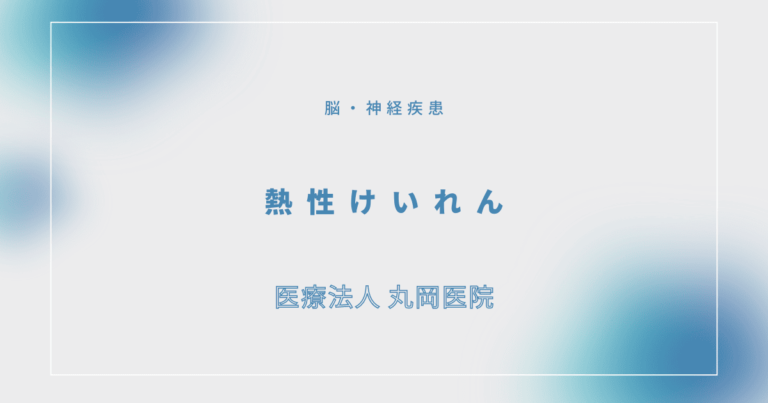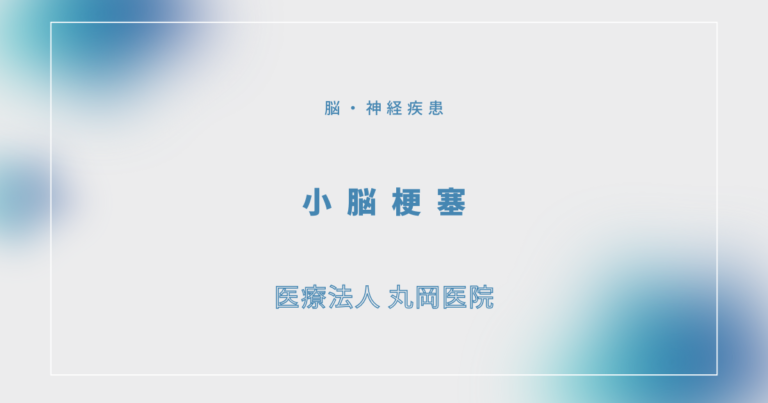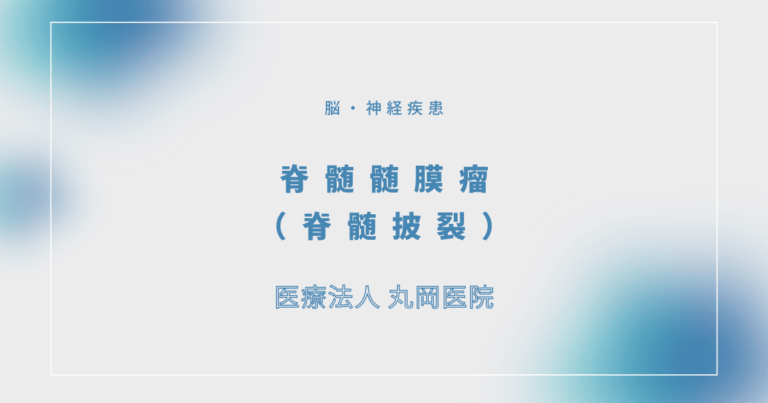閉じ込め症候群(locked-in syndrome)とは、脳幹部の特定の領域の損傷によって、意識や知能は正常なものの、随意筋の麻痺により、自力での発声や四肢の動きが困難となる神経学的な症候群です。
患者さんは周囲の状況を完全に理解し、考えることも感じることもできる一方で、垂直方向の眼球運動以外の身体動作が著しく制限されます。
目の動きを通じたコミュニケーション方法を確立することで、患者さんの意思や要望を把握し、医療ケアを提供することが必要です。
閉じ込め症候群の主な症状
閉じ込め症候群の患者さんは、意識と認知機能が完全に保たれているにもかかわらず、全身の随意運動が制限され、垂直方向の眼球運動と瞬き以外の動作が困難となります。
基本的な神経学的症状
脳幹部の障害により、四肢と体幹の運動麻痺が顕著に表れ、発声や嚥下機能も大きく損なわれる一方で、意識ははっきりとした状態を保ち、記憶力や思考力などの高次脳機能も正常に維持されることが特徴です。
患者さんは、周囲で起きている出来事を明確に理解し、記憶や思考などの認知機能も働き続けるものの、表現するための身体機能が著しく制限されることにより、独特な症状パターンを示します。
脳幹部の損傷による神経学的な症状は、運動系と感覚系に異なる影響を及ぼします。
| 保たれる機能 | 障害される機能 |
| 意識レベル | 四肢の随意運動 |
| 認知機能 | 発声機能 |
| 垂直性眼球運動 | 嚥下機能 |
| 瞬き | 水平性眼球運動 |
症状パターンは脳幹部における特定の神経回路の障害によって引き起こされ、残存する機能と失われる機能の組み合わせが非常に特徴的な様相を呈します。
コミュニケーション機能
垂直方向への眼球運動と瞬きという限られた動作のみが残るため、残った機能を活用した独自のコミュニケーション方法を確立することが、大きな課題です。
医療従事者やご家族は、患者さんの眼球運動や瞬きのパターンを細やかに観察し、効果的な手段を段階的に構築していくことで、患者さんとの意思疎通を図ることが求められます。
自律神経系への影響
自律神経系の制御に関与する脳幹部の損傷により、以下のような症状が現れます。
- 体温調節機能の低下
- 血圧変動の不安定性
- 発汗異常
- 心拍数の変動
- 消化管機能の低下
自律神経症状は、患者さんの全身状態に多大な影響を及ぼすことから、24時間体制での継続的なモニタリングと細観察が必須です。
自律神経系の症状は、日内変動や環境要因によって変化することが多く、患者さんの状態を常に注意深く観察し、わずかな変化も見逃さないよにする必要があります。
感覚機能と覚醒状態
| 感覚の種類 | 特徴と状態 |
| 体性感覚 | 痛覚や温度覚は保持 |
| 視覚機能 | 基本的に維持 |
| 聴覚機能 | 通常は保持 |
| 嗅覚機能 | 多くの場合維持 |
感覚機能は基本的に保持されており、外界からの様々な刺激を正常に知覚することが可能なので、患者さんの感覚機能を活用したコミュニケーション方法を工夫できます。
覚醒状態も通常通り維持され、昼夜のリズムや睡眠覚醒サイクルにも大きな支障をきたすことはないため、患者さんの生活リズムに合わせた医療ケアを提供することが望ましいです。
閉じ込め症候群の原因
閉じ込め症候群の主な原因は、脳幹部、特に橋と呼ばれる部位における血管障害や外傷性損傷で、神経組織の障害によって意識と認知機能は保たれたまま、全身の随意運動が著しく制限される状態が起きます。
血管性病変による発症
脳底動脈の閉塞や出血が、閉じ込め症候群の発症原因として最も高い頻度で確認され、脳底動脈の血栓性閉塞や動脈硬化性変化による狭窄が典型的な原因です。
| 血管性病変 | 解剖学的特徴 |
| 脳底動脈閉塞 | 橋の腹側領域への血流が途絶える |
| 脳底動脈解離 | 血管壁の内膜が裂け、血流障害が生じる |
| 脳底部出血 | 出血により橋への圧迫が起こる |
脳底動脈は橋への主要な血液供給源として機能しており、この血管に何らかの異常が生じると、神経細胞への酸素や栄養の供給が途絶え、深刻な神経学的障害を起こします。
血管性の原因の中でも、特に動脈硬化性変化による脳底動脈の狭窄や閉塞は、加齢とともにリスクが上昇することが知られており、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病との関連も指摘されています。
外傷性損傷による発症
脳幹部への直接的な外力や、急激な頭部の回転運動による以下のような損傷が原因となり、外傷による二次的な脳幹損傷には細心の注意が必要です。
- 交通事故による脳幹部への衝撃
- 高所からの転落による頭部外傷
- スポーツ外傷による脳幹損傷
- 頭蓋底骨折による二次的な脳幹損傷
- 頸椎損傷に伴う脳幹部の圧迫
外傷性の脳幹損傷では、受傷直後の一次性損傷に加えて、その後に発生する脳浮腫や循環障害による二次性損傷が病態を複雑化させる要因です。
自動車事故などの高エネルギー外傷では、頭部への直接的な衝撃だけでなく、急激な加速度変化による脳の変位も重大な損傷を生じさせます。
炎症性疾患による発症
炎症性疾患による脳幹部の障害は、急性または慢性の経過をたどりながら進行性に神経症状を悪化させ、早期の診断と対応が不可欠です。
| 炎症性疾患 | 病態の特徴 |
| 脳幹脳炎 | ウイルスや細菌による炎症 |
| 多発性硬化症 | 自己免疫による神経組織の破壊 |
| 視神経脊髄炎 | 抗アクアポリン4抗体による炎症 |
また、自己免疫性疾患による脳幹部の炎症性変化は、再発と寛解を繰り返しながら徐々に神経組織に障害を与えます。
腫瘍性病変による発症
脳幹部における原発性腫瘍の発生や他臓器からの転移性腫瘍の存在が、周囲組織への圧迫や浸潤を通じて発症の重要な原因となります。
腫瘍による圧迫は、進行性に神経症状を悪化させる傾向があり、早期発見と迅速な対応が大切です。
特に転移性腫瘍の場合、原発巣の特定と全身状態の評価を含めたアプローチが求められます。
代謝性疾患による発症
代謝性の原因としては、様々な中毒性物質への曝露や代謝異常が脳幹部の機能障害を起こすことが報告されています。
ミトコンドリア病などの先天性代謝異常も、まれではありますが閉じ込め症候群の原因となる可能性があり、若年発症例では考慮に入れるべき病態の一つです。
代謝性疾患による脳幹障害では、全身的な代謝異常の是正と並行して、神経組織の保護を図ることが求められます。
診察(検査)と診断
閉じ込め症候群の診断においては、神経学的所見の詳細な観察と画像検査による脳幹部の評価を組み合わせた多面的なアプローチが必要です。
初期診察における神経学的検査
神経学的所見の確認において、患者さんの意識状態と認知機能の保持を確認しながら、運動機能と感覚機能の評価を実施することで、症状の全体像を把握します。
特に垂直性眼球運動と瞬きの状態を注意深く観察し、これらの動作による意思表示が可能かどうかを確認することは、診断プロセスにおいて極めて重要な要素です。
患者さんの反応を細かく観察しながら、複数回の診察を通じて症状の一貫性や変化を確認し、より正確な神経学的所見の把握を行います。
| 診察項目 | 観察のポイント |
| 意識状態 | 覚醒度と応答性 |
| 眼球運動 | 垂直運動の有無 |
| 瞬き反応 | 随意性の確認 |
| 四肢麻痺 | 運動障害の程度 |
画像診断による脳幹評価
MRIやCTなどの画像検査を用いて脳幹部の状態を詳細に観察することで、病変の位置や範囲を正確に知り、診断の確実性を高めます。
MRI検査で調べる項目
- 脳幹部の構造異常
- 血管障害の有無
- 浮腫の程度
- 圧迫所見の確認
- 周辺組織への影響
画像検査の結果は、複数の専門医による詳細な検討を経て、画像所見と神経学的所見を慎重に照らし合わせながら、診断の精度を上げることが必要です。
神経生理学的検査
脳波検査や誘発電位検査などの神経生理学的検査により、脳機能の状態を客観的に評価することで、より詳細な病態の把握が可能です。
神経生理学的検査の結果は、経時的な変化も含めて慎重に分析することで、診断の精度向上に大きく貢献します。
| 検査種類 | 確認内容 |
| 脳波検査 | 基礎波形の確認 |
| 聴性脳幹反応 | 脳幹機能の評価 |
| 体性感覚誘発電位 | 感覚伝導路の確認 |
| 運動誘発電位 | 運動神経路の評価 |
検査結果は、患者さんの状態に応じて実施し、複数回の測定結果を比較検討することで、より正確な診断に繋がります。
閉じ込め症候群の治療法と処方薬、治療期間
閉じ込め症候群の治療アプローチには、急性期における血栓溶解療法や抗凝固療法などの薬物療法、理学療法・作業療法・言語療法などのリハビリテーション、そして呼吸・循環管理などの全身管理が含まれます。
急性期の薬物療法
血栓溶解薬や抗凝固薬による初期治療が、血管性の原因による閉じ込め症候群において重要で、発症後できるだけ早期に投与を開始することで治療効果を高めることが可能です。
発症早期の血栓溶解療法では、組織プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)などを使用し、血管内の血栓を溶解することで、脳幹部への血流を回復させることを目指します。
| 薬剤分類 | 使用目的と特徴 |
| 血栓溶解薬 | 血栓を溶解し、血流を回復させる |
| 抗凝固薬 | 新たな血栓形成を予防する |
| 抗血小板薬 | 血小板凝集を抑制する |
血栓溶解療法の実施後は、抗凝固薬や抗血小板薬による継続的な治療を行い、新たな血栓形成を予防することで、再発防止を図ります。
神経保護療法
神経保護療法では、以下の薬剤を組み合わせて使用することで、脳幹部の神経組織を保護し、二次的な障害を最小限に抑えます。
- エダラボン 脳保護薬として使用
- グリセロール 脳浮腫の軽減に使用
- ビタミンB群 神経機能の維持に使用
- ATP製剤 エネルギー代謝改善に使用
- 神経栄養因子 神経細胞の保護に使用
神経保護薬は、フリーラジカルの除去や細胞膜の安定化、エネルギー代謝の改善などの作用を通じて、神経細胞の保護効果を発揮します。
特にエダラボンは、強力な抗酸化作用により、脳虚血後の酸化ストレスから神経細胞を保護する効果が認められています。
呼吸・循環管理
全身管理の中でも重要となる呼吸・循環管理では、医療機器を用いた継続的なモニタリングと管理が不可欠です。
| 管理項目 | 具体的な方法 |
| 呼吸管理 | 人工呼吸器による呼吸補助 |
| 循環管理 | 血圧・心拍のモニタリング |
| 栄養管理 | 経管栄養による栄養補給 |
呼吸管理においては、人工呼吸器を用いた換気サポートにより、安定した酸素供給と二酸化炭素の排出を維持します。
さらに、循環管理では、血圧や心拍数、血液の酸素飽和度などを24時間体制でモニタリングし、必要に応じて昇圧剤や降圧剤を使用します。
リハビリテーション
急性期を脱した後、段階的なリハビリテーションプログラムを開始し、患者さんの状態に合わせて徐々に訓練の内容と強度を調整していきます。
眼球運動を利用したコミュニケーション訓練からスタートし、その後、関節可動域訓練や筋力維持訓練などの身体機能訓練へと段階的に移行することが大切です。
閉じ込め症候群の治療における副作用やリスク
閉じ込め症候群の治療において、薬物療法や人工呼吸器管理などの様々な医療介入に伴う副作用やリスクを慎重に管理することが重要となりますが、それぞれの治療法には固有のリスクがあります。
薬物療法における副作用管理
薬物療法において抗凝固薬や筋弛緩薬などの使用は、出血性合併症や呼吸抑制などの深刻な副作用をもたらす可能性があるため、投与量や投与時期の調整が重要です。
血液凝固能のモニタリングを継続的に行いながら、薬物の投与量を細やかに調整することで、治療効果を最大限に引き出すことを目指しますが、同時に副作用の発現にも十分な注意を払う必要があります。
薬物療法における副作用の中でも特に注意を要するものとして、抗凝固薬による出血性合併症があり、時として生命を脅かす重大な事態に発展する危険性があるこあとから、定期的な血液検査による凝固能の評価が欠かせません。
| 薬剤分類 | 主な副作用 | 対処方法 |
| 抗凝固薬 | 出血傾向、消化管出血 | 凝固能検査による用量調整 |
| 筋弛緩薬 | 呼吸抑制、筋力低下 | 呼吸機能モニタリング |
| 降圧薬 | 血圧低下、めまい | 血圧測定による用量調整 |
人工呼吸器関連のリスク管理
人工呼吸器管理においては、気道感染症や肺炎などの感染性合併症のリスクが高まることから、徹底した感染対策と継続的な呼吸器ケアが求められ、合併症は患者様の予後に大きな影響を与えます。
定期的な気道内分泌物の吸引や、呼吸器回路の清潔管理を通じて、感染リスクの低減を図れますが、完全な予防は困難で、常に感染の兆候を注意深く観察する必要があります。
人工呼吸器関連肺炎(VAP)は、特に注意を要する合併症の一つで、予防には口腔内ケアの徹底や、体位管理、定期的な気道内圧のモニタリングなど、複数の予防的介入を組み合わせた包括的なアプローチが重要です。
栄養管理におけるリスクと対策
経管栄養や静脈栄養による栄養管理では、次のようなリスクがあります。
- 誤嚥性肺炎
- 電解質異常
- カテーテル関連血流感染症
- 消化管合併症
栄養管理における合併症予防には、定期的な血液検査による栄養状態の評価と、栄養投与計画の見直しが重要となりますが、同時に投与方法や投与速度の調整も慎重に行います。
| 栄養管理方法 | 想定されるリスク | 予防的対策 |
| 経管栄養 | 誤嚥、下痢 | 投与速度調整、体位管理 |
| 静脈栄養 | カテーテル感染 | 無菌操作の徹底 |
| 経口摂取訓練 | 窒息、誤嚥 | 嚥下機能評価 |
リハビリテーションにおける合併症予防
関節拘縮や褥瘡などの二次的合併症を予防するため、理学療法士による介入と体位変換などのケアを組み合わせたアプローチを実践しますが、予防的介入にも一定のリスクが伴います。
早期からのリハビリテーション介入により、廃用症候群の予防と二次的合併症の発生リスクを軽減することが望ましいものの、患者さんの全身状態を考慮しながら、段階的にリハビリテーションの強度を調整していく慎重なアプローチが必要です。
リハビリテーションの過程では、特に循環動態の変化や呼吸状態の悪化に注意を払い、患者さんの状態に応じた介入方法の選択と実施を行っていきます。
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
入院時の基本的な医療費
入院時の基本的な医療費には、個室差額ベッド代を除く一般病棟での入院費用が含まれます。
| 入院費用項目 | 保険適用後の自己負担額(3割負担の場合) |
| 一般病棟入院費(1日) | 5,000円~8,000円 |
| 集中治療室使用料(1日) | 15,000円~25,000円 |
| 特定集中治療室(1日) | 30,000円~45,000円 |
検査関連費用
神経学的検査や画像診断に関する費用は以下の通りです。
- MRI検査 15,000円~25,000円/回
- CT検査 8,000円~15,000円/回
- 脳波検査 4,000円~8,000円/回
- 血液検査 3,000円~6,000円/回
- 嚥下造影検査 5,000円~10,000円/回
薬物療法費用
| 薬剤分類 | 1ヶ月あたりの自己負担額(3割負担の場合) |
| 血栓溶解薬 | 50,000円~80,000円 |
| 抗凝固薬 | 3,000円~15,000円 |
| 神経保護薬 | 5,000円~20,000円 |
| 抗痙縮薬 | 3,000円~10,000円 |
リハビリテーション費用
リハビリテーションの費用は、実施する種類や頻度によって大きく変動し、標準的な理学療法では、1回あたり3,000円から5,000円程度の自己負担が発生します。
作業療法や言語療法も同様の費用水準となり、週3回から5回程度の実施が一般的です。
人工呼吸器管理費用
人工呼吸器使用時には、1日あたり8,000円から15,000円程度の追加費用がかかり、呼吸器関連の消耗品代として、月額5,000円から10,000円が必要です。
長期入院時の費用
標準的な3ヶ月の入院治療では、検査費用や薬物療法を含めて総額で80万円から150万円程度の自己負担となることが多いです。
回復期リハビリテーション病棟での入院では、1ヶ月あたり20万円から30万円程度の費用が見込まれます。
以上
Smith E, Delargy M. Locked-in syndrome. Bmj. 2005 Feb 17;330(7488):406-9.
Patterson JR, Grabois M. Locked-in syndrome: a review of 139 cases. Stroke. 1986 Jul;17(4):758-64.
Bauer G, Gerstenbrand F, Rumpl E. Varieties of the locked-in syndrome. Journal of neurology. 1979 Aug;221:77-91.
Lulé D, Zickler C, Häcker S, Bruno MA, Demertzi A, Pellas F, Laureys S, Kübler A. Life can be worth living in locked-in syndrome. Progress in brain research. 2009 Jan 1;177:339-51.
Laureys S, Pellas F, Van Eeckhout P, Ghorbel S, Schnakers C, Perrin F, Berre J, Faymonville ME, Pantke KH, Damas F, Lamy M. The locked-in syndrome: what is it like to be conscious but paralyzed and voiceless?. Progress in brain research. 2005 Jan 1;150:495-611.
León-Carrión J, Eeckhout PV, Dominguez-Morales MD, Pérez-Santamaría FJ. Survey: The locked-in syndrome: a syndrome looking for a therapy. Brain injury. 2002 Jan 1;16(7):571-82.
Halan T, Ortiz JF, Reddy D, Altamimi A, Ajibowo AO, Fabara SP. Locked-In syndrome: a systematic review of long-term management and prognosis. Cureus. 2021 Jul;13(7).
Das JM, Anosike K, Asuncion RM. Locked-in syndrome. InStatPearls [Internet] 2023 Jul 24. StatPearls Publishing.
Schnetzer L, McCoy M, Bergmann J, Kunz A, Leis S, Trinka E. Locked-in syndrome revisited. Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 2023 Mar;16:17562864231160873.
Feldman MH. Physiological observations in a chronic case of “locked‐in” syndrome. Neurology. 1971 May;21(5):459-.
\