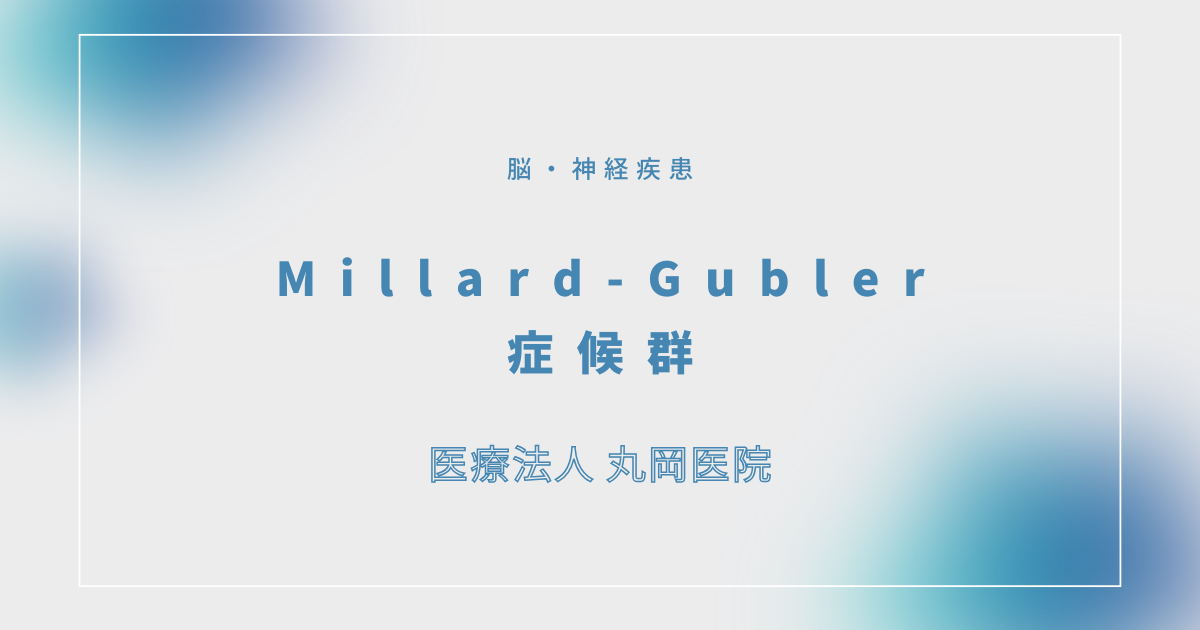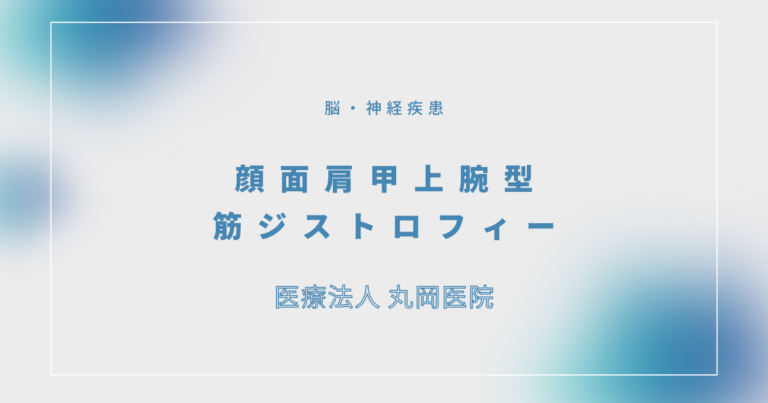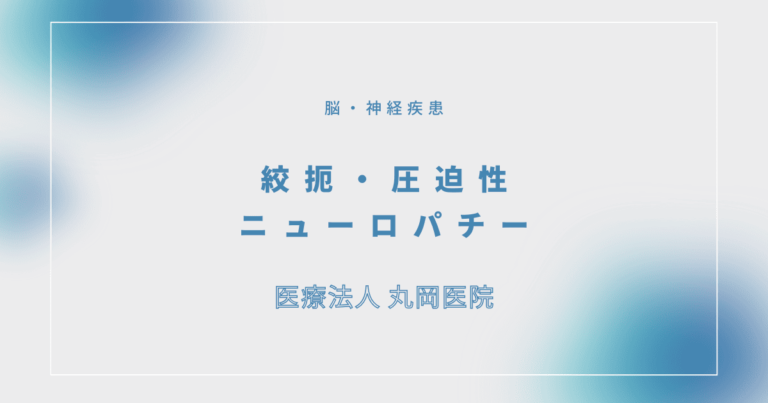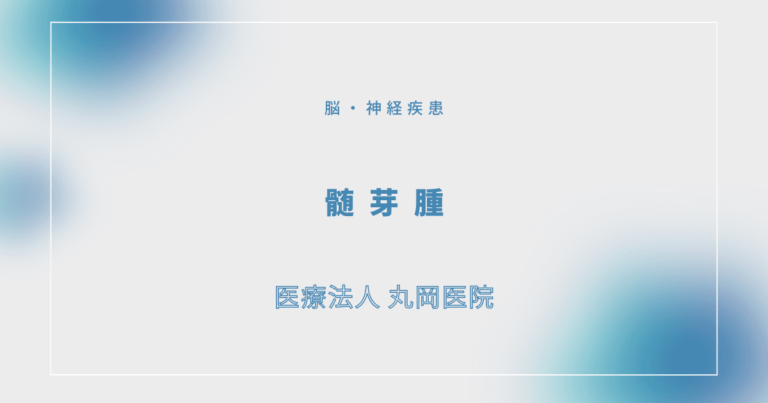Millard-Gubler症候群(Millard-Gubler syndrome)とは、脳幹部にある橋という重要な神経組織に障害が生じることで発症する神経学的症候群です。
この症候群の特徴的な症状として、脳神経の障害による片側の顔面神経麻痺と、錐体路障害による反対側の上下肢の運動麻痺が出現します。
神経内科医や脳神経外科医による専門的な診察と、理学療法士による機能回復訓練を組み合わせた包括的なアプローチが重要です。
Millard-Gubler症候群の主な症状
Millard-Gubler症候群における主な症状は、脳幹部の橋腹側病変から起きる同側の外転神経麻痺および顔面神経麻痺、対側の片麻痺です。
神経学的徴候の特徴
Millard-Gubler症候群の神経学的徴候は、脳幹部における解剖学的な構造により、複数の脳神経が同時に障害されることで特徴的な症状パターンを呈することです。
中脳から延髄にかけての脳幹部における神経走行は複雑で、この部位における病変は、神経核や神経線維の機能低下を起こすことで、患者さんの身体に神経症状として現れます。
患者さんの神経学的所見は、外転神経麻痺による眼球運動の制限と顔面神経麻痺による表情筋の機能不全が病変と同側に出現するという特徴的な組み合わせを認め、診断の際の貴重な手がかりです。
| 障害部位 | 主な神経症状 |
| 外転神経 | 外側への眼球運動制限 |
| 顔面神経 | 表情筋の麻痺、味覚障害 |
| 皮質脊髄路 | 対側の上下肢の運動麻痺 |
神経症状の組み合わせじゃ、橋の腹側部における病変が、同部位を通過する神経線維束を障害することで発症するというメカニズムが明らかです。
外転神経麻痺の臨床像
外転神経麻痺による症状は、眼球の外側への動きが著しく制限されることにより、複視や斜視などの視覚障害が現れることがあり、患者さんの視覚機能に大きな影響を及ぼします。
眼球運動の制限は、側方視において顕著となることが多く、患者さんの視覚機能に関する詳細な評価が必要な症状です。
外転神経の機能障害により、眼球を外側に向ける外直筋の筋力低下が生じることで、内側への眼位ずれを引き起こすという一連の病態生理学的な変化が特徴です。
顔面神経麻痺の様相
顔面神経麻痺は、表情筋の機能不全として現れ、以下のような特徴的な症状を示します。
- 眉毛の挙上困難
- 額のしわ寄せ不全
- 眼輪筋の機能低下による閉眼障害
- 口角の下垂
- 口笛や膨らまし運動の障害
| 顔面表情の変化 | 随伴症状 |
| 非対称性の表情 | 流涙過多 |
| 口角下垂 | 構音障害 |
| 閉眼不全 | 味覚異常 |
顔面神経麻痺による表情筋の機能不全は、患者さんの表情による感情表現やコミュニケーションに影響を与えるだけではなく、味覚や涙腺分泌にも影響を及ぼすことがあります。
対側性片麻痺の特徴
皮質脊髄路の障害により、病変の反対側に上下肢の運動麻痺が現れることはMillard-Gubler症候群の典型的な症状です。
運動麻痺の程度については、軽度の筋力低下から重度の麻痺まで幅広い症状を呈し、患者さんの神経学的状態を詳細に評価することで、病変の範囲や程度を推測する手がかりとなります。
対側性の片麻痺は、上肢および下肢の両方に影響を及ぼすことが特徴的で、運動機能の低下や筋力の減弱として現れることから、筋力評価と継続的な観察が必要です。
Millard-Gubler症候群の原因
脳・神経疾患の一種であるMillard-Gubler症候群は、脳幹部の橋における顔面神経核および錐体路に対して、血管障害や腫瘍性病変などの様々な病的変化が生じることによって起こります。
基本的な解剖学的構造と病変部位
脳幹部の橋には、人体の様々な機能を制御する上で不可欠な神経核と神経線維が密集して存在しており、顔面の表情筋を支配する顔面神経核と、四肢および体幹の随意運動を制御する錐体路という2つの重要な神経構造が非常に近接しています。
それぞれが独立して機能しながらも相互に関連し合いながら、人体の精密な運動制御システムを構成しているため、この部位における病変は複数の神経症状を同時に引き起こす結果となります。
| 神経構造 | 主な機能 | 解剖学的特徴 |
| 顔面神経核 | 表情筋の運動制御 | 橋部内側に存在 |
| 錐体路 | 四肢・体幹の随意運動制御 | 橋部を縦走 |
血管性病変による発症機序
橋部における血管障害は、Millard-Gubler症候群の発症原因として最も高い頻度で見られます。
脳底動脈やその分枝である傍正中枝における血流障害は、局所的な虚血や梗塞を起こすことで神経組織に重大な影響を及ぼすのです。
血管性病変による神経障害は、急性期には虚血性変化や出血による直接的な組織障害として現れ、その後の慢性期には神経組織の変性や瘢痕化といった二次的な変化へと進展していきます。
| 血管障害の種類 | 主な原因 | 病態生理学的特徴 |
| 脳梗塞 | 動脈硬化、血栓形成 | 急性の虚血性変化 |
| 出血性病変 | 高血圧性変化、血管奇形 | 圧迫性・破壊性変化 |
腫瘍性病変と圧迫性病変
橋部における腫瘍性病変は、発生部位や増大速度によって様々な神経症状を起こす可能性があり、緩徐に増大する良性腫瘍であっても、狭い空間である橋部において重要な神経構造を圧迫することで、深刻な神経機能障害が生じます。
腫瘍による神経構造の圧迫や浸潤は、以下のような複数のメカニズムを介して神経障害を起こすことが明らかになってきました。
- 腫瘍組織による直接的な神経組織の圧迫と変形
- 腫瘍の増大に伴う局所の微小循環障害と虚血性変化
- 腫瘍周囲の浮腫性変化による二次的な圧迫効果
- 腫瘍に関連する炎症性変化の周囲組織への波及
その他の発症要因
炎症性疾患や脱髄性疾患による神経障害は、免疫学的な機序や代謝異常を介して橋部の神経構造に影響を与え、時には不可逆的な組織障害を起こします。
外傷性の病変や感染性病変なども重要な発症要因で、急性期には炎症性変化や浮腫性変化が強く現れる一方で、慢性期には組織の瘢痕化や変性といった器質的変化が前面に出てくることが特徴的です。
診察(検査)と診断
Millard-Gubler症候群の診断では、神経学的診察による臨床所見の詳細な評価と、画像診断技術を用いた病変の直接的な確認を組み合わせることで、より正確な病態把握を目指します。
基本的な神経学的診察
神経学的診察においては、脳神経機能、運動機能、感覚機能などについて、系統的かつ詳細な観察を行うことから始まり、特に顔面神経領域と錐体路症状に関する慎重な評価が大切です。
診察時に患者さんの表情筋の動きを注意深く観察しながら、同時に四肢の運動機能についても詳細なチェックを行い、両者の関係性について総合的な判断を下します。
| 診察項目 | 観察のポイント | 具体的な手法 |
| 脳神経機能 | 顔面筋力、眼球運動 | 表情運動の左右差確認 |
| 運動機能 | 筋力、腱反射、協調運動 | 徒手筋力テスト実施 |
| 感覚機能 | 表在感覚、深部感覚 | 触覚・振動覚の評価 |
画像診断による評価
MRIやCTなどの精密な画像検査を用いることで、橋部における病変の存在や範囲を詳細に確認でき、MRI検査では病変の性状や進展範囲についてより詳細な情報を得ることが重要です。
画像診断によって得られる情報は、次のような観点から慎重に分析を進めていく必要があります。
- 病変の正確な解剖学的位置と三次元的な広がり
- 周囲の脳組織への圧迫や浸潤の程度
- 血管性変化の有無と血管走行との関係
- 腫瘍性病変の場合の性状や造影効果の特徴
補助的検査
血液検査や髄液検査などの補助的検査は、病態の本質を理解する上で欠かせない情報を提供し、炎症性疾患や自己免疫性疾患が疑われる際には、さらなる検査項目が必要です。
血液検査では一般的な炎症マーカーに加えて、自己抗体の測定なども併せて実施することで、より包括的な病態評価を進められます。
| 検査項目 | 主な検査内容 | 臨床的意義 |
| 血液検査 | 炎症マーカー、自己抗体 | 全身性疾患の評価 |
| 髄液検査 | 細胞数、蛋白、糖 | 中枢神経感染症の除外 |
経時的観察
診察所見や各種検査結果の経時的な変化を注意深く追跡することは、病態の進行状況を正確に把握し、より効果的な治療方針を決定していく上で極めて大切な過程です。
画像所見の変化と臨床症状の推移を詳細に記録し、定期的な再評価を行うことで、病態の進行や改善の程度をより正確に判断できます。
Millard-Gubler症候群の治療法と処方薬、治療期間
Millard-Gubler症候群の治療は、ステロイド薬による急性期の炎症抑制治療を基本として、リハビリテーション療法と神経保護薬の併用します。
薬物療法の基本方針
急性期における炎症抑制と神経保護を目的とした治療には、メチルプレドニゾロンを代表とするステロイド薬の投与が中心で、炎症を抑える働きとともに神経組織の保護効果も期待できます。
炎症反応の抑制効果を十分に引き出すため、初期投与量を高用量に設定し、症状の推移に応じて段階的に減量し、4週間から8週間かけて慎重に投与量を調整していくことが大切です。
神経保護作用を有するエダラボンの投与により、脳内で発生する有害な活性酸素を除去し、二次的な神経障害の予防を図ることができ、発症後できるだけ早期から2週間から4週間程度投与することで高い効果が得られます。
| 薬剤分類 | 投与目的と期間 |
| ステロイド薬 | 急性期の炎症抑制、4-8週間 |
| 神経保護薬 | 神経細胞保護、2-4週間 |
| ビタミンB12製剤 | 神経再生補助、3-6ヶ月 |
メチルプレドニゾロンの投与量は体重あたり30mgから開始し、症状の改善に応じて2週間ごとに漸減していくことで、急性期の炎症を効果的に抑制できます。
リハビリテーション療法
運動機能回復のための理学療法
- 関節可動域訓練
- 筋力増強運動
- バランス訓練
- 歩行訓練
- 日常生活動作訓練
リハビリテーション療法は、薬物療法による炎症抑制効果が現れ始める時期から開始し、段階的に運動負荷を増やしていくことで、効果的な機能回復をすることが目標です。
理学療法士による専門的な指導のもと、各訓練項目を正しい強度で実施することで、運動機能の回復を促進でき、発症早期からのリハビリテーション介入が機能予後の改善に大きく寄与します。
複合的治療アプローチ
薬物療法とリハビリテーション療法の組み合わせにより、相乗効果を引き出すことを目指し、それぞれの治療効果を最大限に高められます。
理学療法と作業療法の併用により、運動機能と日常生活動作の両面からの機能回復を図ることが不可欠で、急性期から回復期にかけての集中的なリハビリテーションが効果的です。
| 治療法 | 実施時期と頻度 |
| 理学療法 | 急性期から開始、週3-5回 |
| 作業療法 | 回復期から開始、週2-3回 |
| 言語療法 | 必要に応じて追加、週1-2回 |
治療期間と経過
治療開始から6ヶ月程度を目安として、症状の改善度合いに応じて治療内容を調整していく中で、薬物療法の投与量や種類、リハビリテーションの内容や頻度を細かく見直していきます。
リハビリテーション期間は通常1年程度を要し、神経機能の回復状況や全身状態を考慮しながら、個々の状況に合わせて治療期間を設定することで最大限の治療効果を引き出すことが可能です。
Millard-Gubler症候群の治療における副作用やリスク
Millard-Gubler症候群の治療過程においては、薬物療法やリハビリテーション、各種検査や処置に関連する多様な副作用やリスクが発生する可能性があります。
薬物療法における副作用
ステロイド薬や抗凝固薬などの投与に際しては、薬剤の特性に応じた複数の副作用に細心の注意を払い、特に長期投与を要する場合には、定期的な血液検査や画像検査によるモニタリングが欠かせません。
免疫抑制作用を持つステロイド薬の使用では、感染症のリスクが高まることから、投与開始前の感染症スクリーニングと、投与中の感染予防対策を徹底することが重要です。
| 使用薬剤 | 主な副作用 | モニタリング項目 |
| ステロイド薬 | 胃潰瘍、骨粗鬆症 | 定期的な内視鏡検査、骨密度測定 |
| 抗凝固薬 | 出血傾向、肝機能障害 | 凝固能検査、肝機能検査 |
リハビリテーションに関連するリスク
リハビリテーションの実施には、患者さんの全身状態や神経症状の程度を十分に考慮しながら、いくつかのリスクに対して細心の注意を払いながら進めていきます。
- 過度な運動による筋疲労と神経症状の悪化
- 関節可動域訓練時の痛みや組織損傷
- バランス練習時の転倒と二次的な外傷
- 嚥下訓練時の誤嚥と呼吸器合併症
画像検査に伴うリスク
MRIやCTなどの画像検査実施時には、造影剤使用に関連する様々な合併症に注意が必要であり、腎機能障害やアレルギー歴のある患者さんでは、代替検査の検討や予防的な対策を講じることが大切です。
造影剤を使用する検査前には、腎機能や甲状腺機能の評価を行い、補液などの予防措置を実施することで、合併症のリスクを最小限に抑えられます。
| 検査種類 | 想定されるリスク | 予防的対策 |
| MRI造影検査 | 腎機能障害、アレルギー | 腎機能評価、補液 |
| CT造影検査 | 造影剤腎症、ショック | アレルギー歴確認、前投薬 |
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
入院時の治療費について
入院期間中の基本的な治療費は、病室の種類や入院期間によって変動します。
一般病床での入院費用は、1日あたり18,000円から24,000円程度です。
| 入院費用項目 | 3割負担時の概算費用(月額) |
| 一般病床入院基本料 | 15万円~18万円 |
| 特別病室利用料 | 追加5万円~10万円 |
| 食事療養費 | 約1.5万円 |
| MRI検査 | 3万円~4万円/回 |
薬物療法に関わる費用
ステロイド薬による治療費は、使用する薬剤の種類や投与量により異なります。
メチルプレドニゾロンの投与にかかる費用は、1クール(4週間)あたり2万円から3万円程度で、神経保護薬であるエダラボンの投与費用は、2週間の投与で4万円から5万円です。
リハビリテーション療法の費用
リハビリテーションには以下のような費用が発生します。
- 理学療法 1回あたり3,500円~4,500円
- 作業療法 1回あたり3,000円~4,000円
- 言語療法 1回あたり3,000円~4,000円
- 運動器具使用料 1回500円~1,000円
長期的な治療費の内訳
外来診療への移行後も、定期的な診察とリハビリテーションが継続します。
| 治療段階 | 期間と費用 |
| 急性期入院 | 2~4週間 60万円~80万円 |
| 回復期入院 | 8~12週間 120万円~180万円 |
| 外来リハビリ | 週3回 4~5万円/月 |
薬剤投与スケジュールと費用
薬物療法は症状の推移に応じて投与量を調整していきます。
神経保護薬とビタミンがB12製剤の併用により、月額で6万円から8万円程度が必要です。
以上
Silverman IE, Liu GT, Volpe NJ, Galetta SL. The crossed paralyses: the original brain-stem syndromes of Millard-Gubler, Foville, Weber, and Raymond-Cestan. Archives of Neurology. 1995 Jun 1;52(6):635-8.
Sakuru R, Elnahry AG, Lui F, Bollu PC. Millard-Gubler Syndrome. InStatPearls [Internet] 2024 Feb 25. StatPearls Publishing.
Casamajor L. A case of Millard-Gubler syndrome. The Journal of Nervous and Mental Disease. 1916 Oct 1;44(4):354-6.
Abdallah A, Asitürk M, Abdallah BG, Emel E. Millard-Gubler Syndrome: A Case Report. Journal of Nervous System Surgery. 2015 Dec 30;5(2):10-4.
Onbas O, Kantarci M, Alper F, Karaca L, Okur A. Millard–Gubler syndrome: MR findings. Neuroradiology. 2005 Jan;47:35-7.
Chakraborty U, Santra A, Pandit A, Dubey S, Chandra A. Space occupying lesion presenting as Millard-Gubler syndrome. BMJ Case Reports CP. 2022 Apr 1;15(4):e248590.
Vemana HR, Ahmed N, Chikkala BA, Gogulamanda RL, Kandregula P, Nalli M, Yanamadala PK. A Rare Neurological Sequela: Pontine Infarct Conducing to Millard-gubler Syndrome. International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports. 2023 Nov 15;16(4):69-75.
Matlis A, Kleinman Y, Korn-Lubetzki I. Millard-Gubler syndrome. AJNR: American Journal of Neuroradiology. 1994 Jan;15(1):179.
Yasuda Y, Matsuda I, Sakagami T, Kobayashi H, Kameyama M. Pontine infarction with pure Millard-Gubler syndrome: precise localization with magnetic resonance imaging. European neurology. 1993;33(4):333-4.
Kesikburun S, Safaz I, Alaca R. Pontine cavernoma hemorrhage leading to Millard-Gubler syndrome. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2011 Mar 1;90(3):263.
Patil AR, Samal S, Sasun AR. Harnessing Neuroplasticity: A Case Report on Physiotherapy Rehabilitation for Millard-Gubler Syndrome. Cureus. 2024 Mar;16(3).