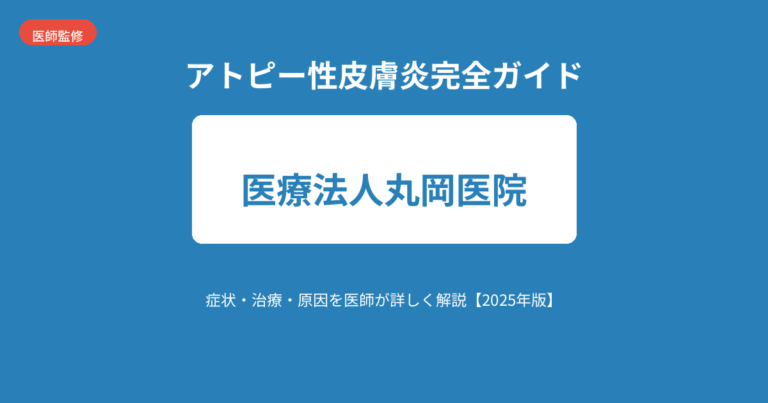目次[]
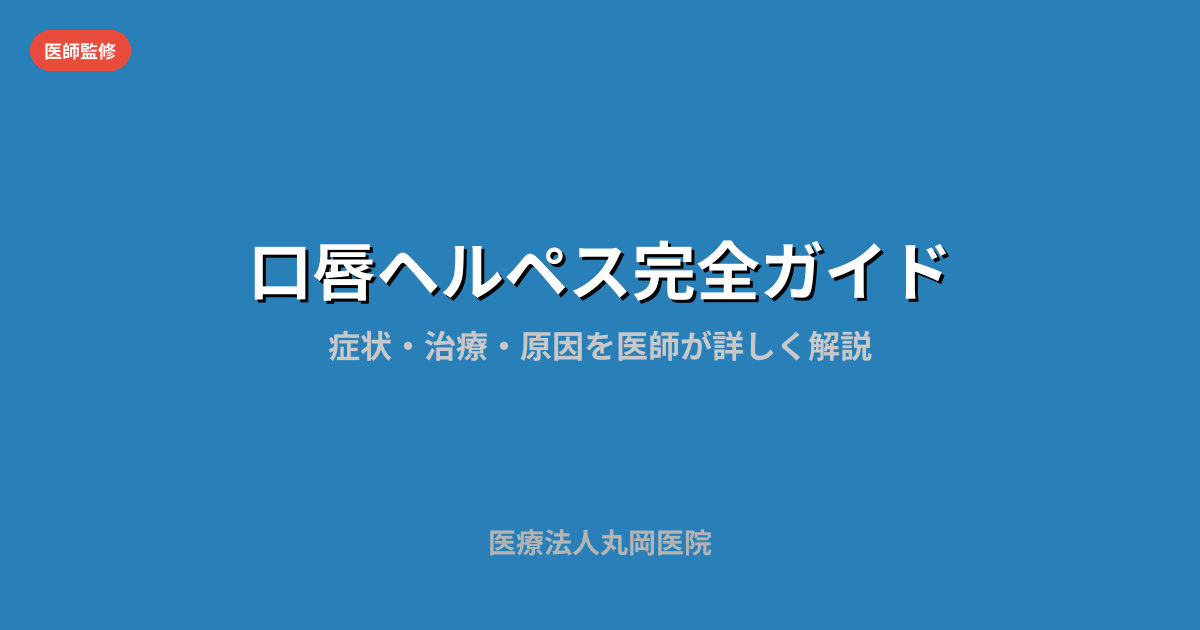
口唇ヘルペスの症状・治療・予防法|保険適用治療と再発防止策を解説
唇の周りに小さな水ぶくれができて、ピリピリとした痛みやかゆみに悩まされていませんか?そんな症状は口唇ヘルペスかもしれません。
口唇ヘルペスは多くの方が経験する身近な疾患ですが、適切な治療により症状を早期に改善し、再発を予防することが可能です。疲労やストレス、風邪などで免疫力が低下した時に現れやすいこの症状について、正しい知識を持つことが大切です。
この記事では、口唇ヘルペスの症状の見分け方から効果的な治療法、日常生活でできる予防策まで、患者さんからよく寄せられる疑問にお答えしながら詳しく解説いたします。保険適用の治療法についても具体的にご紹介しますので、適切な対処で症状の改善を目指していきましょう。