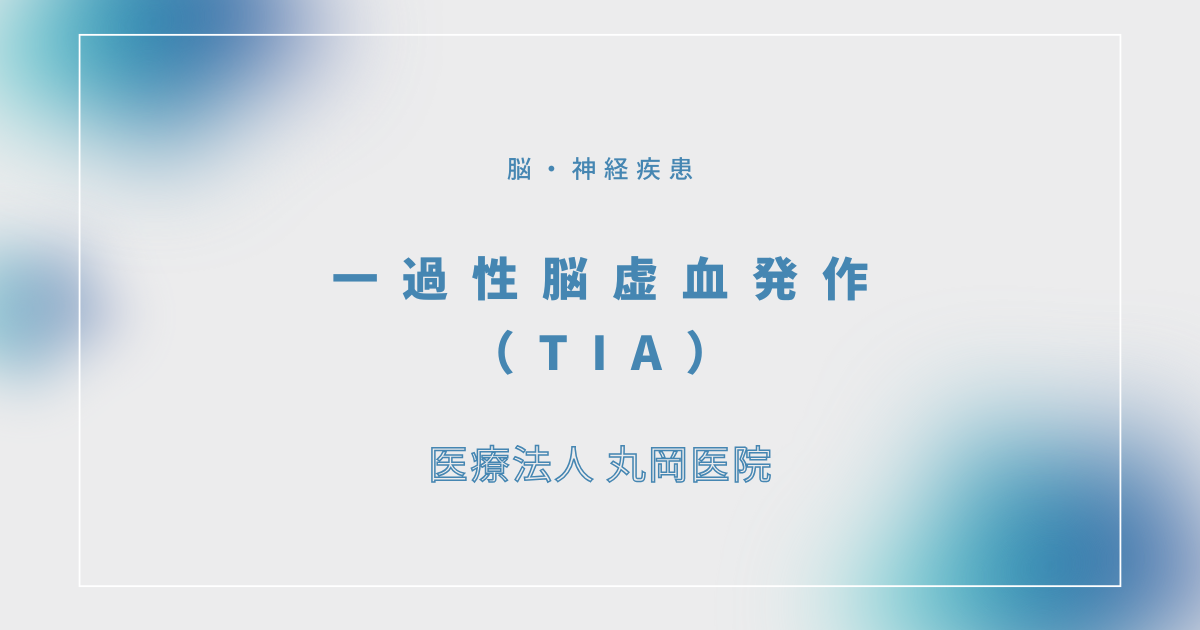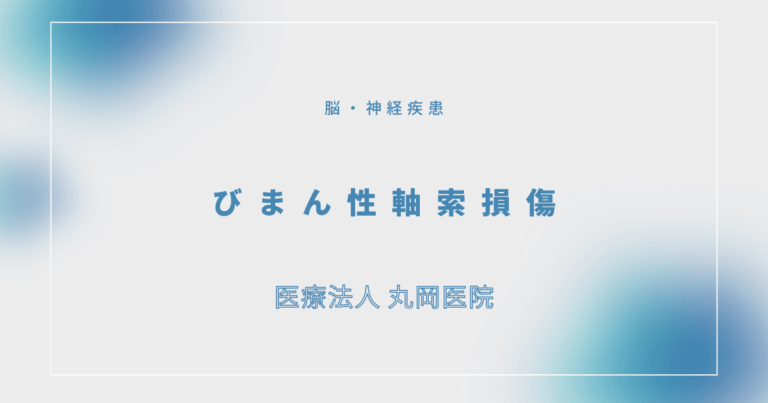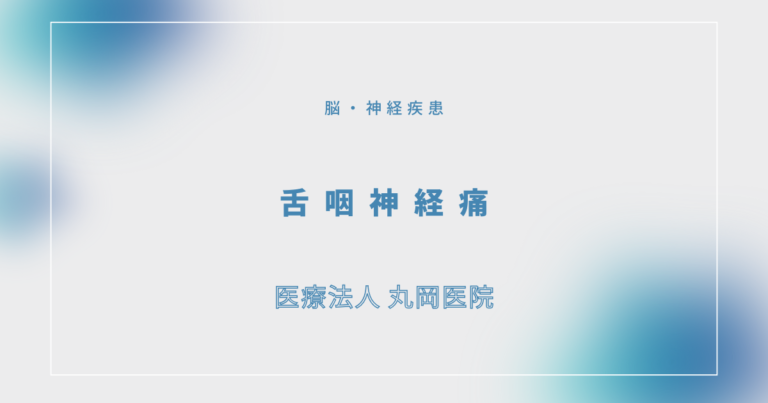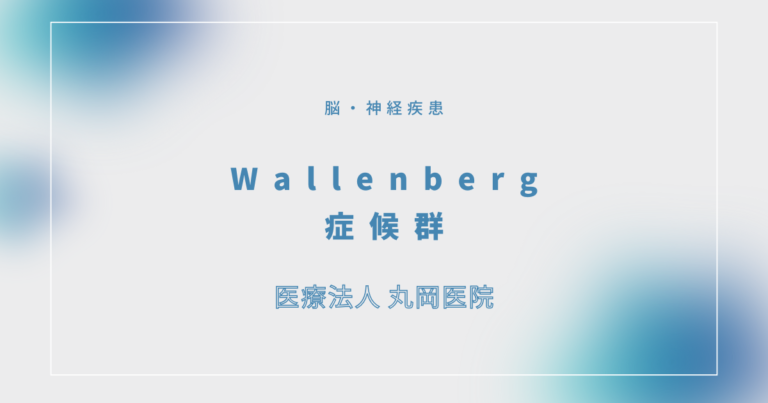一過性脳虚血発作(TIA)(Transient ischemic attack)とは、脳の血管が一時的に詰まることで、脳の一部への血流が途絶え、神経症状が出現する状態です。
この疾患では、手足の麻痺や言葉の障害、視野が欠けるなどの症状が突然現れますが、症状は24時間以内に自然と消失していきます。
ただし、一過性脳虚血発作は将来の重大な脳卒中につながる可能性が高い警告サインとして認識することが重要です。
一過性脳虚血発作(TIA)の主な症状
一過性脳虚血発作(TIA)における症状は、突然の片側の手足の脱力や感覚障害、言語障害、視野障害などが一時的に出現し、24時間以内に完全に回復するものです。
一過性脳虚血発作の主要な神経症状
一過性脳虚血発作において神経症状が生じる際には、脳の血管が一時的に詰まることによって、その血管が担当している脳の部分の機能が一時的に低下することで多彩な症状が引き起こされます。
神経症状の持続時間は数分から数時間程度で、症状の程度には個人差があるものの、多くの患者さんが症状の出現に強い不安を感じることから、医療機関への早期受診を行ってください。
虚血が起きた脳の部位によって異なる症状が見られるので、症状の種類や性質を正確に把握することで、脳のどの部分に血流障害が生じているのかを推測することが不可欠です。
| 症状の分類 | 具体的な症状の内容 |
|---|---|
| 運動障害 | 片側の手足の脱力や麻痺、歩行困難、ふらつき |
| 感覚障害 | 片側の手足のしびれ、触覚低下、温度感覚の鈍化 |
| 言語障害 | 言葉が出にくい、他者の言葉が理解しづらい |
| 視覚障害 | 片目の視力低下、視野の一部が見えにくい |
発作時に現れる特徴的な症状パターン
一過性脳虚血発作の症状は、脳の血管の支配領域によって特徴的なパターンを示します。
内頸動脈系の血管に問題が生じた場合には、反対側の手足の脱力やしびれ、言語障害などの症状が現れることが多く、症状の組み合わせを理解することで、血管病変の位置をより正確に推測できます。
椎骨脳底動脈系の血管に異常がある場合には、めまいやふらつき、複視(物が二重に見える)、嚥下障害などの症状が現れることが多く、症状が複合的に現れることが診断の手がかりです。
- 顔面の症状 顔の片側の脱力、しびれ、歪み
- 構音障害 ろれつが回りにくい、呂律が不明瞭になる
- 視覚異常 突然の視力低下、視野の一部が欠ける
- 平衡感覚の障害 めまい、ふらつき、立位保持が困難
- 嚥下障害 飲み込みにくさ、むせやすさ
症状は、一過性脳虚血発作の代表的な症状として広く認識されており、上記の症状の有無を詳しく確認することで、より正確な診断につなげます。
症状の時間的経過と特性
一過性脳虚血発作における症状の持続時間は、24時間以内に完全に消失することが重要な特徴です。
は症状の持続時間が1時間未満であることが多く、特に発作後の数分から数十分の間に症状が消失していくパターンがよく見られます。
| 症状の持続時間 | 臨床的な意義 |
|---|---|
| 数分以内 | 最も一般的な持続時間であり、軽症例が多い |
| 1時間以内 | 中等度の症例が多く、詳細な検査が必要 |
| 1〜24時間 | 比較的重症例が多く、厳重な経過観察が求められる |
症状の観察と記録のポイント
一過性脳虚血発作の症状を正確に把握するためには、発作が起きた時刻や症状の詳細な内容、症状の持続時間などを具体的に記録することが大切です。
診察時には、症状の発現時刻、持続時間、症状の性質や程度について、できるだけ詳しい情報を伝えることで、より正確な診断や病態の理解につながります。
症状の記録には、動画撮影や音声録音などのデジタル機器を活用することも有効で、特に言語障害や顔面の症状が出現した際には、貴重な情報源です。
一過性脳虚血発作(TIA)の原因
一過性脳虚血発作の主たる原因は、動脈硬化や心臓からの血栓、頸動脈の狭窄などにより、脳血管が一時的に閉塞することで起こる脳血流の低下です。
血管病変による発症メカニズム
脳血管の動脈硬化は加齢とともに進行していく自然な現象ですが、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病があることで、血管壁の損傷や狭窄がより早期から進行します。
血管内皮細胞の機能低下により、血管壁への脂質沈着や炎症反応が促進され、これらの変化が血栓形成を引き起こす土台となることが、解明されてきました。
| 血管病変の種類 | 病態の特徴 |
|---|---|
| アテローム硬化 | 血管内膜への脂質沈着と炎症による血管壁の肥厚 |
| 血管壁の石灰化 | カルシウム沈着による血管の弾性低下と硬化 |
| 微小血管病変 | 細動脈の変性による血流障害と組織障害 |
心臓由来の塞栓症
不整脈、特に心房細動を有する患者さんでは、心臓内で形成された血栓が脳血管を一時的に閉塞することで、一過性脳虚血発作を引き起こします。
ただし、心臓内で形成された血栓は、血流に乗って脳血管まで到達し、血管径が細くなる部分で一時的な閉塞を引き起こすものの、血流の力や生体の持つ血栓溶解能力により再開通することで、一過性の症状として現れることが多いです。
- 心房細動による血流の停滞
- 心臓弁膜症による血流異常
- 心筋梗塞後の壁在血栓
- 心内膜炎による疣腫形成
- 心房中隔欠損症による奇異性塞栓
心臓由来の問題は、脳血管系に直接的な影響を及ぼし、一過性脳虚血発作の発症リスクを著しく高める要因になります。
頸動脈病変の影響
頸動脈の動脈硬化性病変、特にプラーク(粥腫)の形成は、一過性脳虚血発作の重要な原因の一つです。
不安定なプラークが破綻することで、内容物が血流に流出し、より末梢の脳血管を閉塞させます。
| プラークの性状 | 血管イベントのリスク |
|---|---|
| 脂質に富む軟性プラーク | 破綻しやすく高リスク |
| 線維性の安定プラーク | 比較的安定で低リスク |
| 石灰化プラーク | 破綻しにくいが血流障害の原因 |
その他の血管病変
血管炎や血液凝固異常、血液粘稠度の上昇なども、一過性脳虚血発作の原因となることが様々な研究から示されており、特に若年者での発症では、これらの要因を念頭に置いた精査が必要です。
全身性の炎症性疾患に伴う血管炎では、血管壁の炎症により血栓形成が促進されるとともに、血管の狭窄や閉塞が起こることで、脳血流が障害されるメカニズムが解明されています。
血液凝固系の異常を持つ患者さんでは、過剰な凝固能により血栓が形成されやすい状態となり一過性脳虚血発作の発症につながることが報告されています。
診察(検査)と診断
一過性脳虚血発作(TIA)の診断では、詳細な問診による臨床診断と画像検査技術を用いた確定診断を組み合わせることで、症状の経過や神経学的所見を総合的に判断します。
診察の基本と問診のポイント
問診においては、発症時の具体的な状況や症状の持続時間、さらには既往歴や日常的な生活習慣など、患者さんやご家族からの詳細な情報収集を行うことが、診断の第一歩です。
神経学的診察では、意識状態の評価から始まり、瞳孔反射や運動機能、感覚機能、さらには言語機能に至るまで、脳の様々な機能を複数の観点から慎重に評価していくことで、異常の有無や程度を明確にしていきます。
| 問診項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 発症状況 | 発症時刻、活動内容、前駆症状 |
| 症状経過 | 持続時間、回復過程、再発有無 |
| 危険因子 | 高血圧、糖尿病、喫煙歴、家族歴 |
神経学的検査の実際
神経内科専門医は、綿密な神経学的検査を通じて、脳の各部位における機能の状態を詳細に確認し、微細な異常の発見にも努めながら、総合的な神経機能の評価を実施します。
運動機能検査においては、顔面や四肢の筋力低下の程度を細かくチェックするとともに、協調運動障害の有無についても確認を行い、他の検査所見と組み合わせて総合的な判断を行います。
| 検査項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 運動機能 | 筋力、協調性、反射、歩行状態 |
| 感覚機能 | 触覚、痛覚、温度覚、位置覚 |
| 高次機能 | 言語、記憶、認知、計算能力 |
画像診断の種類と特徴
画像検査は脳血管の状態や脳組織の変化を視覚的に捉えることを可能にし、診断精度の向上に大きく貢献する不可欠な検査手段です。
主な画像検査の特徴
- MRI検査 血管の狭窄や閉塞を詳細に描出
- MRA検査 脳血管の3次元的な評価が可能
- CT検査 出血性病変の除外診断に有用
- 頸動脈エコー検査 頸部血管の状態を簡便に確認
血液検査と心機能評価
血液検査では凝固系や代謝系の異常を広範囲にわたって確認し、同時に心電図検査やホルター心電図検査による不整脈の有無の評価も併せて実施することが大切です。
心臓超音波検査は、心原性塞栓症のリスク評価において特に重要で、心腔内血栓の有無や心機能の詳細な評価を通じて、より正確な診断と予後予測に役立てます。
生化学検査や凝固系検査から得られる様々なデータは、一過性脳虚血発作の原因となっている可能性のある基礎疾患の特定に役立ち、その後の治療方針の決定にも重要な指標です。
| 検査種類 | 検査目的 |
|---|---|
| 血液凝固検査 | 血栓形成リスクの評価 |
| 脂質代謝検査 | 動脈硬化リスクの判定 |
| 糖尿病検査 | 血糖コントロール状態の把握 |
一過性脳虚血発作(TIA)の治療法と処方薬、治療期間
一過性脳虚血発作の治療は、抗血小板薬や抗凝固薬による血栓予防を中心とした薬物療法を基本として、外科的治療を組み合わせながら、再発防止に向けた長期的な治療を継続します。
抗血小板薬による血栓予防治療
抗血小板薬は血小板の働きを抑制することで血栓形成を予防する薬剤で、一過性脳虚血発作の治療における基本的な薬物療法です。
アスピリンは血小板凝集抑制作用を持つ代表的な抗血小板薬で、発症後できるだけ早期から投与を開始することで、脳梗塞への進展を抑制する効果が期待できます。
| 抗血小板薬 | 作用機序と特徴 |
|---|---|
| アスピリン | シクロオキシゲナーゼを阻害し、血小板凝集を抑制 |
| クロピドグレル | ADP受容体を阻害し、血小板活性化を抑制 |
| シロスタゾール | ホスホジエステラーゼを阻害し、血管拡張作用も有する |
抗凝固薬による血栓形成抑制
心房細動を有する患者さんに対しては、心腔内での血栓形成を予防するために、ワルファリンや直接経口抗凝固薬(DOAC)による抗凝固療法が実施されることが多いです。
直接経口抗凝固薬は、従来のワルファリンと比較して食事制限が少なく、定期的な血液検査の頻度も少なくて済むという利点があることから、第一選択薬として使用されることが増えています。
- ダビガトラン(トロンビン阻害薬)
- リバーロキサバン(第Xa因子阻害薬)
- アピキサバン(第Xa因子阻害薬)
- エドキサバン(第Xa因子阻害薬)
抗凝固薬は、それぞれ独自の作用機序を持ち、患者さんの状態や併存疾患に応じて使い分けることで、より効果的な治療を実現できます。
外科的治療の選択肢
頸動脈狭窄症による一過性脳虚血発作に対しては、狭窄部位の血行再建を目的とした手術療法が不可欠な治療選択肢です。
| 手術方法 | 手術の特徴と適応 |
|---|---|
| 頸動脈内膜剥離術 | 動脈壁のプラークを直接除去する外科手術 |
| 頸動脈ステント留置術 | カテーテルを用いた低侵襲治療 |
| バイパス手術 | 狭窄部位を迂回する血行再建術 |
治療期間と経過モニタリング
一過性脳虚血発作に対する薬物療法は、長期的な継続が重要となりますが、投薬内容や投与量は患者さんの状態に応じて適宜調整していく必要があります。
抗血小板薬による治療は、特別な事情がない限り、長期的な継続が基本となり、出血性の合併症リスクについても慎重に評価しながら投薬を継続していくことが標準的な対応です。
抗凝固薬による治療においても、心房細動などの基礎疾患が持続する限り、薬物療法の継続が必要となることが多く、定期的な血液検査や心機能評価を行いながら、投薬量の微調整を行います。
一過性脳虚血発作(TIA)の治療における副作用やリスク
一過性脳虚血発作の治療では、抗血小板薬や抗凝固薬による出血性合併症、手術治療における血管損傷や感染症など、様々な副作用やリスクがあります。
抗血小板薬による副作用
抗血小板薬による治療では、血小板機能抑制作用に起因する出血傾向が主たる副作用として挙げられ、消化管出血や皮下出血などの出血性合併症に十分な注意が必要です。
長期的な抗血小板薬の使用に伴い、胃粘膜障害から消化性潰瘍を起こすことがあり、特に高齢者や消化器疾患の既往がある患者さんでは、胃酸分泌抑制薬の併用を検討します。
| 抗血小板薬 | 主な副作用 |
|---|---|
| アスピリン | 消化管出血、胃粘膜障害、気管支喘息 |
| クロピドグレル | 皮下出血、肝機能障害、白血球減少 |
| シロスタゾール | 頭痛、動悸、下痢、めまい |
抗凝固薬関連の合併症
抗凝固薬による治療では、出血のリスクと血栓予防の効果のバランスを慎重に考慮しながら、投与量の調整を行います。
ワルファリンによる治療では、ビタミンK拮抗作用により、予期せぬ出血や血腫形成のリスクがあり、特に頭蓋内出血や消化管出血などの重大な出血性合併症には細心の注が必要です。
- 頭蓋内出血のリスク増加
- 消化管出血の発生率上昇
- 手術時の出血量増加
- 皮下出血や紫斑の形成
- 歯科治療時の出血傾向
出血性合併症は、抗凝固薬の投与量や患者さんの年齢、併存疾患などによってリスクが変動します。
外科的治療に伴うリスク
頸動脈内膜剥離術やステント留置術などの外科的治療では、手術操作に伴う血管損傷や術後合併症のリスクがあることから、手術適応の判断には慎重な検討が大切です。
| 手術の種類 | 術中・術後合併症 |
|---|---|
| 頸動脈内膜剥離術 | 脳神経麻痺、創部感染、血腫形成 |
| ステント留置術 | 血管解離、塞栓症、再狭窄 |
| バイパス手術 | グラフト閉塞、創部感染、出血 |
薬剤相互作用による問題
複数の薬剤を併用することによる相互作用のリスクは、高齢者や多剤併用が必要な患者さんにおいて問題となります。
抗血小板薬や抗凝固薬と、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)との併用では、消化管出血のリスクが相乗的に増加することが知られており、慎重な投薬管理を行います。
薬剤の相互作用による副作用の増強や、効果の減弱を防ぐために、医療機関で服用中の全ての薬剤について伝えることが重要です。
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
基本的な検査費用
MRI検査は3割負担の場合、一回あたり8,000円から12,000円で、CT検査については、単純CTで4,000円から6,000円、造影CTでは8,000円から10,000円が一般的です。
頸動脈エコー検査は2,000円から3,000円程度の自己負担で実施できます。
薬剤治療にかかる費用
抗血小板薬は、種類によって価格が異なりますが、多くの場合1ヶ月あたり2,000円から5,000円程度の自己負担です。
| 主な薬剤分類 | 1ヶ月あたりの自己負担額(3割負担の場合) |
|---|---|
| 抗血小板薬 | 2,000円~5,000円 |
| 抗凝固薬 | 3,000円~8,000円 |
| 降圧薬 | 1,500円~4,000円 |
| 脂質異常症治療薬 | 2,000円~6,000円 |
入院時の費用内訳
入院費用は検査や治療内容によって大きく異なりますが、以下の項目が主な費用となります。
- 入院基本料 1日あたり15,000円~20,000円
- 食事療養費 1食あたり460円程度
- 投薬・注射料 1日あたり3,000円~8,000円
- 各種検査料 検査内容により変動
リハビリテーション費用
理学療養士による運動機能回復訓練は1単位(20分)あたり500円から1,000円程度で、作業療法や言語聴覚療法も同様の費用設定です。
| リハビリ種別 | 1単位(20分)あたりの自己負担額 |
|---|---|
| 理学療法 | 500円~1,000円 |
| 作業療法 | 500円~1,000円 |
| 言語聴覚療法 | 500円~1,000円 |
| 集団リハビリ | 300円~500円 |
専門的検査の費用
- 脳血流シンチグラフィー検査 一回あたり15,000円から20,000円
- 経食道心エコー検査 8,000円から12,000円
- 24時間心電図(ホルター心電図)検査 5,000円から7,000円
- 各種血液検査 一回あたり3,000円から8,000円
以上
Johnston SC. Transient ischemic attack. New England Journal of Medicine. 2002 Nov 21;347(21):1687-92.
Amarenco P. Transient ischemic attack. New England Journal of Medicine. 2020 May 14;382(20):1933-41.
Mendelson SJ, Prabhakaran S. Diagnosis and management of transient ischemic attack and acute ischemic stroke: a review. Jama. 2021 Mar 16;325(11):1088-98.
Coutts SB. Diagnosis and management of transient ischemic attack. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology. 2017 Feb 1;23(1):82-92.
Albers GW, Caplan LR, Easton JD, Fayad PB, Mohr JP, Saver JL, Sherman DG. Transient ischemic attack–proposal for a new definition. The New England journal of medicine. 2002 Nov 1;347(21):1713-6.
Levy DE. How transient are transient ischemic attacks?. Neurology. 1988 May;38(5):674-.
Daffertshofer M, Mielke O, Pullwitt A, Felsenstein M, Hennerici M. Transient ischemic attacks are more than “ministrokes”. Stroke. 2004 Nov 1;35(11):2453-8.
Khare S. Risk factors of transient ischemic attack: An overview. Journal of mid-life health. 2016 Jan 1;7(1):2-7.
Agyeman O, Nedeltchev K, Arnold M, Fischer U, Remonda L, Isenegger J, Schroth G, Mattle HP. Time to admission in acute ischemic stroke and transient ischemic attack. Stroke. 2006 Apr 1;37(4):963-6.
Sorensen AG, Ay H. Transient ischemic attack: definition, diagnosis, and risk stratification. Neuroimaging Clinics. 2011 May 1;21(2):303-13.
References