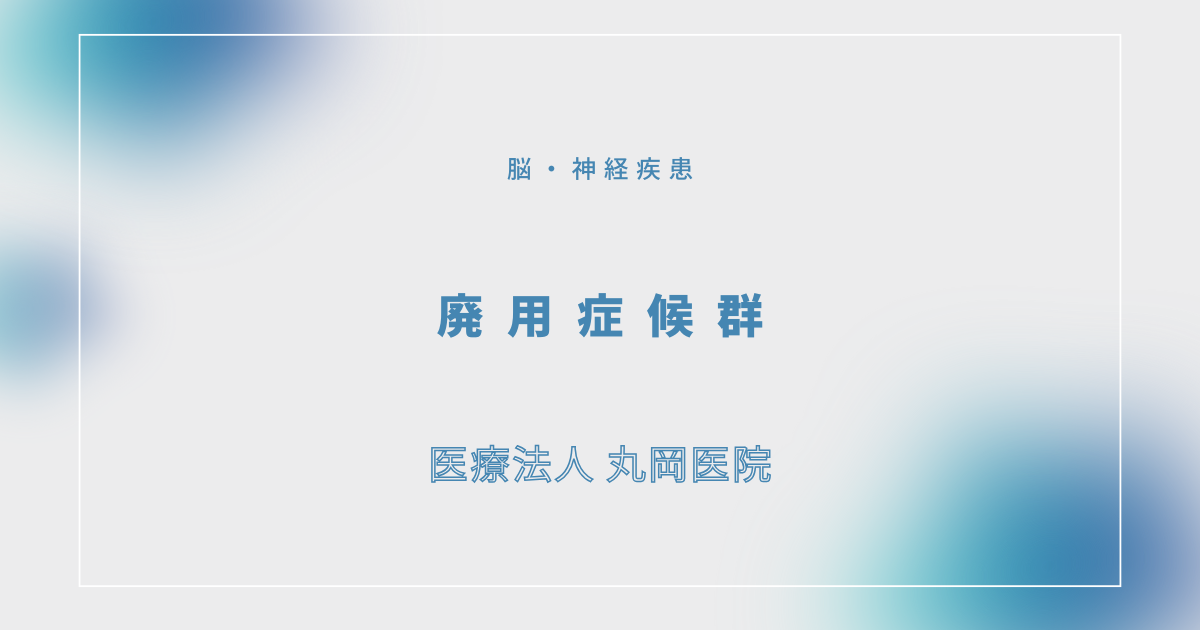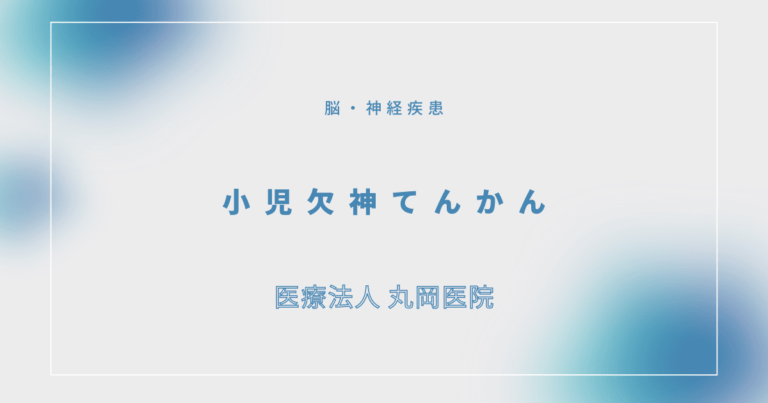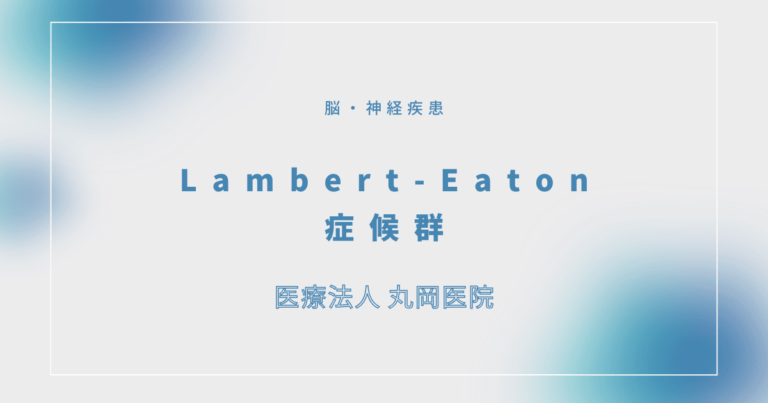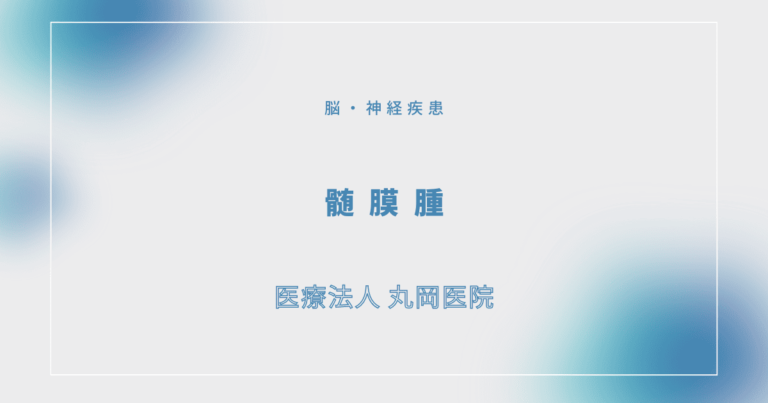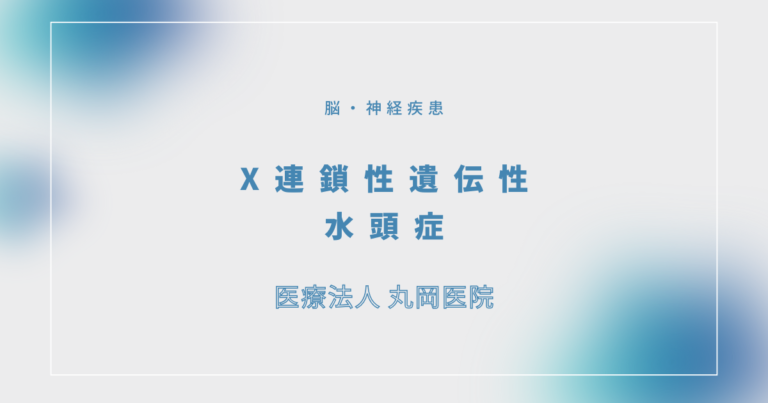廃用症候群(disuse syndrome)とは、長期にわたる安静状態や日常的な活動量の著しい低下によって引き起こされる、全身の機能が段階的に衰えていく症候群のことです。
筋肉量の減少や骨密度の低下、関節の可動域制限といった身体機能の低下だけでなく、心肺機能の低下や認知機能への影響まで及びます。
高齢者や長期療養中の患者さんに多く見られる症候群ですが、事故や怪我による長期の安静を強いられる若年層でも発症リスクがあります。
廃用症候群の主な症状
廃用症候群では、筋肉が弱くなる、関節が動きにくくなる、骨がもろくなる、心肺機能が低下する、褥瘡、血栓ができやすくなるなどの症状が現れます。
身体機能への影響
長期間体を動かさない状態が続くと、人体の様々な機能は大きな影響を受けることになります。
筋肉の衰えは最も分かりやすい変化であり、特に足の筋肉では1週間寝たきりの状態が続くと10〜15%もの筋力低下が起こります。
関節が動きにくくなる症状は、関節のまわりの組織が硬くなることで起こり、特に足首や膝の関節において顕著です。
| 身体の部位 | どのような機能変化が起きるか |
| 筋肉 | 筋線維が細くなる、力が弱くなる、疲れやすくなる |
| 関節 | 動く範囲が狭くなる、硬くなる、関節の袋が癒着する |
| 骨 | カルシウムが減少する、骨密度が低下する、骨粗鬆症になりやすい |
| 心臓と血管 | 心機能が低下する、血液の戻りが悪くなる |
循環器系への影響
心臓と肺の機能低下は、長期の運動不足によって心臓や肺の働きが徐々に弱くなっていき、心臓から送り出される血液量の減少や、体が使える酸素量の低下などが見られます。
深部静脈血栓症は足の血管の中に血の塊ができてしまう状態で、廃用症候群において注意が必要な合併症の一つです。
また、心臓への負担が増えることにより、不整脈や血圧の変動など、循環器系に関する問題が起こることがあります。
皮膚および代謝への影響
褥瘡(じょくそう)は、同じ場所が長時間圧迫されることで皮膚や皮下の組織が壊死する状態であり、仙骨部(お尻の骨の部分)や踵部(かかと)など、骨が出っ張っている部分にできやすいです。
代謝機能の変化により、体重減少や筋肉量の減少、基礎代謝量の低下などが起きることもよくあります。
注意が必要な代謝の変化
- インスリンの働きが弱くなることによる血糖値の調節異常
- タンパク質を作る力が弱まることによる筋肉の減少
- 脂肪の代謝が変化することによる体脂肪の分布の変化
- ミネラルの代謝異常による体内の電解質バランスの乱れ
神経系および内分泌系への影響
自律神経の働きが低下することにより、体温調節、汗の出方、血圧の調整などに問題が生じます。
| 神経の種類 | 症状 |
| 末梢神経 | 感覚が鈍くなる、しびれが出る、反射が遅くなる |
| 自律神経 | 体温調節が難しくなる、汗の出方が異常になる、立ったときに血圧が下がりやすい |
| 中枢神経 | バランスが取りにくくなる、姿勢を保つことが難しくなる |
内分泌系では、副腎皮質ホルモンの分泌リズムが変化することで、体の生体リズムに影響を及ぼし、また、神経の働きが遅くなることにより、運動や感覚の機能に影響が出ることもあります。
さらに、前庭機能(耳の奥にある平衡感覚を感じる器官の働き)の低下により、めまいやバランスの障害が生じることも少なくありません。
廃用症候群の原因
廃用症候群は、長期的な不活動や運動不足による身体機能の低下が引き金となり、全身の器官や組織に機能低下をもたらします。
不活動がもたらす身体への影響
不活動状態が続くと、人体の各器官や組織は本来持っている機能を徐々に失っていき、機能低下は単なる筋力低下にとどまらず、神経系や循環器系にまで広範な影響を及ぼします。
特に注目すべきなのは、脳における神経伝達物質の分泌バランスが崩れることで、認知機能や情動反応にも変化が生じることです。
廃用症候群を引き起こす要因
| 環境要因 | 身体への影響 |
| ベッド上での長期安静 | 筋繊維の萎縮と骨密度低下 |
| 関節の固定 | 関節可動域の制限と軟骨変性 |
| 活動量の著しい低下 | 心肺機能の低下と代謝異常 |
このような要因は、それぞれが独立して存在するのではなく、相互に影響し合いながら症状を複雑化させます。
原因となる生活習慣や環境因子
デスクワークの増加やスマートフォンの普及による運動不足は、若年層における発症の背景として懸念されています。
- 長時間のデスクワークによる同一姿勢の継続
- 電子機器の過度な使用による運動機会の減少
- エレベーターやエスカレーターの頻繁な使用
- 自動車での移動増加による歩行機会の減少
- 在宅勤務による活動量の低下
疾患別の廃用症候群発症リスク
| 基礎疾患 | リスク要因 |
| 整形外科疾患 | 骨折後の固定による不動期間の長期化 |
| 神経系疾患 | 麻痺による活動制限と筋力低下 |
| 循環器疾患 | 心機能低下による活動制限 |
| 呼吸器疾患 | 呼吸困難による運動回避 |
基礎疾患は、それぞれの特性に応じて異なる経路で廃用症候群の発症に関与し、単一の原因ではなく、様々な要因が重なり合って発症に至ります。
また、長期の療養生活を余儀なくされる患者さんの中には、基礎疾患による直接的な機能障害に加えて、不活動による二次的な機能低下が重複することで、予期合併症を起こすリスクが高いです。
診察(検査)と診断
廃用症候群の診察では、筋力測定、関節可動域検査、神経学的診察、血液検査などの各種検査を組み合わせながら行います。
身体診察の基本的な手順
全身の筋力を調べる方法としてMMT(徒手筋力検査)検査を行い、0から5段階で筋力を数値化することで、体のどの部分の筋力が低下しているのかを調べます。
関節の動く範囲を測る検査では、医師が関節の曲げ伸ばしを行いながら、角度計を使って測定します。
| 検査項目 | 診察のポイント |
| 筋力検査 | 左右差の確認、筋萎縮の程度、疲労のしやすさ |
| 関節可動域 | 制限の範囲、痛みの有無、左右差の確認 |
| 皮膚の状態 | 褥瘡の有無、皮膚の色調、浮腫の程度 |
| 呼吸状態 | 呼吸数、呼吸の深さ、酸素飽和度 |
神経学的診察の実際
神経学的な診察では、患者さんの反射、感覚、バランス機能などを確認していきながら、脳や神経の働きに問題がないかどうかを調べます。
深部腱反射検査では、神経の伝達に問題がないかどうかを判断し、感覚検査では、感覚が正常に伝わっているかどうかを確認することが大切です。
血液検査と画像検査
血液検査で調べる項目
- CKという筋肉の損傷を示す酵素の値を測定
- 電解質バランスを確認するためのナトリウムやカリウムの値を測定
- 栄養状態を示すアルブミンなどのタンパク質の値を測定
- 炎症の程度を示すCRPの値を測定
- 貧血の有無を確認する赤血球や血色素量を測定
画像検査の種類と目的は、次の通りです。
| 検査の種類 | 主な確認項目 |
| レントゲン検査 | 骨の密度低下、関節の変形、胸部の状態 |
| CT検査 | 筋肉の萎縮程度、深部の状態、血管の様子 |
| MRI検査 | 軟部組織の詳細、神経の圧迫状態 |
| 超音波検査 | 筋肉の厚み、血流の状態、浮腫の程度 |
その他の機能検査
心肺機能を詳しく調べるために、心電図検査や肺機能検査を実施することがあり、これらの検査では安静時の状態だけでなく、軽い運動をしたときの反応も確認することが重要です。
バランス機能を調べる検査では、患者さんに目を閉じて片足で立ってもらったり、まっすぐ歩いてもらったりすることで、平衡感覚や歩行機能の状態を確認します。
また、嚥下機能の検査では、飲み込みの様子を観察したり、嚥下造影検査を行ったりすることで、誤嚥のリスクがないかどうかを調べます。
廃用症候群の治療法と処方薬、治療期間
廃用症候群の治療には、運動療法を中心とした理学療法、作業療法、薬物療法を組み合わせた総合的なアプローチが必要です。
運動療法による機能回復
運動療法で筋力トレーニング、関節可動域訓練、有酸素運動などを段階的に進めていくことで全身の機能改善を図れます。
筋力トレーニングでは、徐々に負荷を増やしながら関節周囲の筋群を強化していき、関節可動域訓練においては、関節の動きを維持・改善するための運動を継続的に行います。
| 運動療法の種類 | 実施頻度と期間 |
| 等尺性運動 | 1日3回、2週間程度 |
| 関節可動域訓練 | 1日2回、4週間以上 |
| 有酸素運動 | 週3-4回、8週間以上 |
| バランス訓練 | 週5回、12週間程度 |
作業療法によるアプローチ
作業療法では、日常生活動作の改善を目標として、着替え、食事、整容などの基本的な動作訓練から始め、徐々に応用的な活動へと移行していくことが理想的です。
特に上肢機能の回復においては、手指の巧緻性訓練や道具操作訓練を含めた総合的なアプローチが求められます。
作業療法プログラム
- 基本的日常生活動作(ADL)訓練
- 手指の巧緻性訓練
- 道具・器具の操作訓練
- 応用的動作訓練
- 環境適応訓練
薬物療法による支援
| 薬剤分類 | 主な効果と使用目的 |
| 筋弛緩薬 | 筋緊張の緩和と痛みの軽減 |
| 循環改善薬 | 血液循環の促進と代謝向上 |
| ビタミン製剤 | 神経機能の維持と回復促進 |
| 消炎鎮痛薬 | 炎症と疼痛のコントロール |
薬物療法は、運動療法や作業療法の効果を高めるサポート的な役割を果たし、ダントロレンナトリウムなどの筋弛緩薬を用いて過度な筋緊張を和らげます。
循環改善薬では、プロスタグランジンE1製剤などを使用して末梢循環を改善し、組織の代謝を促進することで機能回復を後押しすることが可能です。
治療期間と経過
初期の2週間は基本的な運動療法と薬物療法を組み合わせ、その後4週間程度かけて段階的に運動強度を上げていくことで、機能回復を目指します。
入院治療においては、理学療法士による運動療法と作業療法士による生活動作訓練を並行して行うことで、より効率的な機能回復が望めます。
廃用症候群の治療における副作用やリスク
廃用症候群に対するリハビリテーションや薬物療法には、過度な運動負荷による関節損傷や、薬剤による副作用などがあります。
運動療法に伴う身体的リスク
過度な運動負荷は特に高齢者においては、骨折や腱断裂などの重篤な合併症を起こす危険性があるので注意が必要です。
さらに、運動療法中の急激な血圧上昇や不整脈の出現は、循環器系への負担を増大させ、心臓に過度なストレスを与えることもあります。
| リスク要因 | 予測される合併症 |
| 過度な運動負荷 | 筋肉損傷・関節炎 |
| 急激な体位変換 | 起立性低血圧・めまい |
| 持続的な圧迫 | 褥瘡・末梢神経障害 |
| 不適切な運動強度 | 心不全の悪化・不整脈 |
薬物療法における副作用
筋弛緩薬の使用に伴う眠気や脱力感は、転倒のリスクを高める要因となり、骨折などの二次的な合併症につながることがあります。
循環改善薬による副作用は、血圧低下や、消炎鎮痛薬による胃腸障害などです。
運動療法施行中に見られる副作用
- 筋弛緩薬による過度の脱力や眠気
- 消炎鎮痛薬による胃部不快感や消化器症状
- 循環改善薬による血圧変動や頭痛
- ビタミン製剤によるアレルギー反応
- 抗炎症薬による腎機能への影響
二次的な合併症のリスク
| 合併症の種類 | 発生要因 |
| 深部静脈血栓症 | 長時間の臥床・不動 |
| 褥瘡 | 持続的な圧迫・栄養状態低下 |
| 誤嚥性肺炎 | 嚥下機能低下・唾液分泌低下 |
| 関節拘縮 | 関節可動域制限・筋緊張亢進 |
治療費について
実際の治療費(医療費)が以下説明より高額になるケースが多々ございます。以下記載内容について当院では一切の責任を負いかねます事を予めご了承下さい。
基本的な治療費の構成
入院治療では、一般病棟での1日あたりの基本料金に加え、リハビリテーション料、投薬料、各種検査料などが加算されます。
外来での治療費は、リハビリテーション料を中心に投薬料や検査料が必要です。
| 治療内容 | 一般的な費用(3割負担の場合) |
| 外来リハビリ(1回) | 1,500円~2,500円程度 |
| 理学療法(1回) | 1,800円~3,000円程度 |
| 作業療法(1回) | 1,800円~3,000円程度 |
| 言語聴覚療法(1回) | 1,800円~3,000円程度 |
| 入院費(1日) | 3,000円~8,000円程度 |
投薬治療にかかる費用
筋緊張を和らげる薬剤や、痛み止めなどの薬物療法にかかる費用は、内服薬の場合、1か月あたり3,000円から10,000円程度かかります。
検査費用の内訳
定期的な検査費用
- 血液検査 1回あたり3,000円~5,000円程度
- 画像検査(レントゲン) 1回あたり2,000円~4,000円程度
- MRI検査 1回あたり15,000円~25,000円程度
- CT検査 1回あたり10,000円~20,000円程度
- 筋電図検査 1回あたり4,000円~8,000円程度
補助具やリハビリ用具の購入費用
補助具やリハビリ用具の購入費用は、簡単な自主トレーニング用具で数千円から、より専門的な機器では数万円程度になる場合があります。
| 補助具の種類 | 価格帯 |
| 歩行補助杖 | 3,000円~15,000円 |
| 車椅子 | 30,000円~150,000円 |
| 関節装具 | 5,000円~30,000円 |
| リハビリマット | 3,000円~20,000円 |
以上
Bortz II WM. The disuse syndrome. Western Journal of Medicine. 1984 Nov;141(5):691.
Ardila Suárez EF, Escalada‐Hernández P. Proposal of nursing diagnosis “adult disuse syndrome”: A conceptual derivation and integrative review. International Journal of Nursing Knowledge. 2024 Jul;35(3):205-12.
Wakabayashi H, Sashika H. Association of nutrition status and rehabilitation outcome in the disuse syndrome: a retrospective cohort study. General Medicine. 2011;12(2):69-74.
van Wilgen CP, Dijkstra PU, Versteegen GJ, Fleuren MJ, Stewart R, van Wijhe M. Chronic pain and severe disuse syndrome: long-term outcome of an inpatient multidisciplinary cognitive behavioural programme. Journal of Rehabilitation Medicine. 2009 Feb;41(3):122-8.
Norimoto M, Yamashita M, Yamaoka A, Yamashita K, Abe K, Eguchi Y, Furuya T, Orita S, Inage K, Shiga Y, Maki S. Early mobilization reduces the medical care cost and the risk of disuse syndrome in patients with acute osteoporotic vertebral fractures. Journal of Clinical Neuroscience. 2021 Nov 1;93:155-9.
Usuda D, Takanaga K, Sangen R, Higashikawa T, Kinami S, Saito H, Kasamaki Y. Abdominal compartment syndrome due to extremely elongated sigmoid colon and rectum plus fecal impaction caused by disuse syndrome and diabetic neuropathy: a case report and review of the literature. Journal of Medical Case Reports. 2020 Dec;14:1-6.
Usuda K, Uesaka T, Okubo T, Shimada T, Shimada C, Ito H, Douko N, Aoki T, Takada M, Yokoyama K, Shimizu M. 688 How much do disuse syndrome patients improve with convalescent rehabilitation? Assessment of improvement. Balneo and PRM Research Journal. 2024 Aug 3;15(2).
Sonoda S. Immobilization and disuse syndrome. The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine. 2015:265-71.
Kim S, Cho W, Kim B. Application of Robotic Rehabilitation to Patients with Disuse Syndrome: A Case Report. Journal of International Academy of Physical Therapy Research. 2023 Jun;14(2):2840-5.
Fernandes T, Mendes E, Preto L, Novo A. Experience of a mobilization and active exercise program on the range of motion of bedridden patients with disuse syndrome. Jounal of Rehabilitation Medicine. 2015:791-2.